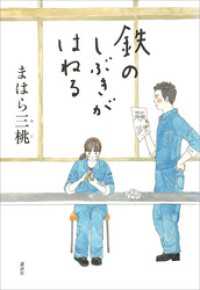
『鉄のしぶきがはねる』を読み終えて、しばらくページを閉じたままぼんやりしてしまいました。高校生たちが旋盤と真剣に向き合う姿に、思っていた以上に心を持っていかれてしまったからです。 工業高校の機械科で、しかも女子は主人公の心(しん)ただひとり。舞台だけ聞くと少し硬派な印象ですが、読んでみると「職人の世界」よりもむしろ、「自分は何に本気になれるのか」を探していく青春小説だと感じました。切削音が鳴り響く実習室や、鉄のしぶきが飛び散る旋盤の前で、彼らの迷いや葛藤がじわじわと熱を帯びていきます。 私は機械加工の知識がほとんどなく、最初は専門用語が難しいかも…と構えていたのですが、物語に引き込まれているうちに、いつの間にか「もっとこの世界を知りたい」と思っている自分がいました。青春の「ときめき」を恋愛ではなく、ものづくりに全振りしている感じが新鮮で、とても気持ちの良い読書体験でした。
【書誌情報】
| タイトル | 鉄のしぶきがはねる |
|---|---|
| 著者 | まはら三桃【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2017/03 |
| ジャンル | 絵本・児童書・YA・学習 |
| ISBN | 9784062167611 |
| 価格 | ¥1,265 |
工業高校機械科1年唯一の女子、冷たく熱い鉄の塊に挑む!めざせ「ものづくり」の真髄!!「高校生ものづくりコンテスト」旋盤青春物語。「高校生ものづくりコンテスト」とは……。全国の工業高校生の精鋭たちが、技術・技能を競い合う大会。「高校生技能五輪」「ものづくり甲子園」などとも呼ばれ、日本の高校生による「ものづくり」の頂点をめざす大会として注目を集めている。
本の概要(事実の説明)
物語の舞台は、北九州の工業地帯にある工業高校。主人公の心は、機械科に通う唯一の女子生徒です。実家はかつて金属加工の町工場で、祖父や父の背中を見て育った彼女ですが、とあるトラブルをきっかけに工場は倒産。その出来事が心の中にしこりとして残り、「機械にはもう関わりたくない」と感じるようになっています。 高校では、より「今っぽい」コンピュータ系の進路を目指し、当初はコンピュータ研究部に所属する心。しかし、授業で見せた旋盤の腕をきっかけに、「ものづくり研究部(通称・もの研)」から声をかけられます。文化祭までの助っ人のつもりで入った部活で、彼女はふたたび鉄と機械の世界に向き合うことになります。 もの研の目標は、高校生版の技能五輪ともいえる「高校生ものづくりコンテスト」出場と全国制覇。原口先輩をはじめ、個性豊かな部員たちと共に、心は旋盤加工の技術を磨きながら、自分の中に眠っていた「ものづくりが好きだ」という気持ちを少しずつ認めていきます。 対象読者は中高生だと感じましたが、職人仕事の世界観や工業高校の日常が丁寧に描かれているので、大人が読んでも十分に楽しめる作品だと思いました。
印象に残った部分・面白かった点
タイトルにもなっている「鉄のしぶき」は、金属を削ったときに飛び散る切りくずのことです。最初は比喩的な表現なのかなと思っていたのですが、読み進めるうちに、それが物理的な現象であると同時に、心たち高校生の胸の中で飛び散る感情のしぶきにも重なっているように感じました。 心は、工場倒産の苦い記憶から、機械に対して複雑な感情を抱えています。それでも旋盤の前に立つと、体が覚えている感覚がよみがえり、「やっぱり好きかもしれない」と認めざるを得なくなる。その瞬間の戸惑いと高揚感が、とても丁寧に描かれていて印象的でした。 また、「ものづくりは楽しい」という一文の後に続く、「でもそれは簡単な楽しさではなく、苦しみと隣り合わせの、もっと奥にある喜びだ」というニュアンスの記述も心に残りました。おいしいものを食べる・音楽を聴くといった分かりやすい快楽とは違う、「自分で手を伸ばして取りに行く種類の楽しさ」。その感覚は、好きなことに本気で取り組んだことのある人なら、ジャンルが違っても共感できるのではないかと思います。
本をどう解釈したか
この作品は、一見「旋盤青春小説」のように見えますが、奥には「デジタルかアナログか」という問いが流れているように感じました。心は、倒産した町工場の姿を見て、「これからはプログラミングだ」「コンピュータ制御の方が将来性がある」と考えます。それはある意味で、とても現実的な判断です。 一方で、旋盤の前に立つと、デジタルでは味わえない種類の充実感や、機械と体で対話しているような感覚が湧き上がってくる。この「頭で描く合理性」と「身体が求める楽しさ」のズレこそが、心の葛藤の正体なのだと思いました。 ものづくり研究部でのエピソードを通して、作品は「アナログ回帰」を押しつけているわけではありません。むしろ、コンピュータも機械加工も、どちらも「人の手と頭」が関わる仕事だと示しているように感じました。機械を制御するだけでなく、自分の心も制御できるのか――その試金石として、旋盤という具体物が置かれているように思えます。 また、男子ばかりの工業高校で、女子である心が感じる居心地の悪さや、期待と偏見が入り混じった視線も描かれています。とはいえ、作品は「女子だからつらい」という一点に寄せるのではなく、「好きなことを貫こうとする人は誰であっても孤独を抱える」という普遍的なテーマへと広げていきます。そのバランス感覚が、とても心地よいと感じました。
読後に考えたこと・自分への影響
この本を読みながら、何度も「一生懸命になっているとき、それが本物かどうか、人は時々試される」という趣旨の言葉を思い出しました。心にとっての試練は、単に大会で勝てるかどうかだけではなく、「本当に機械が好きなのか」「過去の出来事とどう折り合いをつけるのか」という内側の問題でもあります。 私自身、何かに真剣に取り組んでいるときほど、「これでいいのか」「別の道の方が楽なのでは」と迷いが出てきます。心や原口先輩たちの姿を追いかけているうちに、「迷うこと自体が、本気で向き合っている証拠なのかもしれない」と感じました。 もうひとつ印象的だったのは、「機械に人偏をつけると何と読むか」というエピソードです。答え自体はここでは伏せますが、ただの言葉遊びではなく、「機械と人間の関係性」を象徴するような問いかけになっています。機械を「使う」側と「使われる」側、どちらが主導権を握っているのか――そのバランスを考えたくなる一場面でした。 読み終えたあと、「自分にとっての『鉄のしぶき』は何だろう」と考えました。見た目には地味だけれど、削って削って、ようやく形になっていく何か。すぐには結果が出なくても、手を動かし続けることでしかたどり着けない領域があるのだと、改めて感じさせてくれる物語でした。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この作品は、がっつり集中して読みたいタイプの本だと感じました。おすすめのシチュエーションは、静かな休日の午後です。できればスマホを少し離れた場所に置いて、ページの向こうから聞こえてくる切削音や、工業高校の空気に浸るような気持ちで読み進めると、物語の世界に入りやすいと思います。 もう一つのおすすめは、「自分の進路や仕事について悩んでいるとき」です。今の道でいいのか、もっと別の選択肢があるのではないか――そんなモヤモヤを抱えているときに読むと、心が「デジタルかアナログか」で揺れる姿が、自分ごとのように感じられるはずです。 読み終えたあと、すぐに答えが出るわけではありませんが、「とりあえず今できることを一生懸命やってみよう」と、ほんの少し前向きになれる読書時間になると思いました。
『鉄のしぶきがはねる』(まはら三桃・著)レビューまとめ
『鉄のしぶきがはねる』は、工業高校という少しマニアックな舞台設定でありながら、描かれているのはとても普遍的な青春の悩みと成長でした。町工場の娘としての過去を抱えた心が、鉄のしぶきとともに自分の進む道を削り出していく姿に、何度も胸が熱くなりました。
ものづくりが好きな人はもちろん、「自分の本気になれることって何だろう」と立ち止まっている人にもおすすめしたい一冊です。読後、工場から聞こえる機械音や、どこかの作業場で飛び散る鉄のしぶきを想像しながら、心たち高校生の姿を思い出してしまうような、余韻の長い物語でした。


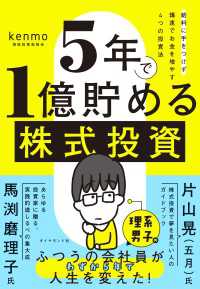
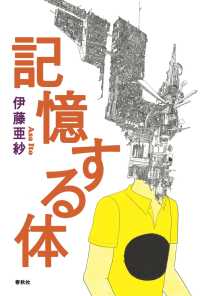
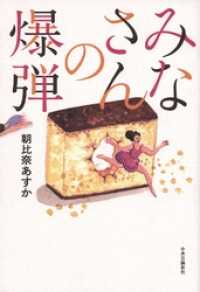
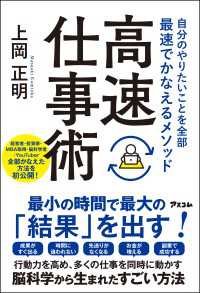

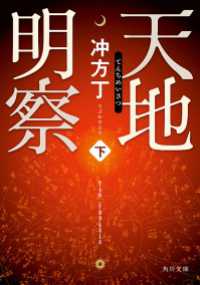

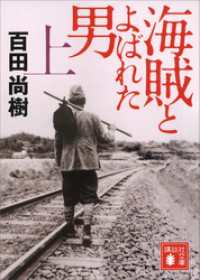
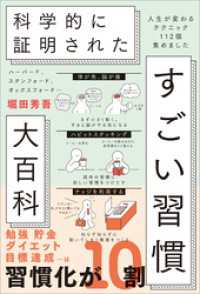


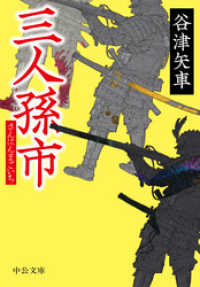
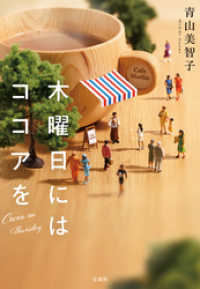
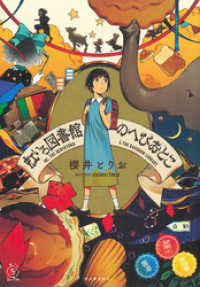


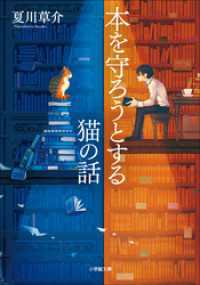


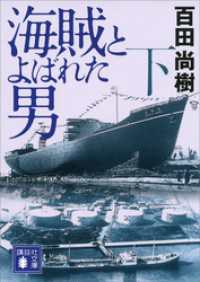
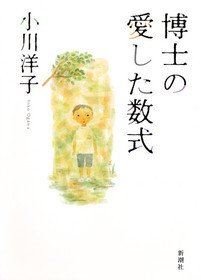
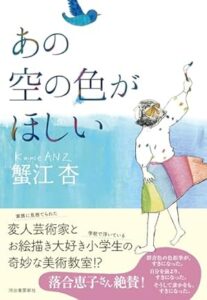
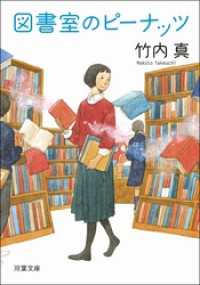
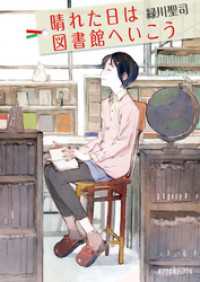
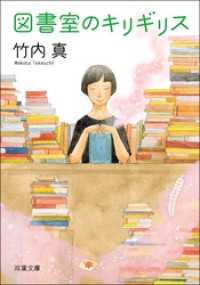

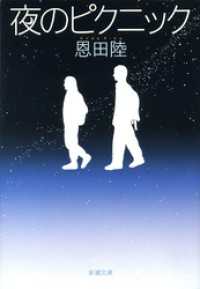
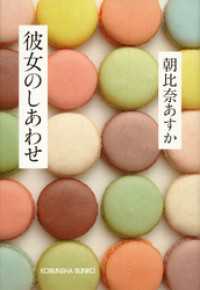
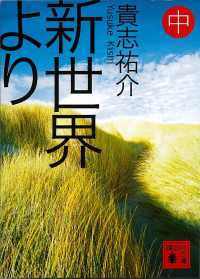


コメント