
『天地ダイアリー』は、マスクが手放せない中学一年生の男の子・木下広葉が主人公の物語です。転校先での人間関係に失敗した過去から、「もう傷つきたくない」と自分を守るためにマスクを手放せなくなった広葉。新しい中学校でも、クラスの「上層」「下層」を観察しながら、できるだけ目立たないように過ごそうとします。読んでいて、その息苦しさがじわじわと伝わってきました。 そんな広葉が、消極的な理由で選んだ「栽培委員会」で、先輩や同級生、そして植物たちと関わりながら少しずつ表情を取り戻していきます。花壇の花やゴーヤ、ヘチマの世話を通して、自分の気持ちや他人の思いに向き合っていく姿はとてもささやかで、でも確かな変化でした。 派手な事件や大きなドラマが起こるわけではありません。けれど、クラスの空気や友だちとの距離感に揺れる中学生の日常が、とてもリアルな温度で描かれていて、気づけば広葉の「内側の日記」を読むような気持ちでページをめくっていました。
【書誌情報】
| タイトル | 天地ダイアリー |
|---|---|
| 著者 | ささきあり/高杉千明 |
| 出版社 | フレーベル館 |
| 発売日 | 2021/03 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784577046982 |
| 価格 | ¥1,540 |
中1の広葉は過去のトラウマから軽度のマスク依存症に。新しい環境で出会った個性的な栽培委員らと植物を育て、自身も成長する。
本の概要(事実の説明)
本作は、中学生向けの児童文学でありながら、大人が読んでも刺さる「人間関係」と「自己肯定感」がテーマの成長ストーリーだと感じました。主人公の木下広葉は、転勤族の家庭で育ち、転校先のクラスで孤立した経験から、マスクを「防護服」のように身につけています。中学入学とともに新しい街・新しい学校へ。そこでも同じ失敗をしないように、クラスの序列を観察しながら、波風を立てないことだけを意識して生活を始めます。 そんな広葉が選んだ栽培委員会は、いわゆる「スクールカースト下層」が集まる、地味で目立たない委員会だとされています。でも、実際は先輩たちの園芸スキルも活動も本格的で、季節ごとの花壇づくりやゴーヤ、ヘチマ、ペチュニアなどの世話を通して、きちんと「責任」と「自分たちの役割」が生まれていきます。 クラスメイトとのちょっとしたすれ違いや、花壇づくりをめぐる意見の衝突は、中学生にとっては大きな事件です。その揺れを、広葉の視点から丁寧に描き出しているので、「その感じ、わかる…」と何度も頷きたくなりました。いじめ描写で読者を追い詰めるタイプの作品ではなく、「どうやって自分の殻から一歩出るか」に焦点を当てた、やさしめのトーンなのも読みやすいところです。 悩み多き中学生はもちろん、かつて中学生だった大人にも「こんな空気、あったな」と思い出させてくれる一冊だと感じました。
印象に残った部分・面白かった点
一番印象に残ったのは、植物と広葉の心が並行して描かれているところです。手をかけないとすぐに弱ってしまう花壇の花、切り戻した途端に元気を取り戻すペチュニア、土を掘り起こし空気を入れ替える「天地返し」。どれも園芸の作業なのですが、そのひとつひとつが広葉の変化と重なっていて、読みながら「人間も同じだな」と何度も思いました。 マスクをして、クラスではなるべく目立たず、相手の表情ばかりを気にしていた広葉は、最初、花に対してもどこか距離を置いています。それが、自分の担当花壇の花がしおれていきそうになると、急にそわそわし、気になって仕方なくなる。その様子に、「ああ、この子は本当はすごく真面目で、優しいんだな」と感じて、胸がきゅっとなりました。 また、栽培委員会の先輩たちが、ちょっと変わっているけれど温かいのも良かったです。花をアイドルに例える独特のネーミングセンスや、「植物は世話をしなければ枯れるし、水をやりすぎても枯れる」という当たり前だけど重い一言。そこから、「人との距離感」について自然と考えさせられました。 終盤、広葉が「相手を知ろうとすることと、心を開いて自分を知ってもらう努力をしないと、親しい関係なんて築けない」と気づく場面も、とても印象的でした。それは大人でもなかなか腹に落としきれない真理で、その言葉が広葉の口から出てくるまでの積み重ねが丁寧だからこそ、すっと心に入ってきたのだと思います。
本をどう解釈したか
この作品は、「スクールカースト」や「マスク依存」という現代的なキーワードを扱いながらも、根っこにはとても古典的なテーマ――「自分をどう受け入れ、他人とどうつながるか」があると感じました。 広葉は、他人に傷つけられることを恐れて、常に「どう思われているか」を気にし続けています。その結果、自分の表情をマスクで隠し、クラスのヒエラルキーを観察し、「ターゲットにならない立ち位置」を探してしまう。これは、SNSや噂話があふれる今の中高生にとって、かなりリアルな肌感覚なのではないかと思いました。 そんな広葉が変わっていくきっかけが、「勝ち負け」と無縁に見える栽培委員会だというのも象徴的です。植物は、人の顔色をうかがいません。水が多すぎればしおれてしまうし、肥料が足りなければ花が咲かない。そこには、「みんなからどう見えるか」とは別の物差しがあり、「必要なことをするかどうか」というシンプルな関係だけが存在しています。 その世界に身を置くことが、広葉にとっての「天地返し」のようだと感じました。過去の痛みや、スクールカーストへの過剰な意識という硬い土を、一度ひっくり返し、空気を入れ直す作業。その中で、「自分がどう見られるか」ではなく、「自分は何を感じているのか」「本当はどうしたいのか」に気づいていく。タイトルの「天地ダイアリー」には、そんな心の耕し直しも含まれているように思えました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えて一番強く感じたのは、「人間関係は自分だけではどうにもならないけれど、自分の態度次第で変わる余地がある」という、少し心強い事実です。広葉は最初、クラスでの自分の立ち位置を「上層・下層」という外側の基準でしか見ていませんでした。でも、栽培委員会を通して出会った人たちは、「どの層にいるか」よりも、「何をしたいか」「目の前の花や人とどう向き合うか」で広葉を見てくれる存在でした。 その関わりの中で、広葉自身も、「嫌われないように」ではなく「ちゃんと相手を知ろうとすること」「自分の気持ちを伝えようとすること」を少しずつ選べるようになっていきます。もちろん、現実の学校生活はこの物語ほどきれいにいかない場面も多いと思います。それでも、「自分から歩み寄ってみる」「怖くても一言だけ本音を足してみる」という、小さな一歩の重要さをあらためて教えてもらった気がしました。 また、植物と人との重ね方から、「成長には時間がかかるし、失敗も込みだ」という当たり前のことも、優しく再確認させられます。切り戻しや天地返しのように、一度傷ついたり、崩れたりするプロセスがあっても、その先にまた新しい芽が出るかもしれない。そう考えると、自分のこれまでの失敗や、人間関係の行き違いも、少しだけ違う角度から見られるようになると感じました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この本は、心が少し疲れているときや、人間関係でモヤモヤしているときに、ゆっくり読みたい一冊です。たとえば、予定のない休日の午後、暖かい飲み物を用意して、ソファやベッドの上で一章ずつ味わうのが合っていると感じました。章ごとの区切りがはっきりしているので、「今日はここまで」と読み進めやすく、気づいたら広葉の心の変化を一緒にたどっている、そんな読書時間になります。 学校の先生や保護者が読むなら、連休の合間など、少し時間に余裕のあるときに一気読みするのもおすすめです。自分自身の思春期を振り返りながら、今目の前にいる子どもたちのことも重ねて考えられるので、読後しばらくはクラスや家庭での子どもたちの表情がいつもと違って見えるかもしれません。静かな時間にじっくり向き合うことで、この物語が持つやわらかい余韻を、いちばん深く味わえると思いました。
『天地ダイアリー』(ささきあり・著)レビューまとめ
『天地ダイアリー』は、マスクが外せない中一男子と、栽培委員会の植物たちの成長を並走させながら、「自分を守ること」と「人とつながること」のバランスをそっと問いかけてくる物語でした。劇的ではないけれど確かな変化が描かれていて、読み終えた後、「自分ももう少しだけ本音で人と話してみようかな」と静かに背中を押されるような感覚が残ります。中学生世代にはもちろん、かつて同じようにクラスの空気を気にしていた大人にも、ぜひ手に取ってほしい一冊だと感じました。


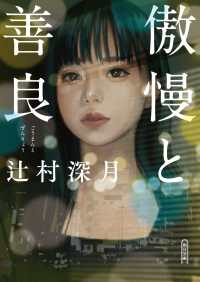
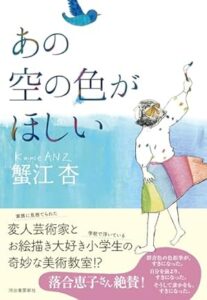

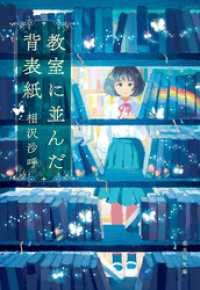
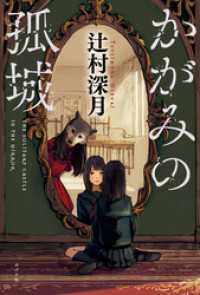

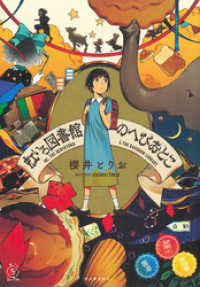
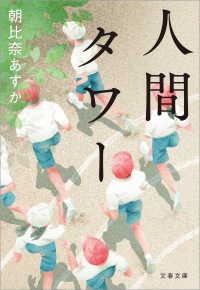
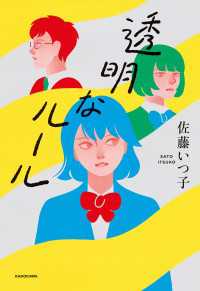
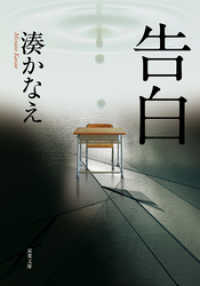
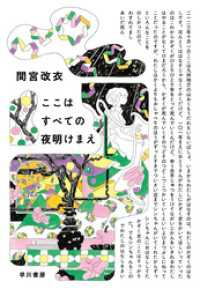
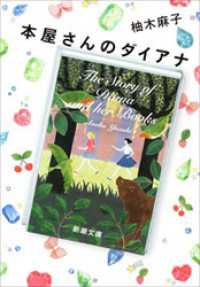
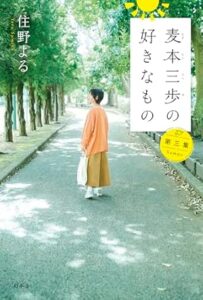
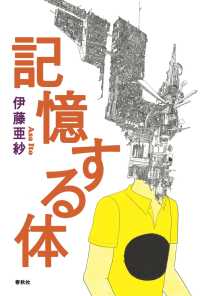

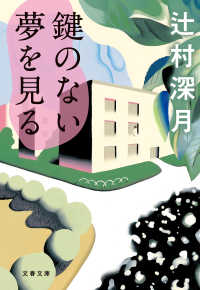
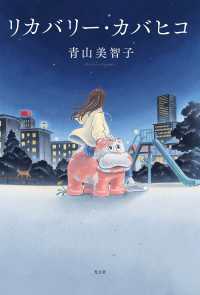


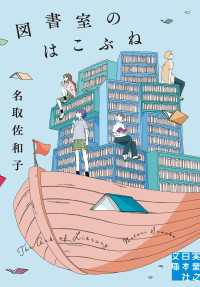
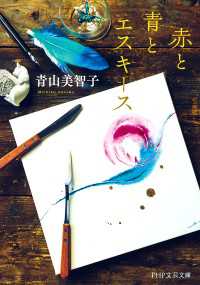
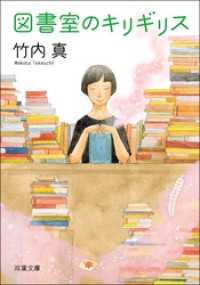
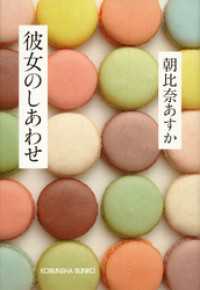
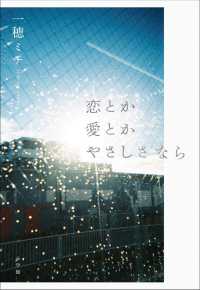

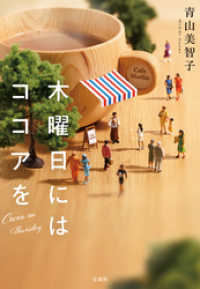
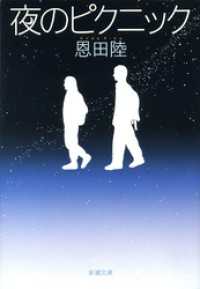
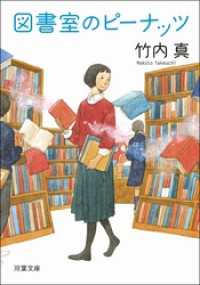
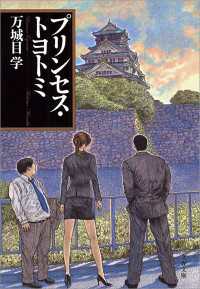
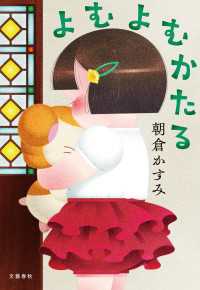
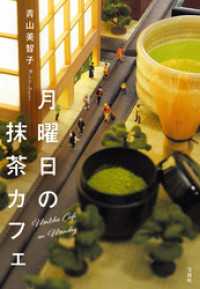
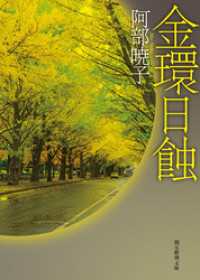
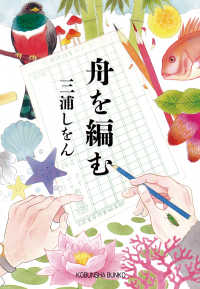

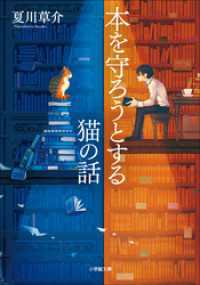
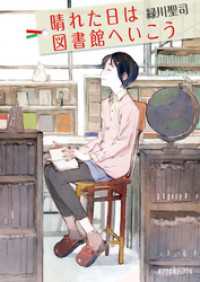
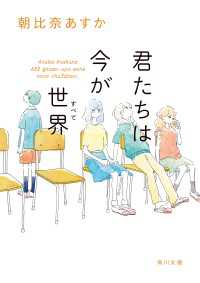
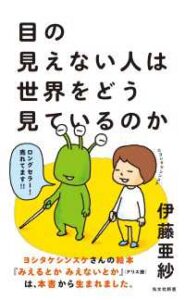
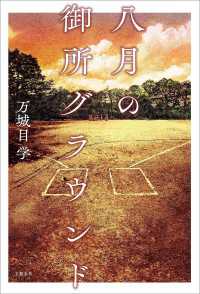
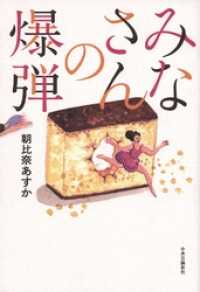

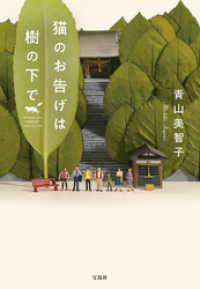
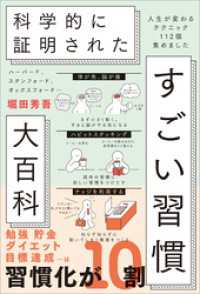
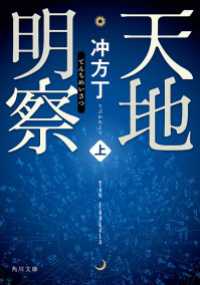


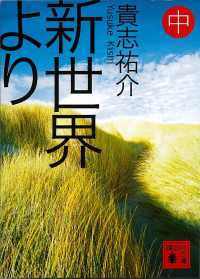
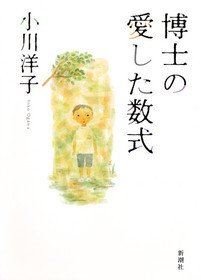


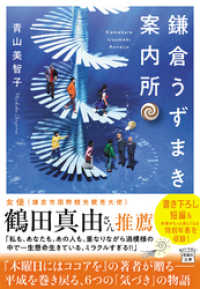


コメント