
『手の倫理』を読みながら、私は何度も自分の手を見つめ直していました。介護や看護の現場にいるわけではないのに、「ふれる」と「さわる」の違いについてこれほど考えさせられるとは思っていなかったからです。 きっかけになったのは、「不道徳だからこそ倫理的でありうる」という一文でした。道徳が「こうすべき」と行動を決めつけるのに対し、倫理は状況ごとに迷い、悩みながら決めていくもの。触れるという行為が、まさにその“迷い”の中でしか立ち上がらないのだと感じた瞬間、ページをめくる手が一気に加速しました。 私は普段、仕事として他人に触れることはほとんどありません。それでも、子どもや家族の肩にそっと手を置いたり、友人をハグしたりするたびに、「今のこれは“ふれる”だったかな? “さわる”になっていなかったかな?」と、自分の手つきを振り返るようになりました。この本は、特定の専門職だけではなく、誰の生活にも静かに入り込んでくる一冊だと感じました。
【書誌情報】
| タイトル | 講談社選書メチエ 手の倫理 |
|---|---|
| 著者 | 伊藤亜紗【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2020/10 |
| ジャンル | 人文 |
| ISBN | 9784065213537 |
| 価格 | ¥1,705 |
人が人にさわる/ふれるとき、そこにはどんな交流が生まれるのか。介助、子育て、教育、性愛、看取りなど、さまざまな関わりの場面で、コミュニケーションは単なる情報伝達の領域を超えて相互的に豊かに深まる。ときに侵襲的、一方向的な「さわる」から、意志や衝動の確認、共鳴・信頼を生み出す沃野の通路となる「ふれる」へ。相手を知るために伸ばされる手は、表面から内部へと浸透しつつ、相手との境界、自分の体の輪郭を曖昧にし、新たな関係を呼び覚ます。目ではなく触覚が生み出す、人間同士の関係の創造的可能性を探る。
本の概要(事実の説明)
『手の倫理』は、「手」と「触覚」を軸に、人と人との関わり方を問い直すノンフィクションです。著者の伊藤亜紗さんは、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』『記憶する体』などでも身体と社会の関係を考えてきた研究者。本書では、視覚や聴覚が中心になりがちなコミュニケーションから一歩離れ、「触れる」「触られる」というとても身体的なやりとりに光を当てています。 本の中では、「さわる」と「ふれる」が丁寧に区別されます。「さわる」は一方向的で、検査や触診のように“用件のある”接触。一方「ふれる」は、相手と自分が同時に影響を受け合う、双方向的な行為として描かれています。ブラインドランナーと伴走者を結ぶロープ、ラグビーのスクラム、子どもの額にそっと触れる母の手…さまざまな具体例を通して、抽象的な議論がとても身近なものとして立ち上がってきます。 さらに、「道徳」と「倫理」の違い、「安心」と「信頼」の違いなど、抽象的な言葉も、介護現場のエピソードや「注文をまちがえる料理店」の話、見えないスポーツ観戦の試みなどと結びつけて説明されていきます。哲学・倫理と聞くと構えてしまいそうですが、日常の具体例が多いので、私にとっては思っていたよりずっと読みやすい一冊でした。 この本は、介護・医療・教育の現場にいる人はもちろん、家族との距離感に悩んだことのある人、自分の“善意”の扱いに迷うことがある人にも向いていると感じました。
印象に残った部分・面白かった点
いちばん印象に残ったのは、「ふれてほしいときに“さわられる”と暴力に感じる」という指摘です。ケアの場面では特に、「ふれる」と「さわる」が混ざってしまう危うさがある、と本書は何度も警告します。たとえば、触診が必要な場面では、あまりに感情を乗せた“ふれる”ほうがむしろ不快になり得る。一方で、慰めてほしいときに、単なる作業として“さわられる”と、心が大きく傷ついてしまう。その線引きは、とても繊細で、マニュアル化できないところにあるのだと感じました。 また、「安心」と「信頼」の違いも心に残りました。結果があらかじめ約束されている状態が「安心」であるのに対して、「信頼」は不確実性を含んだまま相手を預けること。本書では、「安心」は社会側が整備するもの、「信頼」は一人ひとりの関係の中で育まれるものとして描かれていきます。ブラインドマラソンの伴走では、お互いの足音やロープのテンション、わずかな力加減から相手の状態を読み取っていく。その共鳴感覚は、「結果が保証された安心」ではなく、「互いに預け合う信頼」そのものだと感じました。 さらに、「不道徳だからこそ倫理的でありうる」という逆説的なフレーズも、じんわりと効いてきます。道徳的に“正しい”とされる距離の取り方、触れ方だけでは、救えない場面が確かにある。相手の領域に踏み込むリスクを引き受けるからこそ、触れることが意味を持つ時もある。その危うさと必要性を、著者は真正面から引き受けているように思えました。
本をどう解釈したか
この本を通して私が一番強く感じたのは、「触覚は、私たちの倫理観そのものを映し出す鏡なのかもしれない」ということでした。視覚や聴覚のコミュニケーションは、どこか“安全な距離”を前提にしています。画面越しの会話やチャットのやりとりでは、相手に物理的に触れることはありませんし、距離を保ったまま関係を続けることができます。 一方で、「ふれる/さわる」という行為は、距離がゼロ、あるいはマイナスになるコミュニケーションです。だからこそ、そこには親密さと暴力性が同居してしまう。その両極をどう扱うかが、「手の倫理」なのだと読み取りました。著者は、触覚をめぐる倫理を“きれいごと”として語るのではなく、介助と性的な領域が重なってしまう危うさ、ケアする側とされる側の非対称性など、目をそらしたくなる部分にもきちんと触れています。 同時に、この本は「多様性の尊重」という言葉への違和感も掘り下げています。多様性を口実に、互いに触れ合わないまま孤立していく現代の人間関係。本当に必要なのは、「違いを尊重する」ことだけではなく、「お互い傷つくかもしれないリスクを抱えながら、どう触れ合うかを一緒に迷うこと」なのかもしれない、と感じました。 私は、この本の「倫理」は、正解を示すものではなく、「一緒に迷うための問い」を提示するものだと受け取りました。どこまで踏み込んでいいのか、どこから先は踏み込みすぎなのか。家族やパートナー、ケアの現場だけでなく、友人関係にも通じる問いとして、静かに残り続ける本だと思います。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えてから、私は日常のささいな場面で、自分の手の動きを意識するようになりました。子どもが不安そうな表情をしているとき、そっと背中に手を当てる。その瞬間、「今の私は“ふれて”いるのかな、それとも“さわって”しまっているのかな」と、ほんの一瞬ですが立ち止まることが増えました。 また、「安心」と「信頼」の違いを考えることで、自分の人間関係のパターンも見えてきたように思います。つい「相手から絶対に嫌われないように」「この関係が壊れないように」と、安心を最優先してしまうことが多いのですが、本当に深い関係は、不確実さを抱えたまま信頼を差し出さないと始まらないのかもしれません。触れることは、その象徴のようにも感じました。 もう一つの大きな気づきは、「家族こそ要注意」という言葉にハッとしたことです。近しい相手ほど、「これくらい触れても大丈夫」「このくらい踏み込んでいいはず」と思い込みがちです。でも本当は、いちばん慎重に、“ふれる”と“さわる”の境界を意識しないといけない相手なのかもしれません。 この本を読んでから、私は「相手のため」と思ってした行為を、一度自分の中で振り返るクセがつきました。それが少し面倒に感じるときもありますが、その“面倒さ”こそが、著者の言う「倫理」の入り口なのだろうと感じています。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
『手の倫理』は、感情が大きく揺さぶられるドラマチックな物語ではありませんが、じんわりと心の深いところに入り込んでくる本だと感じました。なので、読み方としても、一気読みより「少し読んでは、ぼんやり考える」リズムが合っていると思います。 私自身は、静かな休日の午前中や、家族が寝静まったあとに一人でページを開く時間がいちばんしっくりきました。手のエピソードやケアの現場の描写を読んだあと、自分の過去の経験――親に手を引かれた記憶や、子どもの熱をはかったときの額の感触、誰かの肩にそっと触れた瞬間――がいろいろと浮かんできて、それを味わう余白が欲しくなったからです。 気持ちを整えたいときにも、相性の良い一冊だと思います。イライラしているときや、人間関係に疲れているときに、「なぜこの人との距離感にこんなにモヤモヤするんだろう」と考えるきっかけをくれるからです。お気に入りの飲み物を用意して、少しゆっくり呼吸をしながら、章ごとに区切って読むと、自分の中の“触れ方のクセ”が、少しずつ見えてくるように感じました。
『手の倫理』(伊藤亜紗・著)レビューまとめ
『手の倫理』は、「手でふれる」という、とても当たり前で身近な行為を通して、道徳と倫理、安心と信頼、ケアと暴力のあいだを丁寧に見つめ直す本でした。触れることの心地よさと危うさ、そのどちらも直視しながら、「それでも他者とどう関わっていくのか」を読者にそっと問いかけてきます。
読後には、誰かの肩に手を置くとき、子どもの手を握るとき、自分の体をさするときでさえ、その瞬間が少しだけ特別なものに変わるように感じました。倫理の本、と構える必要はありません。むしろ、自分の生活の中で「手」をたくさん使っている人ほど、そっと開いてみてほしい一冊です。
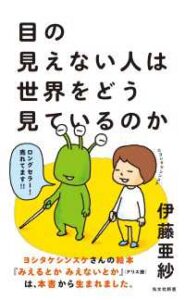
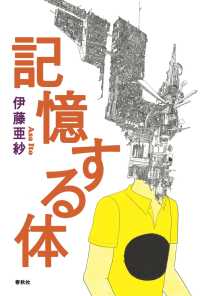

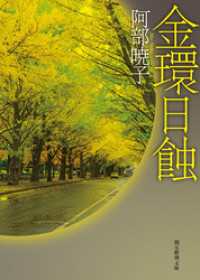


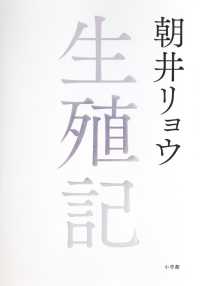
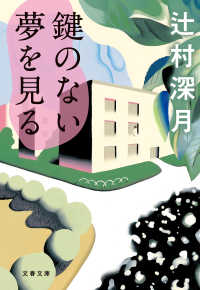
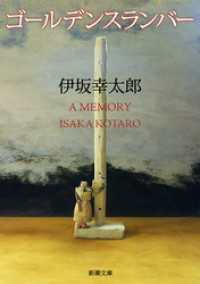



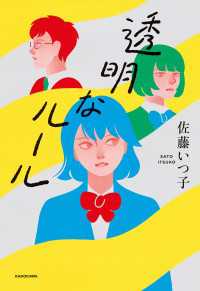
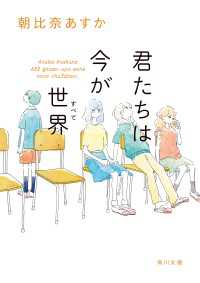
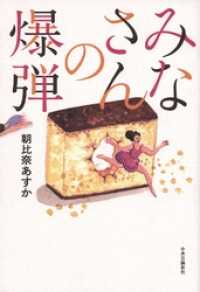
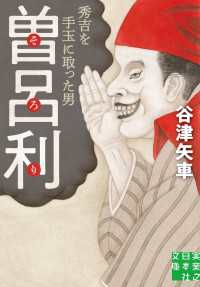
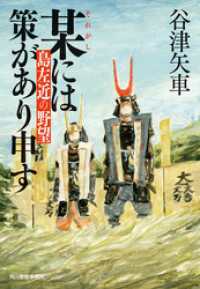


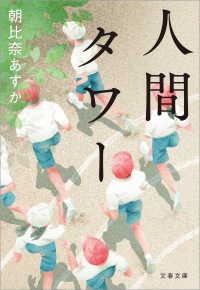
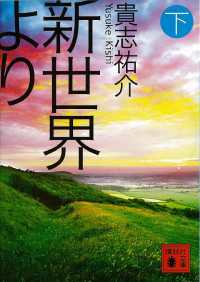
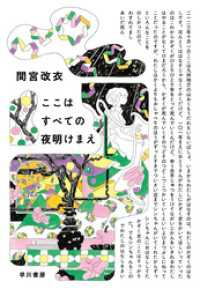
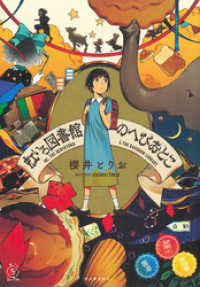




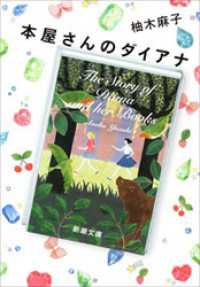
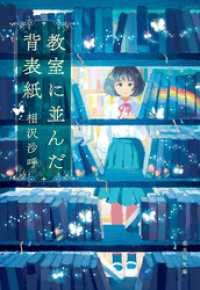
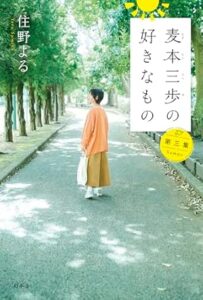
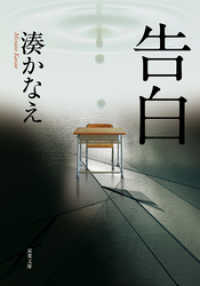
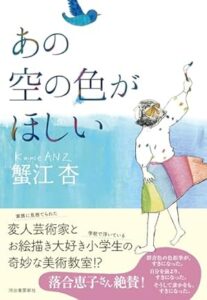
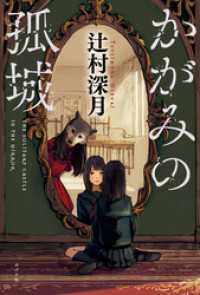

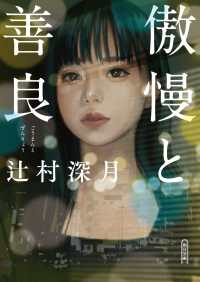
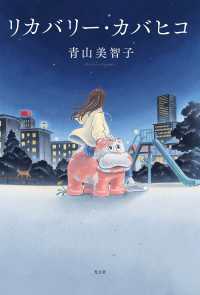
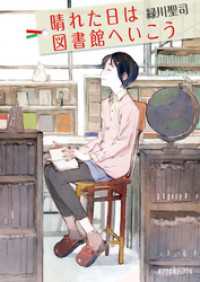

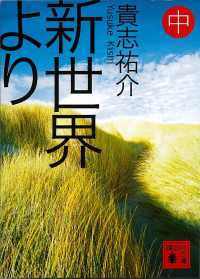

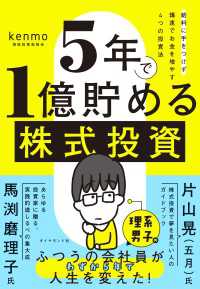
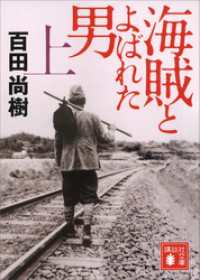
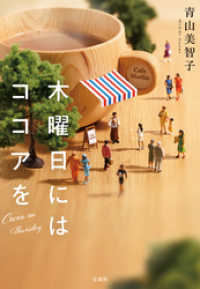
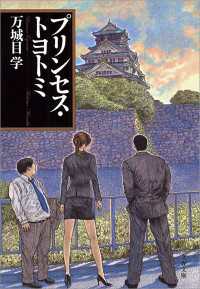
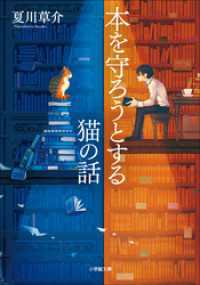
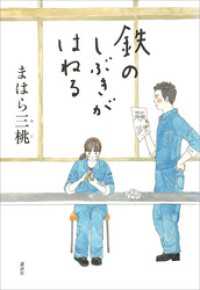

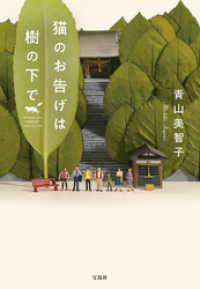
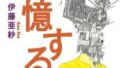

コメント