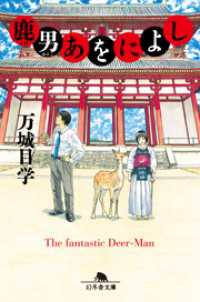
ページをめくるのがこんなに楽しい本、久しぶりだと感じました。読み始めてすぐ、「あ、これは万城目ワールドの中でもかなり好きなタイプかもしれない」と思い、そのまま一気に最後まで連れて行かれました。奈良を舞台に、鹿がしゃべり、卑弥呼の謎が絡み、女子高での青春が描かれる。文字にするとかなり突飛なのに、読んでいるあいだは不思議な説得力があって、世界観にすっかり浸ってしまいました。 主人公は、大学の研究室で「神経衰弱」とあだ名され、居場所をなくしてしまった青年です。教授の勧めで、二学期だけ奈良の女子高へ臨時教師として赴任することになります。この時点では、どこか夏目漱石の『坊っちゃん』のような教師成長ものの匂いがして、苦笑しつつも親しみを覚えました。ところが奈良に着いてほどなく、彼の前に現れるのは、ポッキーが大好きで渋い声で話しかけてくる一頭の鹿。「神無月だよ、先生。出番だよ」という一言で、世界が一気にファンタジー側へとスライドしていきます。 現実ではまずあり得ない展開の連続なのに、読み進めるほど「鹿がしゃべったって、別にいいじゃない」と思えてくるから不思議です。邪馬台国や三角縁神獣鏡のロマンと、女子高の教室や剣道場の空気が混ざり合い、奈良という土地の空と風がとても魅力的に立ち上がっていました。読み終えたあと、本気で「奈良に行きたい」と思ったのは私だけではないはずです。
【書誌情報】
| タイトル | 幻冬舎文庫 鹿男あをによし |
|---|---|
| 著者 | 万城目学【著】 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
| 発売日 | 2012/10 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784344414662 |
| 価格 | ¥877 |
テレビドラマ化もされた大ベストセラー、ついに電子化。 大学の研究室を追われた二十八歳の「おれ」。失意の彼は教授の勧めに従って奈良の女子高に赴任する。ほんの気休めのはずだった。英気を養って研究室に戻るはずだった。渋みをきかせた中年男の声が鹿が話しかけてくるまでは。「さあ、神無月だ――出番だよ、先生」。彼に下された謎の指令とは?古都を舞台に展開する前代未聞の救国ストーリー!
本の概要(事実の説明)
物語のジャンルとしては、現代日本を舞台にしたファンタジー青春小説だと感じました。主人公の「おれ」こと八木は、大学の研究室での失敗や居心地の悪さから逃げるように、奈良の女子高で二学期限定の教師生活を送ることになります。そこで待っていたのは、手強い女子高生たち、クセのある同僚教師たち、そして何より「人語を解する鹿」でした。 鹿は八木に、日本を救うための重大な使命を告げます。それは、鹿・狐・鼠という三つの「使い」が代々守ってきた約束と、邪馬台国の女王・卑弥呼、三角縁神獣鏡にまつわる大きな秘密に関わるものです。奈良・京都・大阪それぞれに拠点を持つ「使い」たちのあいだで、一定期間ごとに「目」を巡る攻防が繰り返されてきた、という設定が語られたとき、現実と空想の境目が良い意味で曖昧になっていく感覚がありました。 一方で、女子高の教室では、なかなか心を開いてくれない生徒たちとの距離感に悩み、剣道部では指導者としての成長が問われます。鹿や狐、鼠といった神獣たちの存在に振り回されながらも、八木は「教師」として、生徒たちと向き合うことを避けられなくなっていきます。ミステリ要素、スポーツ(剣道)、歴史ロマン、青春ドラマと、たくさんのジャンルがひとつの物語の中に詰め込まれていますが、最終的には「一人の冴えない青年の成長譚」としてすとんと腑に落ちる構成でした。 歴史や奈良の土地に興味がある人はもちろん、少し疲れた日常から抜け出して、ユニークな世界に浸りたい人にも向いている一冊だと感じました。ファンタジーが苦手でも、登場人物たちの人間味のおかげで自然と最後まで付き合える物語だと思います。
印象に残った部分・面白かった点
いちばんのハイライトはやはり、「鹿が普通に喋る世界を当然のように受け入れてしまう自分」に気づいた瞬間でした。最初に鹿が渋いおじさんのような声で話しかけてくる場面は、どう考えても突拍子もないはずなのに、万城目作品らしい軽妙な語り口と奈良という舞台の空気感のおかげで、「まあ、この世界ならあり得るか」と思わせてくれます。気づけば、鹿がポッキーを食べる描写すら微笑ましく感じていました。 物語の中盤から後半にかけて、邪馬台国や三角縁神獣鏡の謎が本格的に絡み始めます。教科書で名前を見たことがあるだけの三角縁神獣鏡が、ここでは重要な「鍵」として扱われ、その由来や意味を巡る推理ゲームのような展開になります。歴史ミステリとまではいかないものの、「もし本当にこんな裏話があったら」と妄想したくなるような設定で、歴史好きでなくてもワクワクしました。 そして、もうひとつ心に残ったのは、剣道部の場面です。怖がる部員たちに対して、八木が「別に怖くなってもいいんだ。ただ、やる前からあきらめるな。それは相手に負けたんじゃない。自分に負けただけだ」と語る場面に、ぐっときました。最初は「神経衰弱」呼ばわりされ、自信なさげだった彼が、いつの間にか生徒にこんな言葉をかけられるようになっている。その変化を自然に感じさせてくれる積み重ねも、この作品の魅力だと思います。 ラストに向かっての伏線回収も見事でした。誰が狐の使いで、誰が鼠の使いなのか、私は最後まで確信が持てず、答えを知ったときには「そう来たか」とニヤリとしてしまいました。イトちゃんの大胆な行動や、鹿との別れ、新幹線のシーンなど、読後の余韻を残してくれる場面も多く、最後のページを閉じるのが少し寂しく感じられました。
本をどう解釈したか
私はこの作品を、「世界の見え方が変わるまでの物語」として受け取りました。大学では「神経衰弱」と陰口を叩かれ、自分でも自分をうまく評価できない主人公が、奈良という土地で鹿や生徒たちと出会うことで、自分の役割や居場所を少しずつ掴んでいく。その過程を、邪馬台国の謎や神獣たちとの使命という大きな物語が増幅しているように感じました。 鹿や狐、鼠が守ってきた約束は、歴史の大きな流れに対して人間が抱いてきた「責任」の象徴のようにも思えました。卑弥呼や三角縁神獣鏡というモチーフを使いながら、「今ここにいる自分が何を受け取り、何を次の世代に手渡していくのか」という問いを、軽やかな筆致の裏側で投げかけているように感じます。奈良の街に当たり前に存在する鹿が、古代から続く物語の一部だったとしたら……と想像するだけで、現実の奈良の風景が少し違って見えてくるのも面白いところです。 また、生徒たちとの関係も印象的でした。最初は彼をからかったり無視したりする女子高生たちが、物語が進むにつれて、意外な一面や繊細さを見せてくれます。マドンナ的存在の生徒とのピクニックの場面や、剣道部員たちとのやりとりを通して、「教師」と「生徒」という枠を超えた、ささやかな信頼関係が築かれていく様子に、青春ものとしての味わいも感じました。 タイトルの「鹿男あをによし」は、奈良の枕詞「あをによし」と組み合わさっていて、古代と現代、現実とファンタジーをつなぐ言葉のように思えます。ファンタジーでありながら、妙な説得力と落ち着きがあるのは、この言葉遊びのセンスや、日本語と土地の記憶を大切にした描き方のおかげだと感じました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えたとき、まず思ったのは「日常の風景も、見方ひとつでこんなに物語になるんだな」ということでした。奈良の鹿や遺跡は、日本人にとってはどこか「当たり前」の観光地的イメージがありますが、この作品を通して見ると、そこに古代から続く時間の厚みや、人間と神話の境界が滲むような感覚が重なってきます。次に奈良に行く機会があったら、きっと鹿を前にして「この子も実は何か重大な使命を背負っているのかもしれない」と、少し真面目に想像してしまいそうです。 もうひとつの気づきは、「自分の弱さや不器用さから、物語は始まってもいいのだ」ということでした。八木は最初から頼れる先生ではありません。むしろ、神経質で自信がなく、周りからもあまり評価されていない人物として描かれます。それでも、奈良での出来事を通して、完全に別人になるわけではなく、少しずつ、自分なりの勇気を出せるようになっていきます。その変化が、とても現実的で、だからこそ励まされました。 「怖くなってもいい。ただ、やる前からあきらめるな」という言葉は、日常のいろいろな場面で思い出せるフレーズだと感じました。仕事でのプレッシャーや、新しい挑戦の前で足がすくみそうなとき、「自分に負ける前に、とりあえずやってみよう」と背中を押してくれる、さりげない応援のような一行です。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この本は、時間を気にせず物語の世界に浸りたい休日にぴったりだと感じました。できれば、予定の少ない静かな午後や、ゆっくり起きた休日の午前中など、現実の用事から少し距離を置けるタイミングがおすすめです。奈良の空気感や古代ロマンがじわじわと広がっていくので、途中で頻繁に中断されるより、一気に読んだほうが没入感を味わえます。 また、平日の夜に、疲れた頭をリセットしたいときにも向いていると思いました。重すぎるリアルな社会派小説だとしんどいけれど、ただ軽いだけの物語では物足りない、という気分のときにちょうど良いバランスです。鹿が喋るという突飛な設定にクスッとしつつ、最後には不思議と胸が温かくなる。そんな読書時間を過ごしたい夜に、そっと手に取ってほしい一冊です。
『鹿男あをによし』(万城目学・著)レビューまとめ
『鹿男あをによし』は、奈良という土地の魅力と、邪馬台国の謎、しゃべる鹿という突飛なアイデアが見事に融合した、万城目学らしさ全開のファンタジー青春小説でした。冴えない青年教師が、鹿や生徒たち、古代から続く物語に巻き込まれながら少しずつ自分を見つけていく姿に、何度も笑わされ、最後はじんわりと胸が熱くなりました。読み終えたときには、きっとあなたも「奈良に行きたい」と思っているはずです。
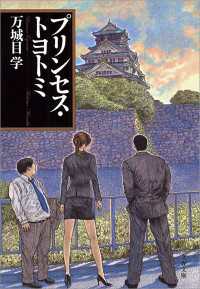
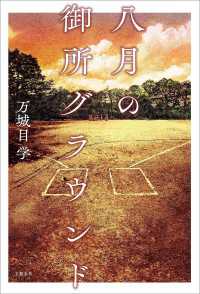


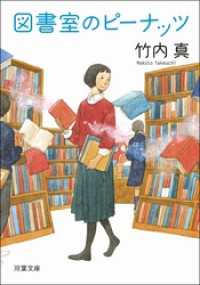

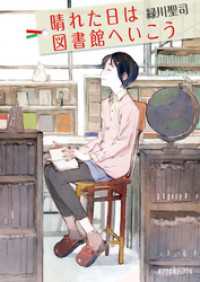
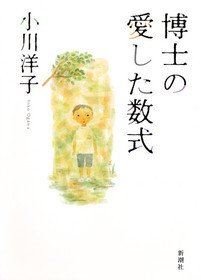

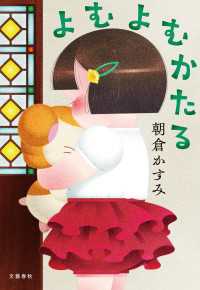
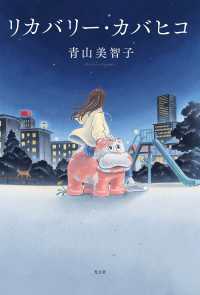
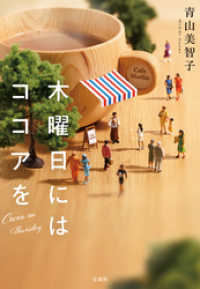
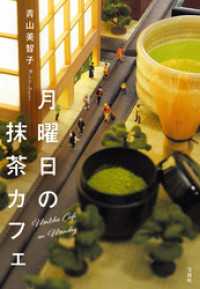
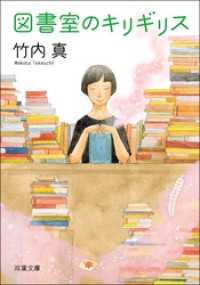
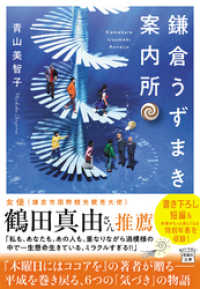
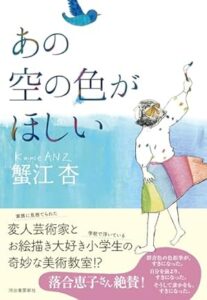

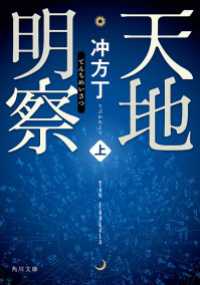
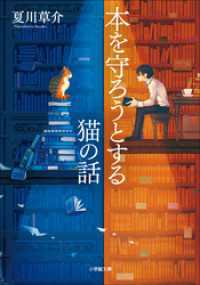

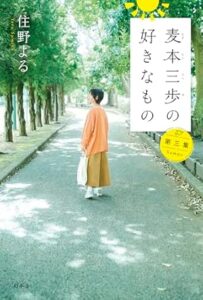
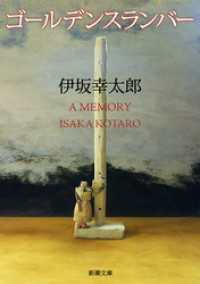
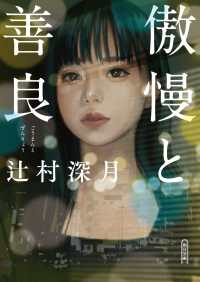


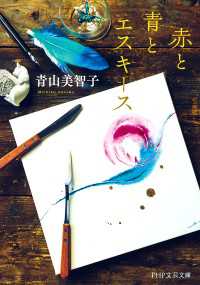
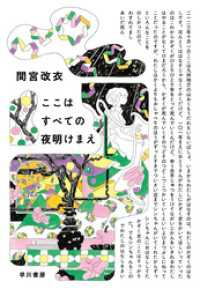


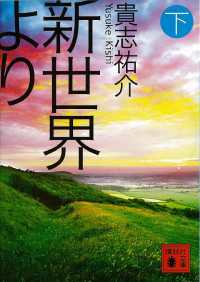
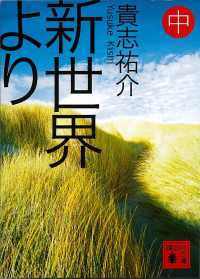
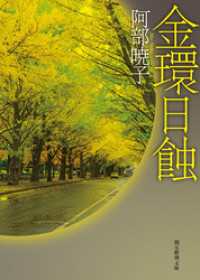

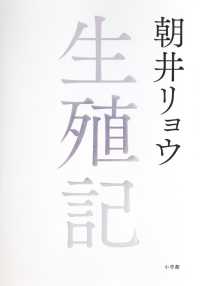
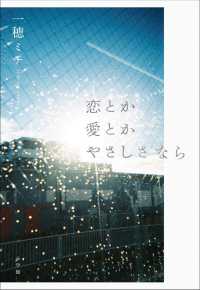
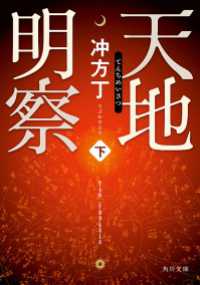
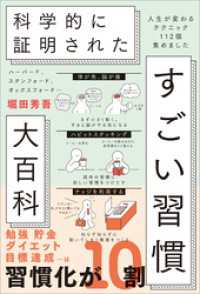

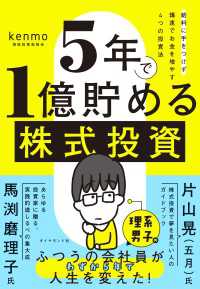

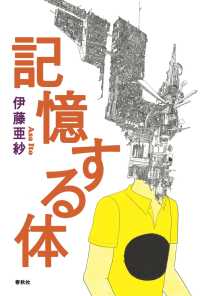
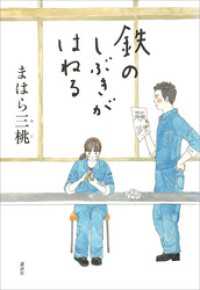


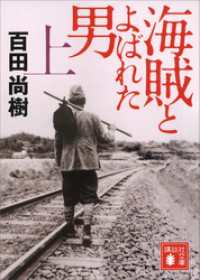
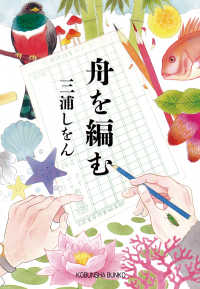


コメント