
『人魚が逃げた』を読み始めてまず驚いたのは、「銀座の歩行者天国」と「人魚姫」という、一見ミスマッチな組み合わせでした。ところがページをめくるほどに、この組み合わせがじわじわと馴染んでいき、読み終わる頃には「銀座って、こういう不思議な物語が似合う街かもしれない」と感じている自分がいました。 ある3月の週末、SNSでトレンド入りした「人魚が逃げた」という謎のフレーズ。銀座をさまよい歩く「王子」と名乗る青年が、「僕の人魚が、いなくなってしまって……逃げたんだ。この場所に」とつぶやく。その一言をきっかけに、銀座を訪れていた5人の男女の人生が、すこしずつ動き出していきます。 読んでいるあいだ、現実の街の風景に、うっすらと童話の影が重なっていく感覚がありました。誰もが何かを抱えて歩いているけれど、ふとしたきっかけで「物語」が入り込む。その入り口としての銀座、そして王子の存在が、とても巧く機能していると感じました。
【書誌情報】
| タイトル | 人魚が逃げた |
|---|---|
| 著者 | 青山美智子 |
| 出版社 | PHP研究所 |
| 発売日 | 2024/11 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784569857947 |
| 価格 | ¥1,500 |
本屋大賞4年連続ノミネート! 今最注目の著者が踏み出す、新たなる一歩とは――。幸福度最高値の傑作小説! 〈STORY〉ある3月の週末、SNS上で「人魚が逃げた」という言葉がトレンド入りした。どうやら「王子」と名乗る謎の青年が銀座の街をさまよい歩き、「僕の人魚が、いなくなってしまって……逃げたんだ。この場所に」と語っているらしい。彼の不可解な言動に、人々はだんだん興味を持ち始め――。そしてその「人魚騒動」の裏では、5人の男女が「人生の節目」を迎えていた。12歳年上の女性と交際中の元タレントの会社員、娘と買い物中の主婦、絵の蒐集にのめり込みすぎるあまり妻に離婚されたコレクター、文学賞の選考結果を待つ作家、高級クラブでママとして働くホステス。銀座を訪れた5人を待ち受ける意外な運命とは。そして「王子」は人魚と再会できるのか。そもそも人魚はいるのか、いないのか……。
本の概要(事実の説明)
本書は、アンデルセン童話「人魚姫」をモチーフにした連作短編集です。 物語はすべて、歩行者天国となった銀座の街を舞台に進んでいきます。 登場するのは、 • 12歳年上の恋人と付き合う元タレントの会社員 • 娘と銀座で買い物中の主婦 • 絵画の収集にのめり込み、妻に離婚されたコレクター • 文学賞の選考結果を待ち続ける作家 • 高級クラブでママとして働くホステス それぞれの短編は独立して読めるのに、王子や小物、童話のモチーフがさりげなくリンクしていて、「あ、さっきのあの人だ」「この場面はあのエピソードとつながっているのか」と気づく楽しさがあります。最後まで読むと、5つの物語が円を描くようにつながり、タイトルの意味もじわっと立ち上がってきました。 印象としては、「現実小説」と「メルヘン」のちょうど中間くらいの読み心地です。銀座の現実感がちゃんとあるのに、時計塔の上空あたりにだけ、少しだけ別の世界への隙間が開いているような、不思議な手ざわりの作品だと感じました。
印象に残った部分・面白かった点
いちばん印象に残ったのは、「人魚とは誰なのか?」という問いが、各エピソードを通して何度も形を変えて現れるところでした。年上の恋人かもしれないし、母かもしれないし、かつての妻かもしれない。あるいは、ずっと叶えられないままでいる作家の「物語」そのものが、人魚なのかもしれません。 作中では、人魚姫の原作に対する解釈も丁寧に語られます。恋が成就しない悲恋としてだけでなく、「泡になったあと、風の精として人の幸せに関わっていく」という視点が提示され、私はそこにハッとさせられました。失われた恋や終わった関係は、ただの「失敗」ではなく、その後の誰かの日常を支えているかもしれない――そんな優しい読み替えに、胸がじんとしました。 また、各話の会話やモチーフが絶妙です。 • 歌舞伎の幕間に重箱を膝に乗せて楽しむ男性が、実は「浦島太郎」的な存在だったり • ラプンツェルや赤ずきん、ヘンゼルとグレーテル、ジョバンニなど、さまざまな物語の登場人物を思わせる人たちが銀座を歩いていたり こうした仕掛けが、読み手の童心をくすぐります。現実の銀座にいるような人々なのに、どこかおとぎ話の登場人物にも見えてくる。その二重写しの感じが、とても楽しかったです。
本をどう解釈したか
この本を通して、一番強く感じたテーマは「誤解」と「すれ違い」でした。 登場人物たちは、みんな勝手に相手の気持ちを想像して、勝手に傷ついたり距離を置いたりしています。 たとえば、長年連れ添った相手に対して、 「もう、つらいことも嬉しいことも、あなたに話したいと思えない」 と感じてしまう場面。 これはとても苦しい言葉ですが、その裏側には「本当は一番最初にあなたに話したかった」という思いがあるように思えました。 本書の登場人物たちは、決して「悪い人」ではありません。むしろ、お互いを思いやろうとして空回りした結果、関係がこじれてしまった印象があります。だからこそ、王子という少し非現実的な存在や、童話のモチーフが入り込むことで、彼らの視点がほんの少しだけズレる。そのズレが、「相手のことを直接聞いてみよう」「自分の本音をちゃんと伝えてみよう」という一歩につながっていくのだと感じました。 「人は同じものを見ても、経験や思いから全く違う考えを持つ」という感想がありましたが、まさにその通りで、各章は「人は皆、自分の物語のフィルターを通して世界を見ている」ということを教えてくれます。そして、そのフィルターを少しだけ外してみる勇気を、物語がそっと後押ししてくれるように思えました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えて、いちばん強く心に残ったのは、「自分の中だけで完結させないで、ちゃんと相手に言葉を届けたい」という気持ちでした。 作中には、こんなニュアンスのメッセージがいくつも出てきます。 • 思い込みや些細な一言が、関係をこじらせてしまうことがある • でも同じくらい、小さな出来事や言葉が、人を前向きに変えることもある 私自身、相手の反応を怖がって本音を飲み込んでしまうことがよくあります。そのたびに「言わなければよかった後悔」と「言わなかった後悔」を天秤にかけてしまうのですが、この本を読んで、「少なくとも、伝えようとした後悔のほうが、未来につながるかもしれない」と感じました。 また、「普段のささやかな日々を、どう味わっていくか」という視点にも惹かれました。何か劇的な出来事が起きなくても、人は日々の中で少しずつ変わっていきます。銀座の一日を切り取っただけのように見える物語なのに、その後の人生が静かに変化していくだろう気配が、ページの端々に漂っているように感じました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この本は、がっつり物語の世界に浸りたいときよりも、「現実と物語のあいだを行き来したい気分」のときにぴったりだと感じました。 おすすめは、静かな休日の午後。 コーヒーや紅茶を用意して、できればスマホを少し離れたところに置いて、1編ずつゆっくり読むのが合っていると思います。1話ごとにきちんと区切りがあるので、「今日はここまで」と余韻を味わいながら本を閉じることもできますし、夢中になって一気読みすることもできます。 もうひとつのおすすめシーンは、「自分の人間関係にモヤモヤしているとき」です。恋人でも家族でも友人でも、「あの人は本当はどう思っているんだろう」と考えすぎてしまうときに読むと、登場人物たちの不器用さに共感しつつ、「じゃあ自分はどうしたいのか」と少しだけ冷静に考えられるようになる気がしました。
『人魚が逃げた』(青山美智子・著)レビューまとめ
『人魚が逃げた』は、銀座という現実の街に、アンデルセン「人魚姫」の物語をふわりと重ね合わせた、大人のための連作短編集だと感じました。王子の「人魚が逃げた」という一言をきっかけに、それぞれの人生が少しだけ軌道修正されていく様子は、派手さはないのに、じんわりと心に残ります。
人間関係に疲れたときや、自分のこれからの生き方に迷ったときに、「物語の力」をそっと借りたくなったら。銀座の歩行者天国に現れる王子と5人の登場人物たちに、もう一度会いに行きたくなる一冊でした。

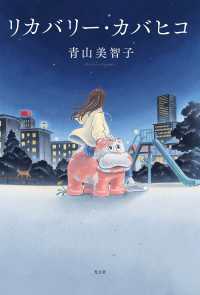
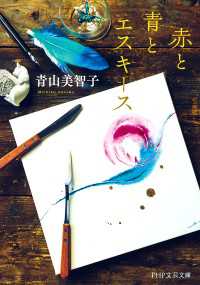
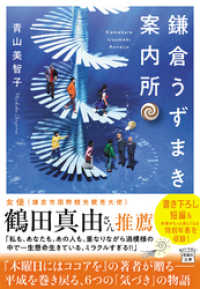

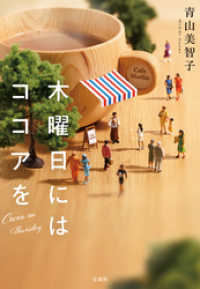

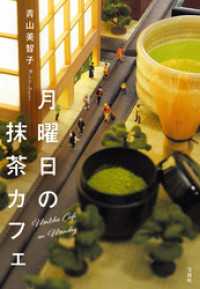
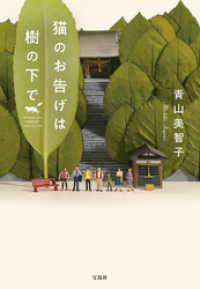
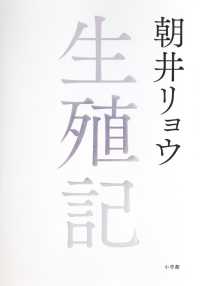
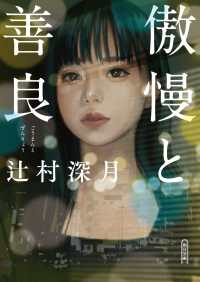
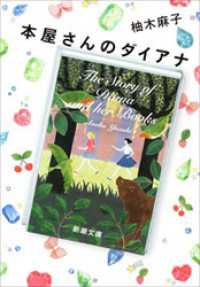
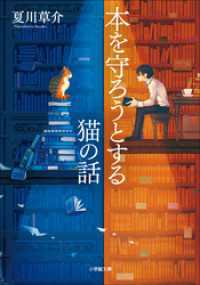
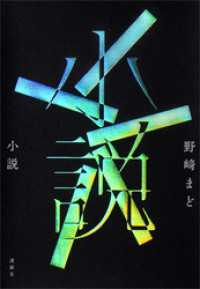

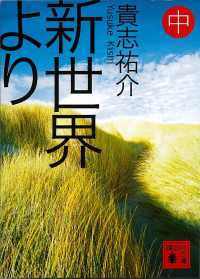
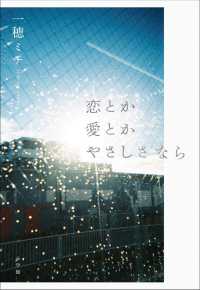


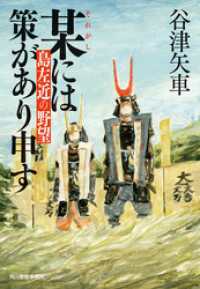
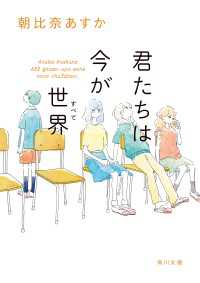
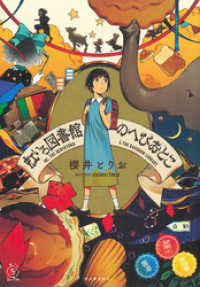
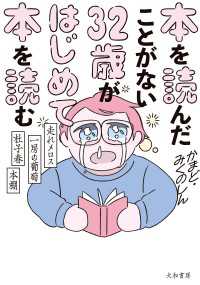
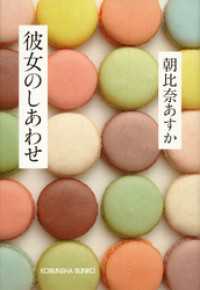

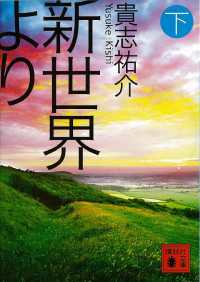



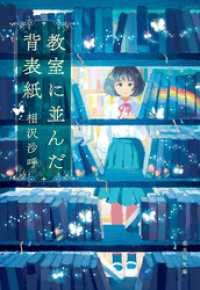

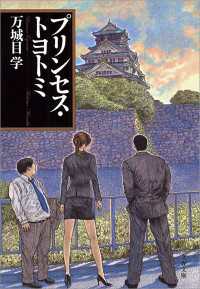
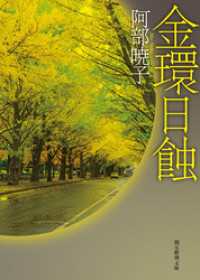
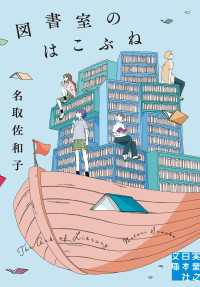
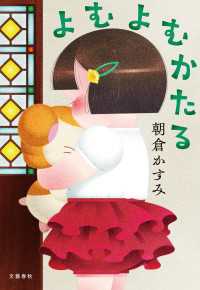

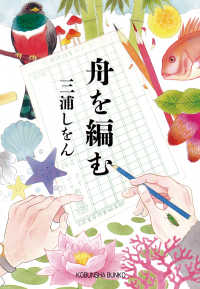
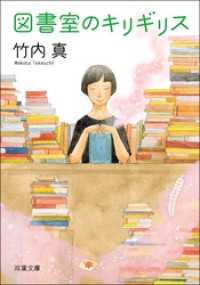
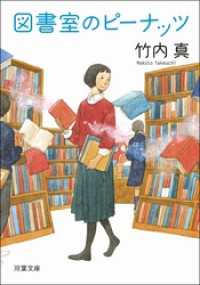
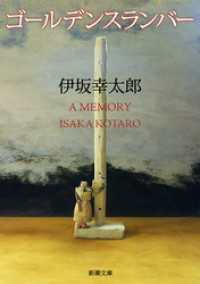


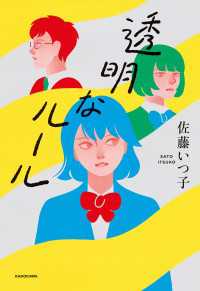
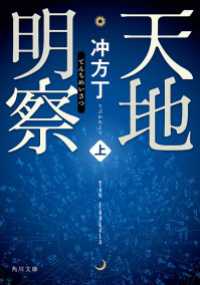
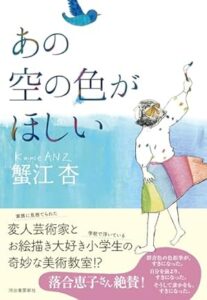



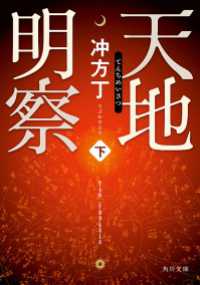



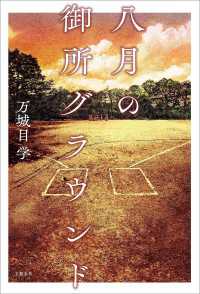
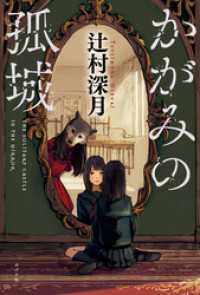


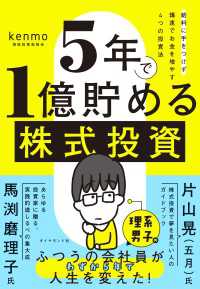



コメント