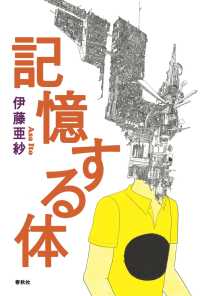
『記憶する体』を読み始めてすぐ、「これはただの医学本でも福祉本でもないな」と感じました。視力や聴力、手足の一部を失った人たちへのインタビューを通して、「体が覚えていること」と「意識している自分」が、意外なところでズレ続けていることが、じわじわと浮かび上がってきます。 事故で足を失ったダンサーが、やがて「失ったはずの足」のほうを利き足のように感じるようになる話。全盲なのに、ものすごい速度でメモを取りながら会話する女性。痛くないのに痛い「幻肢」の感覚。どのエピソードも、人間の体の不思議さとしぶとさを突きつけてきて、読みながら何度も「え…そんなことが起こるの?」と目を見張りました。 同時に、この本は「障害者は大変だね」「かわいそうだね」という同情を誘うための本ではまったくありません。むしろ、当事者たちの徹底した“自己研究”に付き合わされることで、「自分の体だって、結構わかっていないことだらけかもしれない」と、自分自身の生活や体の使い方を振り返らされる一冊だと感じました。
【書誌情報】
| タイトル | 記憶する体 |
|---|---|
| 著者 | 伊藤亜紗 |
| 出版社 | 春秋社 |
| 発売日 | 2020/04 |
| ジャンル | 人文 |
| ISBN | 9784393333730 |
| 価格 | ¥1,760 |
ふだんは意識しないけれど、誰もが自分だけの体のルールをもっている。階段の下り方、痛みとのつきあい方…。「その人らしさ」は、どのようにして生まれるのか。経験と記憶は私たちをどう変えていくのだろう。視覚障害、吃音、麻痺や幻肢痛、認知症などをもつ11人のエピソードを手がかりに、体にやどる重層的な時間と豊かな可能性について考察する、ユニークな身体論。
本の概要(事実の説明)
『記憶する体』は、身体障害や若年性認知症など、さまざまな「体の変化」を経験した11人へのインタビューをもとに構成されたノンフィクションです。著者の伊藤亜紗さんは、美学や現代アートを背景に「障害」を研究してきた研究者。だからこそ、医療やリハビリの枠を超えて、「その人の体の歴史」そのものを丁寧に描き出していきます。 本書で扱われるのは、視覚・聴覚の障害、手足の切断や麻痺、幻肢と幻肢痛、吃音、若年性アルツハイマーなど。一見まったく違うテーマに見えますが、どのエピソードにも共通するのは「体には、その人だけのローカルルールが刻まれている」という視点です。 たとえば、全盲の人が「介助者の言葉」に頼りすぎることで、世界へのアクセスが“言葉経由”になってしまい、自分の感覚との距離が開いてしまう話。逆に、介助から距離をとることで、自分の体と世界を直接つなぎ直していく過程。どれも専門用語に頼りすぎず、エピソードを中心に語られているので、専門知識がなくても読みやすいと感じました。 この本は、医療や福祉に関わる人はもちろんですが、「歳を重ねて体が変わっていくのが少し不安」「最近、前のように動けないな」と感じ始めている人にもおすすめです。自分の体と折り合いをつけていくヒントが、さりげなくあちこちに潜んでいるように思いました。
印象に残った部分・面白かった点
一番刺さったのは、「オートマからマニュアルへ」という比喩です。私たちはふだん、歩いたり、書いたり、話したり…ほとんどの動作を「意識しないオートマ運転」でこなしています。でも、事故や病気で体が変わると、そのオートマが一度壊れてしまう。そこで当事者は、呼吸や筋肉の動きを一つずつ確認しながら、新しい「マニュアル運転」を組み立て直していきます。 バイク事故で手足を失い、常に幻肢痛に悩まされている男性のエピソードは、読んでいて正直怖さすら感じました。脳は「そこにあるはずの手足」を今も当然のように想定しているのに、現実にはもうない。そのズレが「痛み」として出てきてしまうという説明に、体と脳の関係の複雑さを思い知らされます。 一方で、左足を失ったダンサーが、「失った足」の記憶を活かしつつ、義足や体全体を使って新しいダンスを創り上げていく過程には、希望のようなものも感じました。失ったものをなかったことにするのではなく、「かつてそこにあった体」と「今ここにある体」の両方を抱えながら、新しい身体性を作っていく姿は、とてもまっすぐでかっこよく見えました。 読み進めるうちに、「障害」という言葉のイメージが少しずつほどけていきます。かわいそうな人というラベルでもなく、“乗り越えるべき試練”というきれいごとでもない。ただ、自分の体のローカルルールと地道につきあい続けている、一人ひとりの時間が積み重なっているだけなのだと感じさせられました。
本をどう解釈したか
この本を読みながら、私は「体って、実はかなり“勝手”な存在なんだな」と感じました。意識では「もう足はない」と理解していても、脳はなかなか納得せず、幻肢痛を送り続けてくる。逆に、何度も同じ動作を続けるうちに、「考えなくてもできる」オートマ状態ができあがってしまう。その両方が、人間の体の正直な姿なのだと思います。 著者が強調する「体のアイデンティティは、その体とともに過ごした時間に宿る」という考え方にも、とても納得しました。障害の有無や診断名だけでは、その人の体は語りきれません。同じ義足、同じ聴覚障害、同じ認知症というラベルがついていても、その人の経験と記憶の積み重ねによって、体の感覚も、世界との距離の取り方もまるで違う。 また、「障害は個人の中だけにあるのではなく、社会との関係の中で立ち上がる」という視点も印象的でした。義手が「自分には必要ないけれど、周囲の人が安心するからつけている」という話は、見た目や“ふつうらしさ”が、どれだけ人と社会の関係性に影響しているかを物語っています。 この本は、障害を特別視して「そっと遠ざける」のではなく、「それも身体の一つのあり方だ」としてフラットに眺める視点を提案しているように思えました。そして、そのまなざしは、結局は自分自身の体にも向けられていく。完璧ではない体、思い通りに動かないところを抱えながら、どうやって付き合っていくか。その問いは、誰にとっても無関係ではないと感じました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えてからしばらく、ふとした動作のたびに「今これ、オートマでやっているな」と意識するようになりました。階段を降りるとき、キーボードを打つとき、料理中に包丁を握るとき…どれも、意識して手順を追っているわけではないのに、体は迷いなく動いてくれます。それ自体が、これまでの生活で少しずつ積み重ねられた「体の記憶」なのだと思うと、なんだかありがたくさえ感じました。 同時に、「もしどこかをケガしたり、病気になったりしたら」と想像したとき、怖さとともに、少しだけ別の感情も芽生えました。オートマが壊れてしまったら、そのときはマニュアルで組み立て直すしかない。そこで終わりではなく、そこから新しい体のローカルルールが始まるかもしれない。そう考えると、変化する自分の体に対する恐怖が、ほんの少しだけ和らいだように思います。 また、「障害のある人を助けなきゃ」と善意のスイッチが入りそうになる自分の癖にも気づかされました。本書に出てくる人たちは、守られるだけの存在ではなく、自分の体と社会との関係を工夫し、新しいルールを提案してくれる存在でもあります。そこに気づけたことで、「かわいそうだから手を貸す」という発想から、「どう関わればお互いに楽でいられるかな?」と少し視点を変えられた気がします。 結局のところ、この本が教えてくれたのは、「体との付き合い方は、誰もが一生かけて続けるテーマなのだ」ということでした。若さや健康を前提にした“標準仕様の体”ではなく、今ここにある自分の体のローカルルールを、もう少し大事に観察していきたいと感じました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
『記憶する体』は、物語に没入する小説とは少し違って、じっくり味わいながら読みたいタイプの一冊だと感じました。個人的には、静かな休日の午前中に、温かい飲み物を片手に読み進めるのがいちばんしっくりきました。章ごとに登場人物もテーマも変わるので、一区切りごとに本を閉じて、自分の体験にひきよせて考える時間を挟むと、読みごたえが増すと思います。 また、カフェなど少しざわつきのある場所で読むのもおすすめです。行き交う人たちをなんとなく眺めながら、「あの人にも、あの人なりの体のローカルルールがあるんだろうな」と想像してみると、本の内容がぐっと自分の現実に近づいてくる感覚がありました。短時間で一気読みするよりも、通勤やすきま時間に少しずつ読み進めて、その都度「今の自分の体の調子」を意識してみると、新しい発見がありそうです。
『記憶する体』(伊藤亜紗・著)レビューまとめ
『記憶する体』は、障害をテーマにしながらも、「かわいそう」「がんばっていてえらい」といった一方向の感想では終わらせてくれない本でした。それぞれの人が、自分の体のローカルルールを引き受けながら、生きやすさを模索している。その姿は、障害の有無にかかわらず、誰にとっても他人事ではないように感じます。
自分の体が思い通りにならない瞬間にイラッとしてしまうとき。歳を重ねることへの不安がふとよぎるとき。そんなときにこの本を思い出すと、「今の体だからこそ見える世界もあるのかもしれない」と、少し優しい目で自分を見つめ直せる気がしました。
体の不思議さとしぶとさに興味がある方はもちろん、「自分の体とこれからどう付き合っていこうかな」と考え始めている方にも、ゆっくり味わってほしい一冊です。
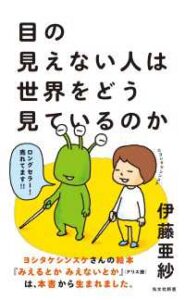


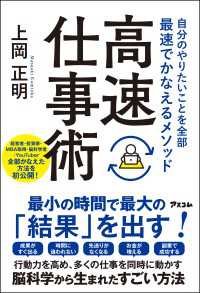
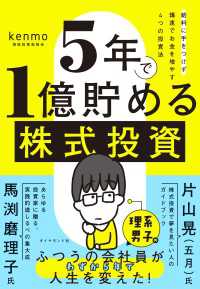

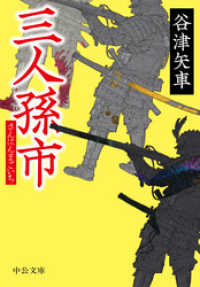
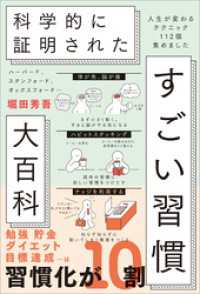



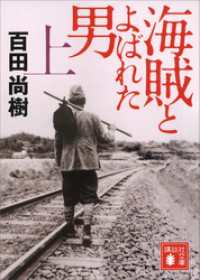
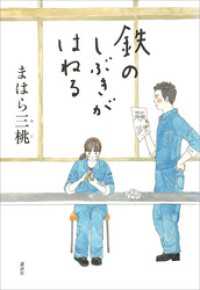
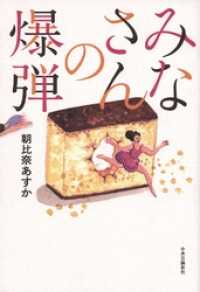
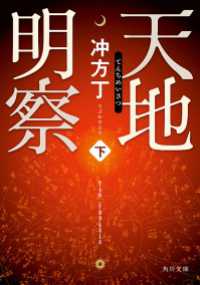

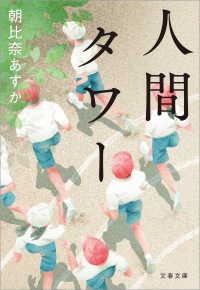
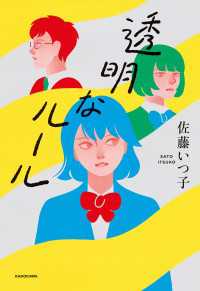
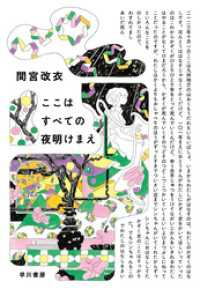

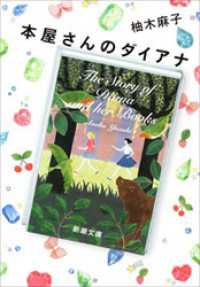
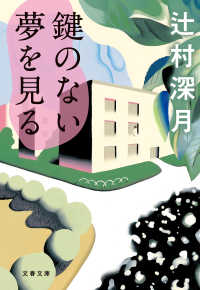

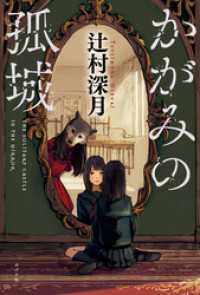
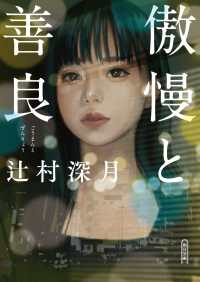

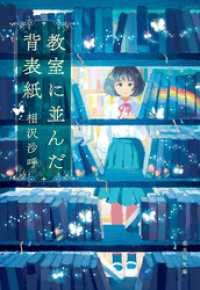
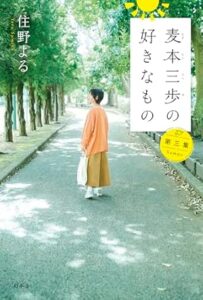
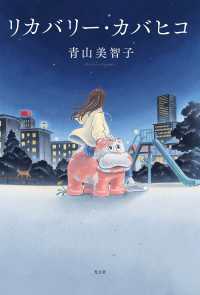

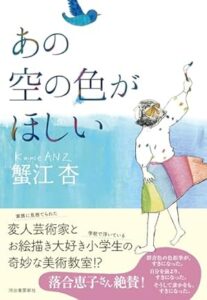
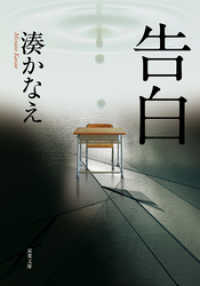
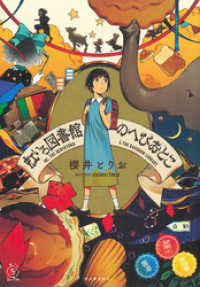
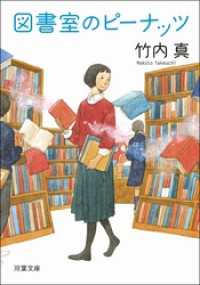

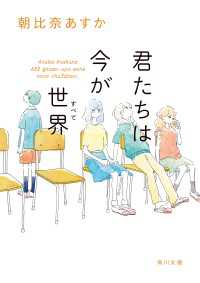
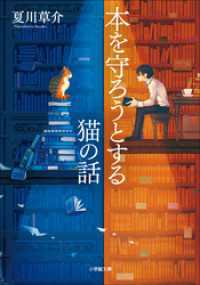
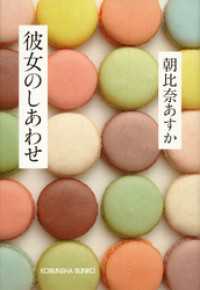


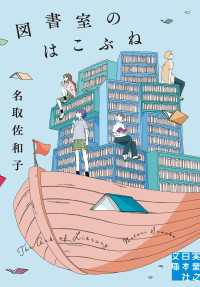
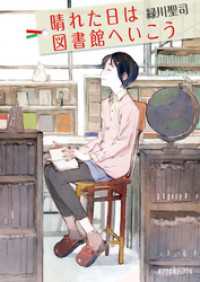


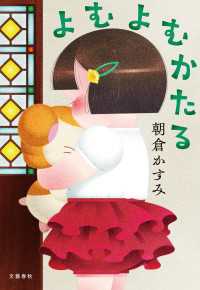
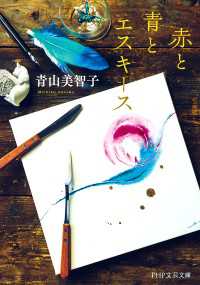
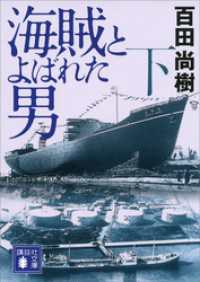


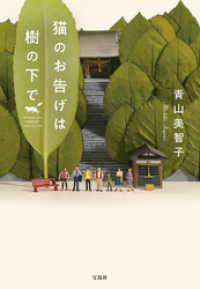

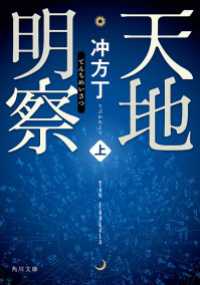



コメント