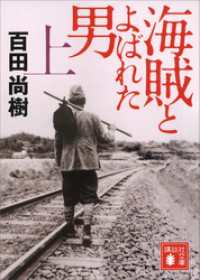
『海賊とよばれた男(上)』は、ただの歴史小説でも経済小説でもありませんでした。ページをめくるごとに熱量が伝わり、国岡鐵造という人物の「まっすぐさ」に胸を突かれる物語だと感じました。敗戦で国が崩れ、未来が見えなくなった時代に、彼がなぜ再び立ち上がれたのか。その背景を知るほどに、私自身も静かに奮い立つような感覚を覚えました。 読み始めた頃は、実在の人物をモデルにした物語であることも知らず、単純に「石油」というテーマにどれほど物語性があるのだろうと疑問に思っていました。しかし、国岡の姿勢や彼を支える仲間の生き方に触れるうち、これは人生の物語であり、挑戦の物語であり、誇りの物語なのだと気づいていきます。 そして、彼の歩みを追っていると、自分自身が何に向き合い、何を大切にしようとしているのかを自然と考えさせられました。上巻を読み終えたときには、気づけば下巻を手に取っていました。
【書誌情報】
| タイトル | 講談社文庫 海賊とよばれた男(上) |
|---|---|
| 著者 | 百田尚樹【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2020/05 |
| ジャンル | 歴史・時代小説 |
| ISBN | 9784062778299 |
| 価格 | ¥880 |
すべてのビジネスマンに捧ぐ。本屋大賞の話題作、早くも文庫化!ページをめくるごとに、溢れる涙。これはただの経済歴史小説ではない。一九四五年八月十五日、敗戦で全てを失った日本で一人の男が立ち上がる。男の名は国岡鐡造。出勤簿もなく、定年もない、異端の石油会社「国岡商店」の店主だ。一代かけて築き上げた会社資産の殆どを失い、借金を負いつつも、店員の一人も馘首せず、再起を図る。石油を武器に世界との新たな戦いが始まる。石油は庶民の暮らしに明かりを灯し、国すらも動かす。「第二の敗戦」を目前に、日本人の強さと誇りを示した男。
本の概要(事実の説明)
本作は、出光興産の創業者・出光佐三をモデルにしたとされる人物「国岡鐵造」の奮闘を描く歴史経済フィクションです。舞台は1945年、日本が荒廃し、すべての価値観が揺らいだ敗戦直後。鐵造が率いる国岡商店は、一代で築き上げた莫大な資産を失い、借金を抱え、社員の生活を守ることすら難しい状況に追い込まれていきます。 しかし國岡鐵造は、店員を誰一人辞めさせることなく、希望すら見えない荒野の中で再起の道を模索します。石油という国家的資源に未来を見出し、世界の強国を相手に渡り合おうとする姿には、読みながら思わず背筋が伸びる瞬間が何度もありました。 物語は、彼の半生を描く第2章「青春」と、敗戦後の再起を描く第1章「朱夏」が交互に配置され、過去と現在の視点が交差する構成です。そこから浮かび上がるのは、一人の男がいかにして“時代を動かす人間”になったのかという成長の軌跡でした。 歴史小説が初めての方でも読みやすく、ビジネスやリーダー論としても多くの示唆があります。
印象に残った部分・面白かった点
最も心を揺さぶられたのは、國岡鐵造の「人」に対する向き合い方でした。出勤簿はない、定年もない、そして誰もクビにしない。それを成立させてしまう鉄造の圧倒的な存在感は、単に奇策ではなく、人を信じぬく覚悟の深さの表れだと感じました。 また、どんな仕事でもやるという精神。ラジオ修理、漁業、農業、タンク底の残油掃除まで従業員とともに汗を流し、国のために燃料を確保しようと奔走する姿は、ただの「経営者」ではありませんでした。彼の行動すべてが、日本を再び立たせるための挑戦に見えたのです。 物語の序盤から心が熱くなるのは、鐵造の周囲に集まる仲間たちもまた魅力に満ちているからです。店主への尊敬と信頼が強い絆となり、彼らが家族のように支え合う場面は自然と胸が熱くなりました。 さらに、零戦の宮部久蔵を思わせる人物の登場には思わず笑みがこぼれました。百田作品を読んできた人には、心躍る小さなサプライズだと思います。
本をどう解釈したか
本作を読みながら、「信念を持つ」とはどういうことかを繰り返し考えさせられました。鐵造は決して全て正しいとは言えない部分もあります。しかし、彼は常に「誰のために働くのか」という問いに真正面から向き合っていたように思います。 戦後の混乱期は、多くの人が自分の生活だけで精一杯だったはずです。そんな中、鐵造は「損得よりも意義」「利益よりも誇り」を選び続けました。その姿勢は、現代の価値観から見ると古めかしく映るかもしれませんが、だからこそ普遍的な力を持っています。 また、彼の生き様からは、国家や社会に対する献身が美談ではなく、個人の信念から積み上げられた現実であることが伝わってきました。 商売を「戦い」ではなく「奉仕」と捉えていた國岡の哲学は、混乱した時代を生き抜くための知恵でもあり、人を動かす言葉の重さにも通じています。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えて最も強く心に残ったのは、「自分は何を信じて働いているのか?」という問いでした。鐵造のように迷いなく生きることは難しいものの、どんなに状況が悪くても自分の信じる価値を手放さない姿勢には強く励まされるものがありました。 また、國岡商店の社員たちの結束を見るうちに、組織は制度よりも“人の在り方”で形づくられるのだと実感しました。鐵造が社員を家族のように扱うからこそ、社員が鐵造のために身体を張れる。そんな関係性は、現代社会ではすっかり薄れてしまったもののように思え、どこか懐かしさすら感じました。 歴史や経済の知識が自然と心に入ってくる構成で、難しいテーマにもかかわらず物語性に引き込まれます。読後には、もっと強く生きたい、もっと誇りを持って仕事をしたいという前向きな気持ちが湧き上がりました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
静かな休日、まだ外が薄暗い早朝に読み進めるのが特に合う作品だと感じました。敗戦の荒野から始まる物語には、余白のある時間がよく似合います。ページをめくるたびに立ち上がる熱意に、静寂がほどよく寄り添ってくれます。 また、夜にじっくり読み込むと、國岡鐵造の言葉や行動の余韻が長く残り、一日の終わりに不思議と勇気をもらえます。仕事でうまくいかなかった日の夜、彼の生き様に触れると「まだ立てる」と背中を押されるようでした。
『海賊とよばれた男(上)』(百田尚樹・著)レビューまとめ
国岡鐵造の生き様は、時代の荒波に抗いながらも信念を貫く人間の強さを鮮烈に浮かび上がらせます。混乱の中でも「誇り」を選び続けた姿勢に触れると、自分の生き方を見つめ直したくなる一冊でした。
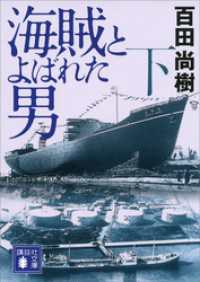
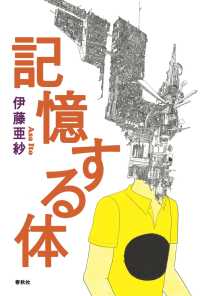
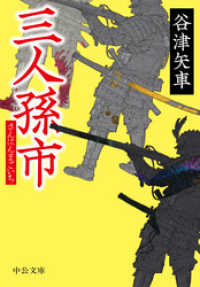


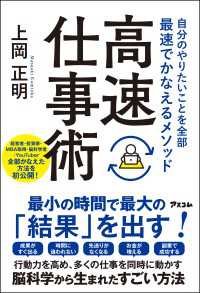



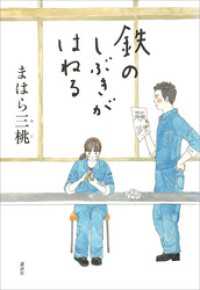
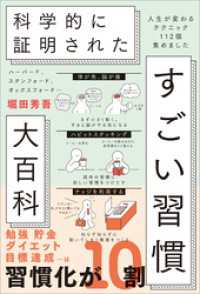
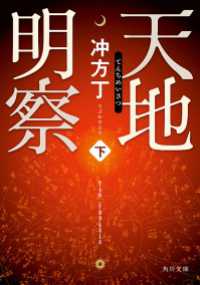
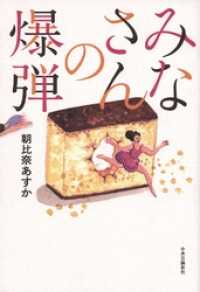
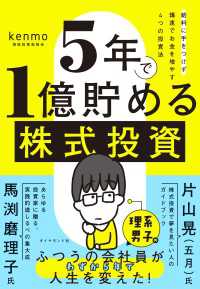
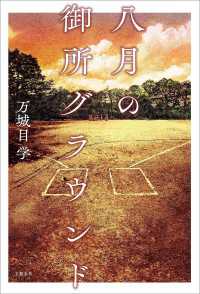
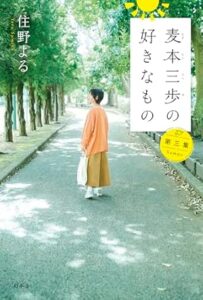
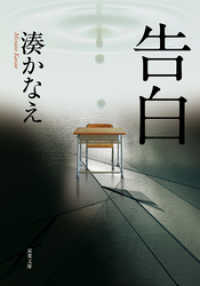
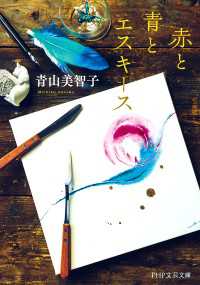
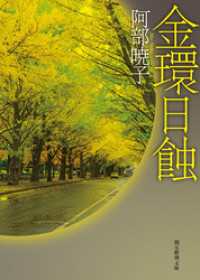
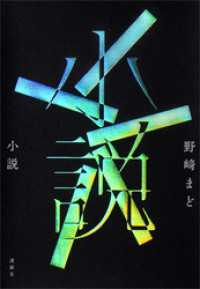


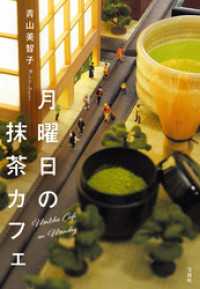
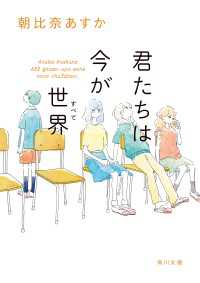

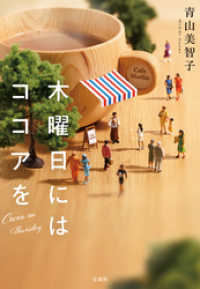

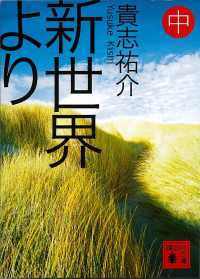

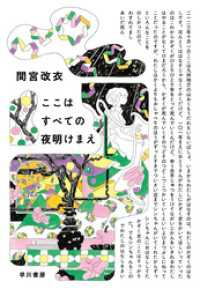
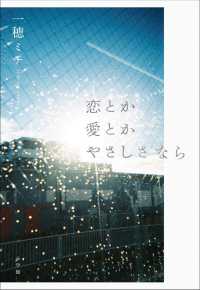
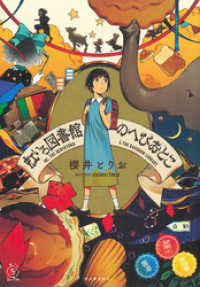

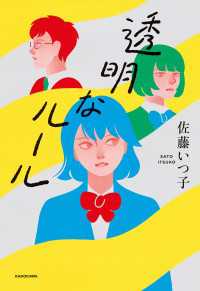
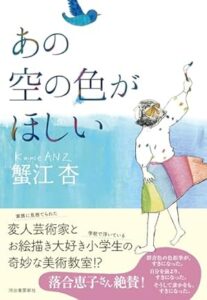

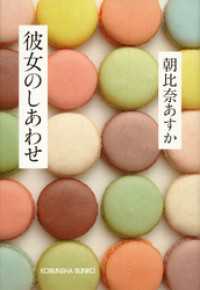

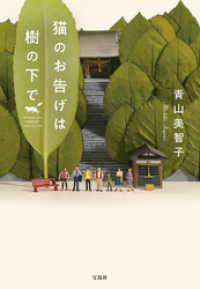
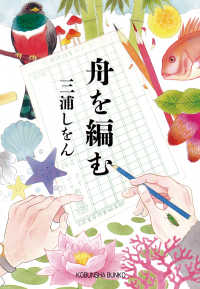
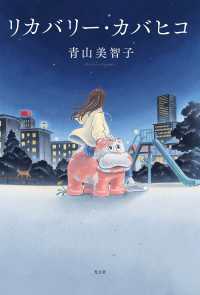

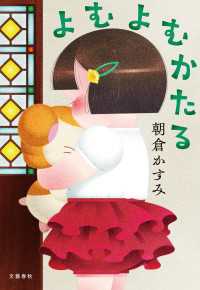



コメント