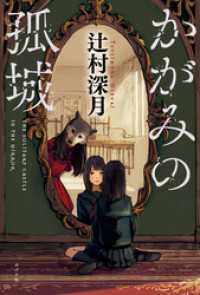
『かがみの孤城』は、読み始めたときの「思春期の繊細さを描いた優しい物語」という印象から、ページを進めるごとに加速度的に膨らんでいく作品でした。最初の方は、こころの学校での息苦しさや、家のなかのピリついた空気にあてられて、正直、読むこちらの心もヒリヒリしてきます。それでも本を閉じることができなかったのは、鏡の向こうの城で出会う七人の中学生とオオカミさまの存在が、どこか「救い」の予感を漂わせていたからだと感じました。 物語が進むにつれて、城という不思議な空間での交流と、それぞれが現実に抱えている事情の輪郭が少しずつ重なり合っていきます。違和感のように散りばめられていた“時間のずれ”や、フルーツティーのアキの存在、電気以外使えない城の制約などが、後半にかけて一気に意味を持ち始める流れは、本当に見事でした。 そして、エピローグで明かされる“あの人”の正体と、喜多嶋先生と子どもたちの関係がつながる瞬間で、完全に胸を掴まれました。物語全体が美しく収束していくのを見届けながら、「本ってこうやって終わるんだ」と静かに感動してしまう一冊でした。
【書誌情報】
| タイトル | かがみの孤城 |
|---|---|
| 著者 | 辻村深月【著】 |
| 出版社 | ポプラ社 |
| 発売日 | 2017/06 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784591153321 |
| 価格 | ¥1,980 |
学校での居場所をなくし、閉じこもっていた“こころ”の目の前で、ある日突然部屋の鏡が光り始めた。 輝く鏡をくぐり抜けた先にあったのは、城のような不思議な建物。 そこにはちょうど“こころ”と似た境遇の7人が集められていた―― なぜこの7人が、なぜこの場所に。 すべてが明らかになるとき、驚きとともに大きな感動に包まれる。 生きづらさを感じているすべての人に贈る物語。
本の概要(事実の説明)
物語の中心にいるのは、中学校でのいじめをきっかけに不登校になった中学生・こころです。彼女の部屋の鏡がある日突然光り、その向こうに不思議な城が現れます。そこには、オオカミの仮面を被った“オオカミさま”と、こころと同じように学校に行けない七人の中学生が集められていました。彼らは一年間のあいだ城に通うことを許され、城のどこかに隠された鍵を見つければ、どんな願いでも一つだけ叶えられるというルールを知らされます。 城の中での時間は、彼らにとって現実から避難できる安全地帯のようでありながら、同時に自分自身と向き合う場にもなっています。最初はぎこちなかった会話が少しずつほぐれ、距離が縮まっていく過程は、とても丁寧に描かれていました。一方で、現実世界では、こころの家庭の空気は張りつめており、母親にもなかなか本音を打ち明けられません。その「城の中では普通に話せるのに、家からは出られない」というちぐはぐさが、読んでいて胸に刺さりました。 全体としては、いじめや不登校といったテーマを扱いながらも、重苦しさ一色にはならず、ミステリーやファンタジーの要素、そして成長物語としての爽やかさも含んだ作品だと感じました。中高生はもちろん、大人の読者が読んでも、自分の過去や、今の親としての視点を重ねながら味わえる物語だと思います。
印象に残った部分・面白かった点
印象に残ったのは、こころが喜多嶋先生について考える場面です。こころは、もし真田さんがまた助けを求めてきても、喜多嶋先生は「真田さんの味方」ではなく「真田さんの周りの大人」であり続けるだろうと感じます。そのうえで、だからこそこの先生は信頼できる、と心のどこかで確信するところに、とても大きな安心感がありました。良いことも悪いことも含めて、現実を丸ごと受け止めたうえで隣にいてくれる大人の姿は、読んでいて涙が出そうになるほど心強く感じました。 また、城で過ごす七人の時間が、読み進めるほど愛おしくなっていったのも忘れられません。最初はぎこちない会話が続き、ちょっとした言葉の行き違いで空気が悪くなる場面もあります。思春期特有の、何気ない一言で心にヒビが入ってしまう感覚が、あまりにリアルで、何度も胸がキュッとなりました。それでも、誰かが誰かを庇ったり、さりげなく支え合ったりする姿が少しずつ増えていき、「この子たち、ちゃんとつながっていってる」と分かった瞬間に、じんとくるものがありました。 終盤の怒涛の伏線回収も圧巻でした。リオンの姉とオオカミさまの関係、フリースクールと鏡の城のつながり、時間のズレの意味など、物語のあちこちに散りばめられていたピースが一気に組み上がる感覚は、驚きと納得と感動が同時に押し寄せてくるようでした。
本をどう解釈したか
この作品を読みながら、「学校」という空間が子どもにとってどれほど大きな世界なのかを、改めて思い知らされた気がしました。大人になった今なら「学校がすべてじゃないよ」と言えるのに、当時の自分には到底そうは思えなかった、という感覚が物語の中で繰り返し立ち上がってきます。クラスで浮いてしまうこと、いじめられていると認めてもらえないこと、その苦しさを“たいしたことない”と片付けられてしまうこと。こころたちの孤独は、決して大げさではなく、あの年代にとっては「世界そのものが揺らぐ出来事」なんだと感じました。 鏡の城は、現実から逃げ込むための幻想的な避難場所であると同時に、本当の意味で“現実と向き合うための場所”でもあったように思います。そこで出会った仲間たちと過ごした時間や交わした言葉は、城が閉じられたあとも、形を変えてそれぞれの人生に影響を残していきます。たとえ記憶が薄れてしまっても、「誰かとつながれた感覚」だけは体のどこかに残っている。その描き方がとても優しくて、救いがあると感じました。 さらに、喜多嶋先生や保護者目線で物語を読むと、「大人は本当に子どもの苦しさをわかってあげられているのか」という問いが突きつけられているようにも感じました。自分なら我が子に優しく手を差し伸べられるだろうか、本当に“分かろうとする努力”を続けられるだろうか。読後に、静かに自問自答したくなる物語でした。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えたあと、一番強く心に残ったのは「大丈夫。大丈夫だから、大人になって」というメッセージでした。今まさに毎日を必死で生きている子どもたちにとっては、とても遠く感じられる言葉かもしれません。それでも、物語の最後までつきあった読者としては、「今がすべてじゃない」とそっと伝えたくなるような気持ちになります。 同時に、いじめや不登校を「よくあること」として片付けてしまう視線の危うさにも、気づかされました。周りの大人から見れば一瞬の出来事に見えるかもしれませんが、当事者にとっては、その瞬間が人生のすべてを塗り替えてしまうこともあります。だからこそ、「たかが学校」と言える側と、「そこが世界のすべて」の側の距離を、少しでも埋められる想像力を持ちたいと感じました。 そしてもう一つの気づきは、「再読したくなる物語の力」です。伏線の鮮やかさや構成の巧みさに圧倒されながら、読み終えた瞬間に「もう一度最初から読み直したい」と思いました。最初はただの違和感だった描写が、真相を知ったあとには別の意味を帯びて立ち上がってくる。そうした“二度目の楽しみ”を約束してくれる物語に久しぶりに出会えた気がしました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この作品は、静かな夜に、できれば一人でゆっくりと読み進めたい本だと感じました。家の灯りを少し落として、スタンドライトの下でページをめくっていると、こころの部屋の鏡がふと光り出してもおかしくないような、不思議な没入感があります。日中のざわざわした空気のなかよりも、夜の少し静まり返った時間帯のほうが、城の中の会話やこころの心の声に集中しやすいと思います。 また、自分の過去や今の立場について少し立ち止まって考えたいときにも向いていると感じました。思春期のころの痛みを思い出しながら読むのか、親や先生の立場で読むのかで、見える景色が変わってきます。読み終えたあとに、本を閉じて、少しだけ自分の周りにいる子どもたちや、かつての自分自身のことを思い返す時間を取ると、この物語の余韻がより深く沁みてくるように思いました。
『かがみの孤城』(辻村深月・著)レビューまとめ
『かがみの孤城』は、傷ついた中学生たちの物語でありながら、大人の読者にも静かに問いを投げかけてくる作品でした。不安定な心を丁寧にすくい上げ、見事な伏線回収と共に「生きていてほしい」という願いをそっと手渡してくれる一冊だと感じました。
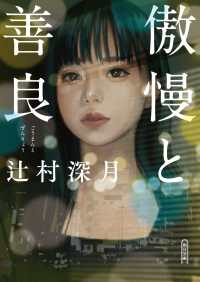
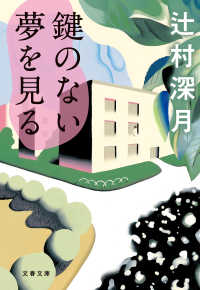


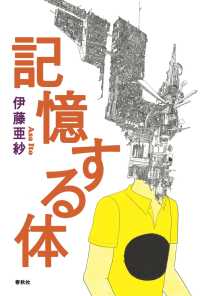
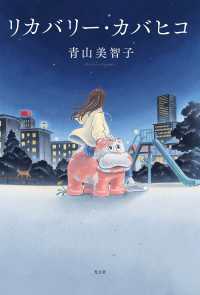
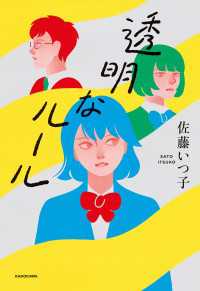

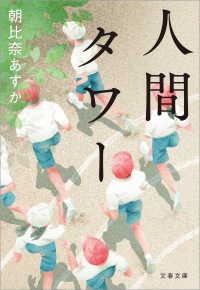
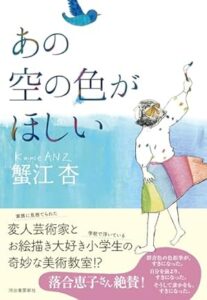
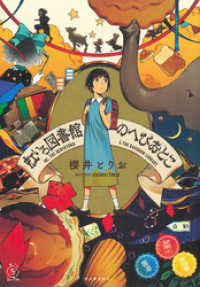
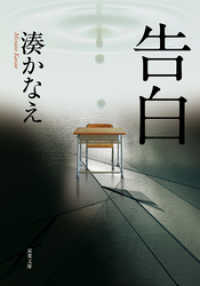

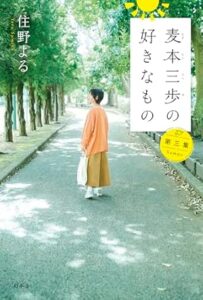
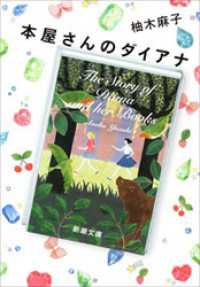
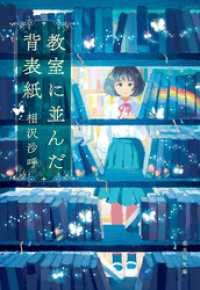
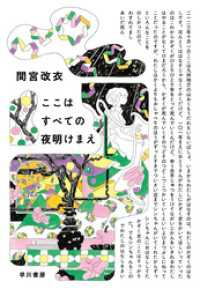



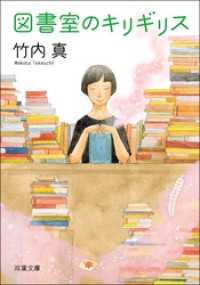
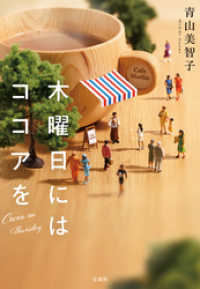
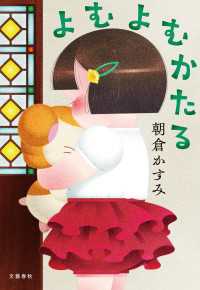

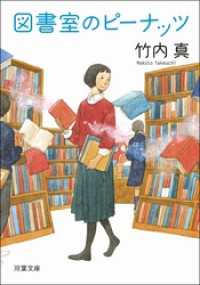
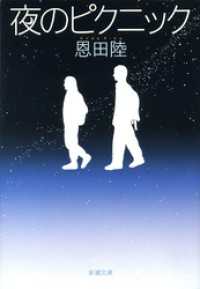
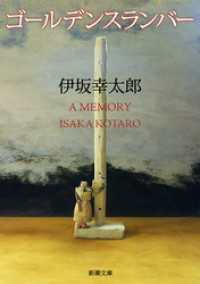
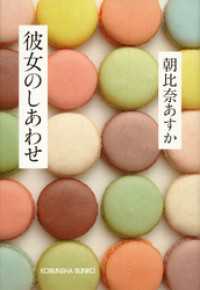
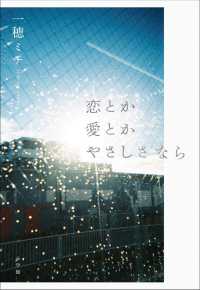
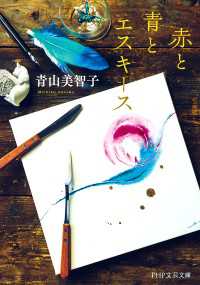
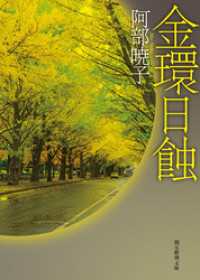
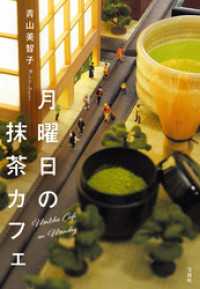
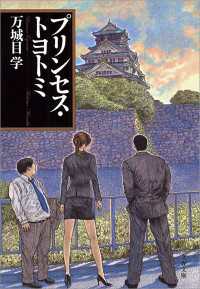

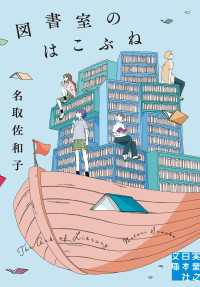

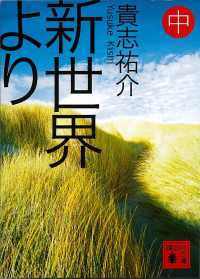
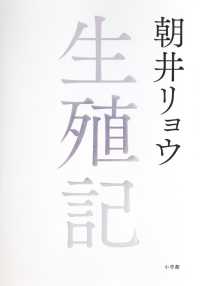
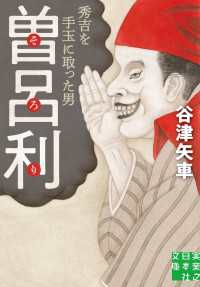




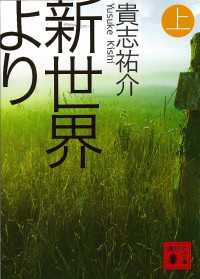

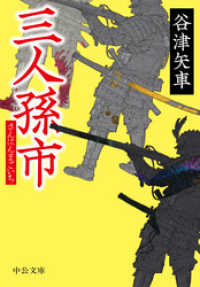
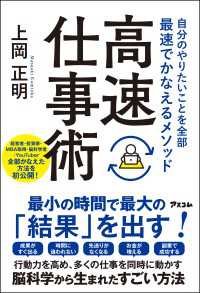
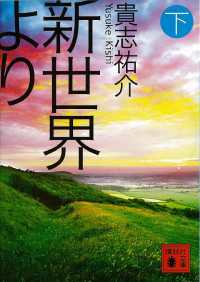
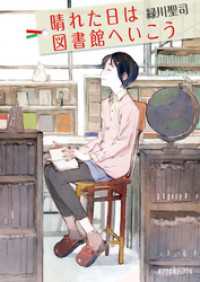
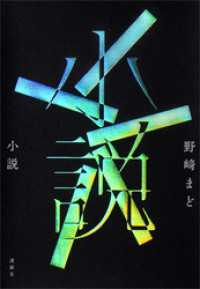
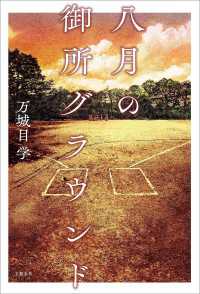
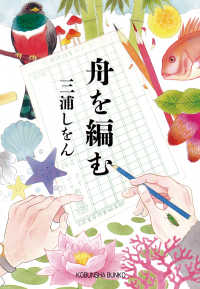
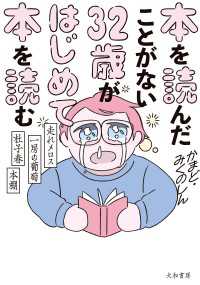

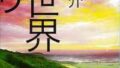

コメント