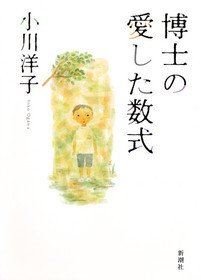
『博士の愛した数式』は、読みながら何度も「静かに胸の奥を撫でられる」ような感覚になる物語でした。激しい事件が起こるわけではないのに、ページを閉じたあともしばらく余韻が抜けない、そんな小説です。 「ぼくの記憶は80分しかもたない」という一文から始まる世界は、一見するととても残酷です。過去の交通事故の後遺症で、新しい記憶が80分しか持たない博士。彼のもとに通う家政婦の「私」と、10歳の息子ルート。三人が共に過ごす時間は、80分ごとに「はじめまして」からやり直しになります。それでも、彼らのあいだには確かに何かが積み重なっていく。そこに、どうしようもなく惹かれました。 私自身、数学は決して得意ではありません。それでも、博士が数字を語るときのまなざしや、オイラーの公式や素数へ向けられる敬意を読んでいるうちに、「数字ってこんなに美しいものだったのかもしれない」と、少しだけ世界の見え方が変わるのを感じました。数式の話なのに、最後には「愛」についての物語を読んでいたのだと気づかされる、その構造もとても印象的でした。
【書誌情報】
| タイトル | 新潮文庫 博士の愛した数式 |
|---|---|
| 著者 | 小川洋子【著】 |
| 出版社 | 新潮社 |
| 発売日 | 2011/10 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784101215235 |
| 価格 | ¥693 |
[ぼくの記憶は80分しかもたない]博士の背広の袖には、そう書かれた古びたメモが留められていた──記憶力を失った博士にとって、私は常に“新しい”家政婦。博士は“初対面”の私に、靴のサイズや誕生日を尋ねた。数字が博士の言葉だった。やがて私の10歳の息子が加わり、ぎこちない日々は驚きと歓びに満ちたものに変わった。あまりに悲しく暖かい、奇跡の愛の物語。寺尾聰主演の映画原作。
本の概要(事実の説明)
この作品は、第1回本屋大賞を受賞した長編小説で、ジャンルとしてはヒューマンドラマに数学と野球がやわらかく織り込まれた「小説・文学」に位置づけられると感じました。舞台はごく普通の日本の町。登場人物も、特別なヒーローではなく、記憶障害を抱えた老人と、30手前のシングルマザー、そして10歳の少年です。 物語は、家政婦紹介所から派遣された「私」が、博士の家に通い始めるところから静かに進んでいきます。博士は一見すると偏屈で、人付き合いが得意なタイプではありません。けれど、彼には数字に対する深い愛情があり、靴のサイズや誕生日といった日常の情報さえ、数式や素数に結びつけて語りはじめます。そこにやがて、息子のルートが加わり、三人の時間は少しずつ色を変えていきます。 大きな謎解きや劇的な展開があるタイプの物語ではありませんが、博士のささやかな変化、ルートの成長、「私」の心の揺れがしっかりと積み重なっていきます。プロ野球、とくに70年代の阪神タイガースのエピソードがたびたび登場するので、その時代の野球が好きな人には二重に楽しめる作品だと感じました。一方で、数学や野球に詳しくない読者でも、物語の核は「人と人の関係」なので、十分に味わえると思います。
印象に残った部分・面白かった点
一番心に残ったのは、博士がルートに向けるまなざしでした。博士は80分経つとルートの存在を忘れてしまうはずなのに、そのたびに同じように丁寧に接し、彼の解いた簡単な計算に対しても、惜しみない称賛を送り続けます。その姿を追っているうちに、「子どもを尊重する大人の態度」とはこういうものなのだと、胸がじんわりと温かくなりました。 また、ルートが博士へ贈り物をしようと、全力でプレゼントを探す場面も忘れられません。博士は自分の状態を完全には把握していないはずなのに、贈り物を受け取ったときには全身で喜びを表現します。ここには、血縁でも恋愛でもない、第三の「愛情のかたち」のようなものが描かれていると感じました。誰かに何かを贈りたい、ただ喜ぶ顔が見たい。その感情の純度の高さに触れて、思わず目頭が熱くなりました。 そして、博士の記憶が80分しか持たないという設定の切なさも、読み進めるほどに重みを帯びてきます。朝、目覚めるたびに昨日までの出来事を失っているという事実は、読者側には強い残酷さとして迫ってきます。ただ、その事実を「博士自身は知ることがない」という逆説的な救いも同時に描かれていて、読みながら何とも言えない複雑な感情になりました。悲しいのは、記憶を持ち続けている「私」とルートの側なのだと気づいたとき、彼らがあえてそれを引き受けて博士と向き合い続ける姿勢にも、静かな尊さを感じました。
本をどう解釈したか
この物語を読み終えてまず感じたのは、「数学」と「愛」がとても近いところに置かれているということでした。博士にとって、数字は単なる記号ではなく、世界を説明し、見えないつながりを証明するための言葉のようなものです。だからこそ、誕生日や電話番号や背番号といった日常の数字にも、美しさや意味を見出していきます。 それと同じように、博士・「私」・ルートの関係も、一見バラバラに見えて、少し引いて眺めると一本の数式のようにつながっているように思えました。恋愛とも家族愛とも違う、不思議な「ほのかな慕情」のようなものが三人を結んでいて、それが物語の最後まで一度も大きな声で名指しされることはありません。それでも、言葉にはされない感情が確かに存在している、と読者に伝わってくるところに、この作品の品の良さを感じました。 また、私はこの小説を「記憶の物語」というよりも、「忘れてしまうことの中に残るもの」を描いた物語として受け取りました。博士は80分ごとにすべてを忘れてしまうけれど、数字や野球の話題を通じて、同じような喜びを何度も表現します。その反復の中に、博士の核となる人柄や価値観が浮かび上がってくるのが面白かったです。記憶は消えても、人の本質や、誰かを思いやる心は、別の層に蓄積されていくのではないか――そう感じさせる描かれ方でした。 そして、ルートが大人になったときの進路や選択にも、静かなメッセージが込められているように思えました。博士との日々は、彼にとって単なる「不思議なおじさんとの思い出」ではなく、世界をどう見るか、数字や仕事や他者とどう向き合うかという「ものの見方」の根っこを形作っている。私には、そのように読めました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えてまず感じたのは、「時間は共有できなくても、経験は分かち合えるのだ」ということでした。博士の記憶は80分ごとにリセットされてしまうのに、「私」とルートの側には、確かに年月が積もっていきます。同じ出来事を何度も一から説明する大変さはあるはずなのに、二人はそれを「負担」としてではなく、「もう一度一緒に味わう機会」として受け取ろうとしているように見えました。その姿勢に、自分のまわりの人間関係を少しだけ優しく見直したい気持ちが芽生えました。 また、「役に立つかどうか」だけで物事を計ろうとする自分の癖にも気づかされました。博士が語る数学の美しさや、プロ野球の細かい記録は、日常生活に直結する情報ではありません。それでも、三人で机を囲んで数字の話をしたり、ラジオ中継に耳を傾けたりする時間には、確かな温度があります。効率や成果からこぼれ落ちる小さな楽しみこそが、日々を支えてくれるのかもしれないと感じました。 もう一つ印象的だったのは、「完全には理解し合えない相手と、どう一緒にいるか」という視点です。博士の頭の中で何が起きているのか、彼自身も、まして「私」やルートにも完全には分かりません。それでも、分からない部分をそのまま抱えたまま、無理に踏み込まず、できる範囲で寄り添おうとする。その距離感は、現実の人間関係にもそのまま持ち込める姿勢だと感じました。相手を「分かりたい」と思うことと、「分からない部分を尊重すること」は両立するのだと教えられた気がします。 そして最後に、「忘れられてしまうこと」は必ずしも悲劇だけではない、という視点にもハッとさせられました。80分ごとに関係が白紙に戻るからこそ、博士は何度でも新鮮な驚きと喜びを味わい、私たち読者も、その無邪気な反応に何度も出会います。変わらないものにしがみつくのではなく、その都度生まれ直してくる感情をていねいに受け止めること。それが、限りある時間の中でできる、ささやかな「愛し方」のひとつなのかもしれないと感じました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この作品は、静かな環境でページとじっくり向き合いたい本だと感じました。たとえば、家事や仕事を一通り終えたあとの夜、部屋の灯りを少し落として、温かい飲み物を片手に読み進めると、物語のトーンと自分の呼吸がだんだんと揃ってくるように思います。1日に数十ページずつ、大事に味わいながら読むのもおすすめです。 また、休日の午後、外の天気があまりよくない日に読むのも合いそうです。窓の外で雨の音がし、家の中が少し暗くなっていく時間帯に、博士の部屋の静けさや、ノートに数式が並んでいく様子を重ねていくと、自分も彼らの居間の片隅に座っているような気持ちになれました。 一気読みもできるページ数ですが、個人的には「今日はここまで」と余韻を残しながら何日かに分けて読むほうが、この物語には合っているように感じました。章の終わりごとにそっと本を閉じて、「博士は今ごろどんな夢を見ているだろう」「ルートは今どんな大人になっているのだろう」と想像してみる――そんな読み方をすると、物語世界との距離が心地よく保てると思います。
『博士の愛した数式』(小川洋子・著)レビューまとめ
読み終えると、胸の奥に静かな温かさが残りました。80分しか記憶が続かない博士が本当に愛した“数式”は、オイラーの等式ではなく、無垢な少年ルートそのものだったのだと感じます。
数式を扱うように丁寧で、驚くほど優しいまなざしを向ける博士。その姿に、血のつながりを越えて生まれる絆の確かさを思いました。忘れられても、消えないものがある。三人が育んだ静かな愛情が、読後にそっと灯り続けるような一冊でした。
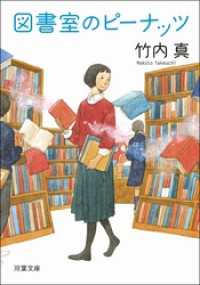
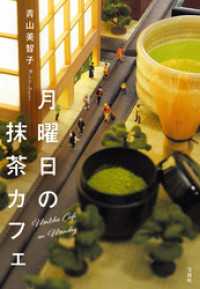
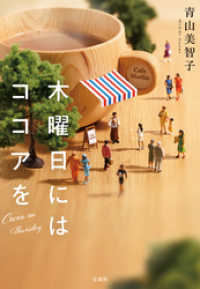


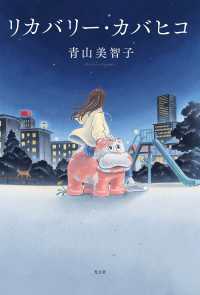
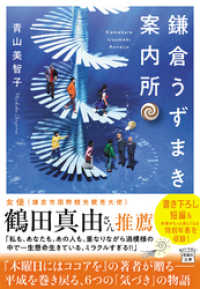
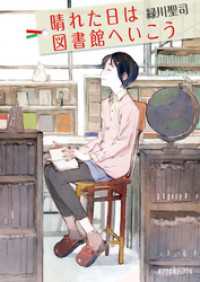
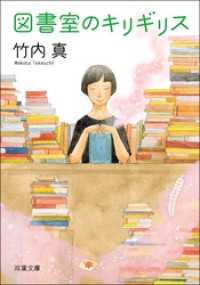

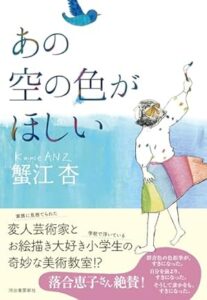


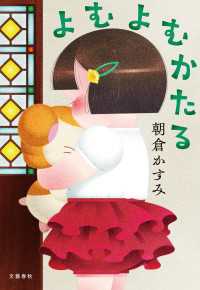


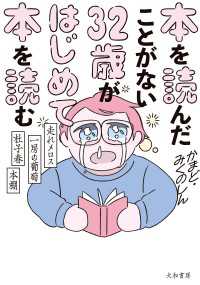

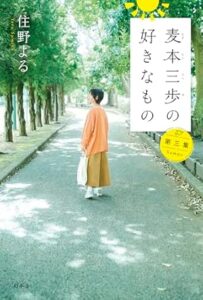

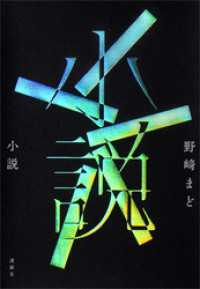

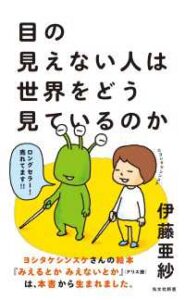
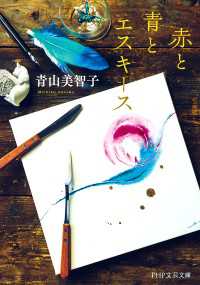
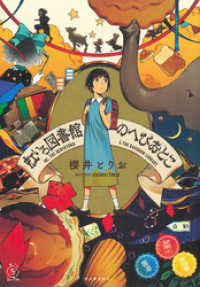
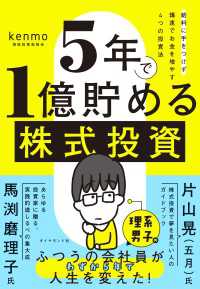
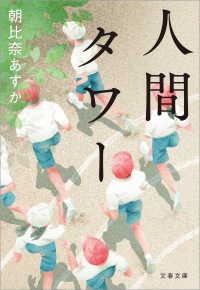


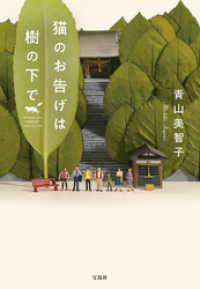
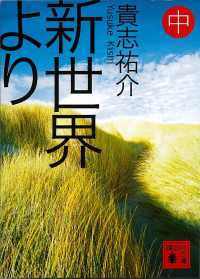
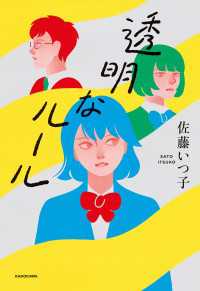



コメント