
高校入学式の朝、駅のホームでひったくり犯を追いかける少年と、その前に車いすで立ちはだかる少女。『カラフル』は、そんなドラマチックな一瞬から始まる青春小説です。車いすユーザーの少女・渡辺六花と、怪我で陸上競技を諦めた元トップランナーの荒谷伊澄。ふたりの出会いは、単なる「ボーイ・ミーツ・ガール」ではなく、世界の見え方そのものを揺さぶるきっかけになっていきます。 読み進めながら、私は何度も胸のあたりがきゅっと締めつけられるような感覚を覚えました。六花に対して伊澄が「……あんた車いすなのに」と口走ってしまう場面、そしてそれに対する「私、車いすじゃないですよ。車いすユーザーではあるけど」という六花の言葉。そこにあるのは、派手な差別発言ではなく、誰の中にも潜んでいそうな「無自覚のまなざし」です。だからこそ、自分のことを責められているような居心地の悪さと、「もっと知りたい」という好奇心が同時に湧きました。 物語の終盤で語られる「世界がカラフルであることは、いいことであるはずだ」というメッセージは、とてもシンプルです。でも、そこにたどり着くまでに描かれるのは、きれいごとでは済まされない現実の重さや、クラスメイトたちのぶつかり合い、そして自分の弱さと向き合う痛みでした。その過程を追体験することで、私自身の世界の色も少し変わったように感じています。
【書誌情報】
| タイトル | 集英社単行本 カラフル |
|---|---|
| 著者 | 阿部暁子【著】 |
| 出版社 | 集英社 |
| 発売日 | 2024/02 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784087901528 |
| 価格 | ¥1,760 |
高校入学式の朝、荒谷伊澄は駅のホームでひったくり犯を捕まえた。その際に、犯人の前に出て足止めをしようとしたのが、車いすに乗った少女だった。その後の事情聴取で判明したのだが、渡辺六花というその少女も、伊澄と同じ高校の新入生だった。弁が立ち気の強い六花に、伊澄はヤな女だな、と感じたのだが……? 夢を追い続けられなくなった少年と少女の挫折と再生の恋物語!
本の概要(事実の説明)
『カラフル』は、高校を舞台にした青春小説であり、同時に「多様性」「障害」「無自覚の差別」といったテーマを真正面から扱う現代的なヒューマンドラマだと感じました。主人公の伊澄は、かつてトップランナーとして期待されていたものの、怪我をきっかけに陸上を諦めた少年です。一方、六花は病気によって車いすユーザーとなった少女。二人は駅でのひったくり事件をきっかけに出会い、同じ高校のクラスメイトとして再会します。 物語の大きな山場となるのが、学校行事「強歩会」をめぐるエピソードです。長距離を歩くこの行事に、六花が「自分も参加したい」と希望したことで、クラス全体を巻き込む議論が始まります。危険を心配する声、本人の意思を尊重したい気持ち、面倒を押しつけられたくない生徒の本音…。様々な感情が入り混じり、教室の空気は一時、不穏なものすら帯びていきます。そこで担任の矢地先生が語る「少しだけでいいから、目の前の人の痛みを想像してほしい」という言葉が、物語全体の指針になっているように感じました。 伊澄と六花それぞれの家族との関係も、丁寧に描かれています。怪我をして以降、うまく気持ちを伝えられなくなった親子、病気によって「普通」から外れてしまった自分をどう受け止めるか悩む姿など、どこかで読者自身の経験と重なる部分があるように思えました。物語は決して説教くさくはなく、青春小説らしい甘酸っぱさや「キュン」とする瞬間もたくさんありながら、読後にはじわっと温かい余韻と考えるための種を残してくれる作品でした。
印象に残った部分・面白かった点
一番心に刺さったのは、六花の「私、車いすじゃないですよ。車いすユーザーではあるけど」という一言でした。この言葉に、伊澄だけでなく、読んでいる私もドキリとさせられました。六花を「車いすの子」と無意識にラベル付けして見ていた視線が、一瞬でひっくり返される感覚です。「車いすは道具であって、その人そのものではない」という当たり前の事実を、普段どれだけちゃんと意識しているだろうかと、自分に問い直したくなりました。 強歩会をめぐるホームルームの場面も、忘れがたいシーンです。六花が行事への参加を望んだことで、クラスは賛成・反対・戸惑いの感情に揺さぶられます。善意からくる「危ないからやめた方がいい」という意見、関わる負担を怖れる本音、六花の気持ちを汲み取りたい思い。それぞれの言葉にそれぞれの正しさがあるからこそ、教室の空気は重く、居たたまれないものになっていきます。その場にいる一人ひとりの気持ちが分かるようで、読んでいるこちらまで息苦しくなるほどでした。 そこに、矢地先生の「考えがバラバラで違うということは、絶望ではない」というメッセージが落とされます。全員が同じことを言うことが正解ではなく、違う考えを持ちながらも、お互いの気持ちを想像しあうことが大事だという視点に、救われるような気持ちになりました。 また、伊澄と六花の距離が少しずつ縮まっていく過程も、とても愛おしく感じました。六花の歌声に心を動かされる伊澄の姿、映画館での静かな「ありがとう」、駅員の長谷川さんのさりげない優しさに涙腺が緩む場面など、派手な告白シーンよりもずっと、静かなやりとりの中に本物の感情が宿っているように思えました。青春らしいときめきと、社会的なテーマの重さが、ちょうどよいバランスで溶け合っているのが、この作品の大きな魅力だと感じます。
本をどう解釈したか
この物語を読みながら、私は「差別とは、相手を分かろうとする意志を手放したときに始まる」という一節を何度も噛みしめました。『カラフル』が描いているのは、「悪意ある差別者」と「善良な被害者」という単純な構図ではありません。むしろ、自分の中にもある「分かろうとするのが面倒になってしまう瞬間」こそが問題なのだと、静かに指し示しているように思えました。 六花は、常に「強い人」として描かれているわけではありません。車いすユーザーとしてのしんどさも、周囲の過剰な配慮や、逆に無理解にさらされる疲れも、きちんと抱えています。それでも彼女は、自分を「かわいそうな存在」として扱ってほしいわけではない。自分の意思で「強歩会に出たい」と言い、その選択が「面倒事」として扱われてしまう痛みと向き合っています。そこにあるのは、「障害のある人」対「健常者」という対立ではなく、「一人の人間として見てほしい」という切実な願いのように感じました。 一方で、伊澄やクラスメイトたち、大人たちもまた、「正解のない問い」と格闘しています。六花を危険から守りたいと思う気持ちも、自分の生活やしんどさを守りたい気持ちも、どちらも現実的な感情です。その中で、先生が「自分のために生きながらも、誰かに少しだけ自分の力を貸すことを惜しまないでほしい」と語る場面は、この作品が提示する一つの答えに思えました。誰かの全部を背負う必要はないけれど、目の前の人の痛みに、少しだけ手を伸ばすこと。それなら、自分もやってみたい、と自然に思わせてくれる言葉でした。 タイトルの「カラフル」は、六花の車いすの色や世界の多様性だけでなく、「人それぞれの事情や感情が混じり合っていること」そのものを指しているように感じました。世界は決して明るい色だけではないけれど、モノクロでもない。その曖昧さを受け入れながら、自分の色で生きていくことを、物語はそっと後押ししてくれているように思えます。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えてから、駅のホームや街中で車いすユーザーの方を見かけたとき、これまでよりも少しだけ長く目を留めてしまう自分に気づきました。「どう接するのが正解なのか」を一瞬で判断することはできませんが、「この人はどんな気持ちなんだろう」と想像してみることなら、今すぐにでもできると感じたからです。世界の見え方が少し変わる、というのは、こういうことなのかもしれません。 また、「世界がカラフルであることは、いいことであるはずだ」というメッセージは、自分自身の生き方にもそのまま跳ね返ってきました。自分とは違う色を持つ誰かを怖れたり、面倒に感じたりする瞬間は、きっとこれからもあると思います。それでも、「違う色を持つ人がいるからこそ、世界は豊かになる」という視点を忘れずにいたい、と素直に思えました。 作品の中で、伊澄が「今からの一秒間だけが、自分でどうにかできるものだ」という言葉を胸に刻む場面も印象的でした。過去の怪我や挫折、取り返しのつかない選択は誰にでもあるけれど、「今の一秒」をどう使うかは、自分次第。その一秒を、誰かのために少しだけ使ってみる。そんな小さな選択の積み重ねが、世界を少しずつカラフルにしていくのかもしれません。 この物語は、中高生にこそ読んでほしいと感じる一方で、大人だからこそ刺さる言葉もたくさん散りばめられていました。「大人というのは、歳をとった少年少女のことなのよ」という一節に、一瞬ドキッとしつつ、どこか救われるような気持ちになりました。年齢を重ねても、自分の中の「少年少女」の部分を大事にしていたい。その思いを、改めて確認させてくれる一冊でした。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この本は、静かに自分と向き合える時間に読むのが一番しっくりくると感じました。たとえば、一日の終わり、家事や仕事がひと段落した夜に、ベッドやソファでゆっくりページを開くような時間です。六花や伊澄、クラスメイトたちの本音がぶつかり合うシーンは、感情が揺さぶられてなかなか現実に戻れないかもしれません。だからこそ、その余韻を抱えたまま、そっと明かりを消せる夜の読書が似合うと思いました。 もうひとつは、自分の気持ちが少し曇っているときや、「人付き合いに疲れたな」と感じたときです。クラスの議論のように、考えがバラバラであることが絶望ではなく、むしろ希望に変わっていく過程を見ていると、「完璧に理解し合えなくても、一緒に悩むことには意味があるのかもしれない」と思えてきます。世界のざらざらした部分をきちんと描きつつ、最後にはそっと背中を押してくれる物語なので、心が少し弱っているときにも、優しく寄り添ってくれる一冊だと感じました。
『カラフル』(阿部暁子・著)レビューまとめ
『カラフル』は、車いすユーザーの少女と、夢を諦めざるを得なかった少年が出会い、「世界の色」と向き合っていく青春物語です。多様性や無自覚の差別といった重いテーマを扱いながらも、説教ではなく、等身大の高校生たちの言葉と葛藤を通して読者に問いを投げかけてきます。世界は決してきれいな色だけではないけれど、それでも「カラフルであってほしい」と願えること。その感覚を、静かに、でも確かに思い出させてくれる一冊でした。
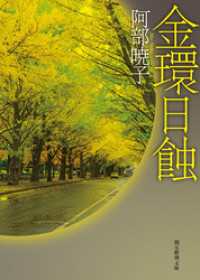

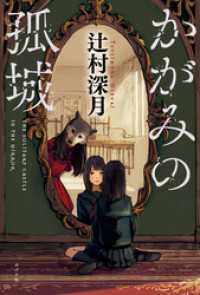


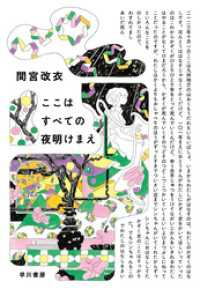
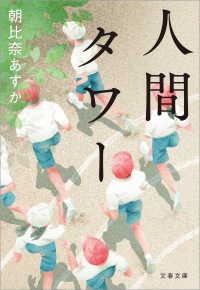
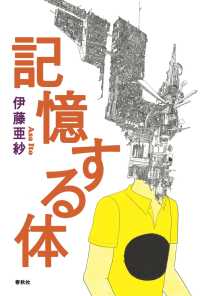
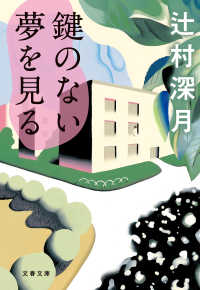

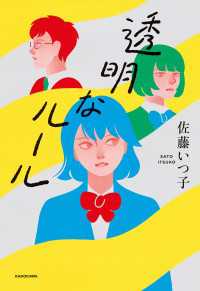
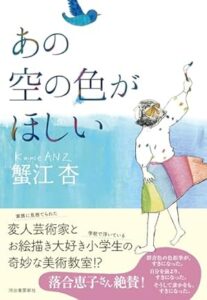

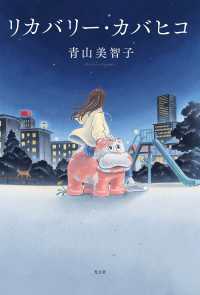
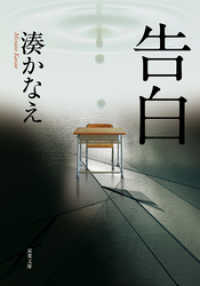
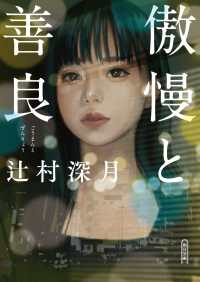
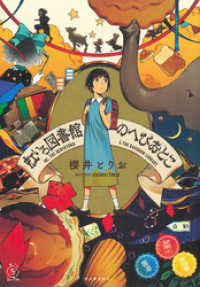
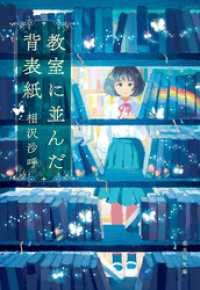
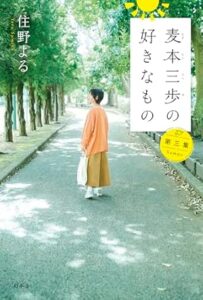

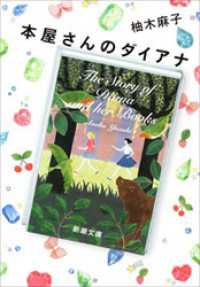

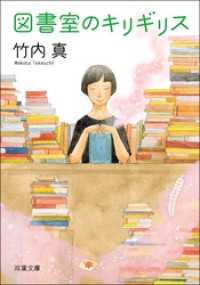
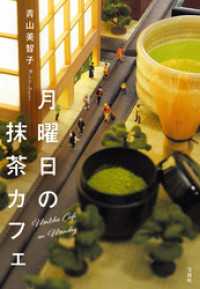

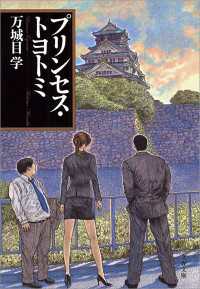
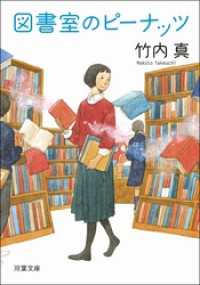
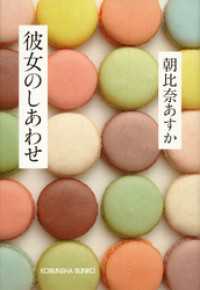
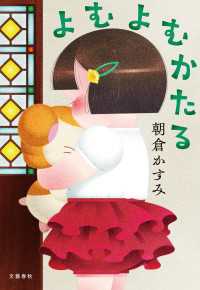
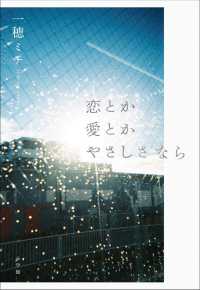
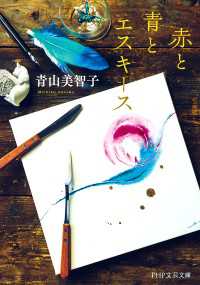
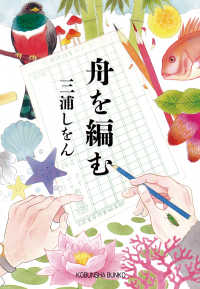
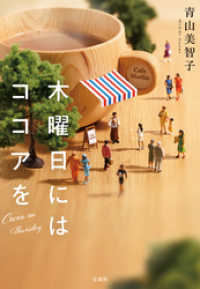
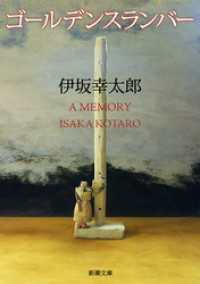
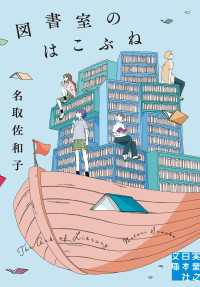

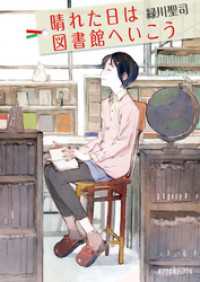
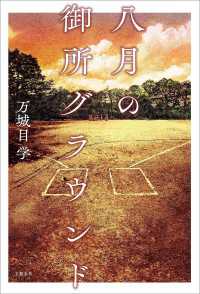
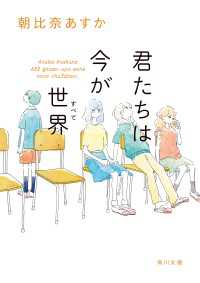
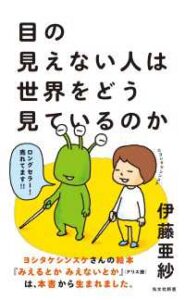
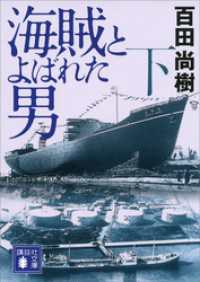


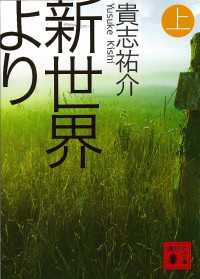

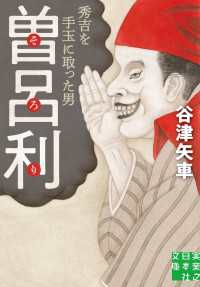

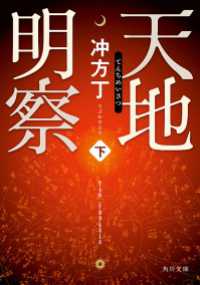
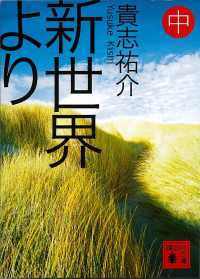
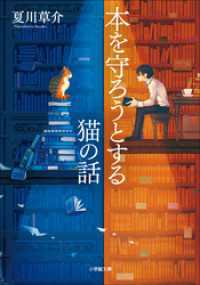
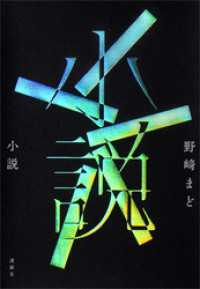


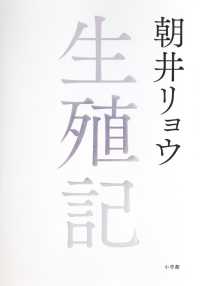


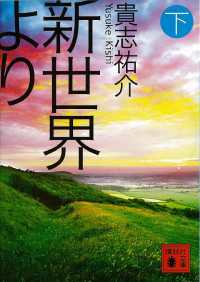




コメント