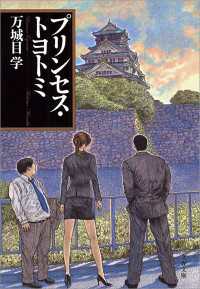
ページをめくりながら、「なんてむちゃくちゃで、なんて真面目な小説なんだろう」と何度も思いました。『プリンセス・トヨトミ』は、大阪という街を舞台に、「大阪国」という架空の国家の秘密と、そこに切り込む会計検査院の調査官たちの攻防を描いた物語です。設定だけ聞くとコメディ寄りのファンタジーに見えますが、読み進めるほど、その芯には深い「愛」と「誇り」があると感じました。 私自身、大阪に特別な縁があるわけではないのですが、気づけば空堀商店街や大阪城、北浜の近代建築をネットで調べたくなり、「大阪ってこんな街なのか」と想像をふくらませていました。歴史ロマンとご当地感、そしてちょっとバカバカしいほどスケールの大きい仕掛けが、万城目学さんらしい軽妙な文体で一気につながっていきます。 読み終えたあとに残るのは、「大阪国すごい!」というより、「人が土地を愛し続けることって、こんなにおかしくて、こんなに尊いんだな」という不思議な温かさでした。タイトルから想像するプリンセス物語とはかなり違いますが、そのギャップも含めて、とても面白い読書体験でした。
【書誌情報】
| タイトル | 文春文庫 プリンセス・トヨトミ |
|---|---|
| 著者 | 万城目学 |
| 出版社 | 文藝春秋 |
| 発売日 | 2012/05 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784167788025 |
| 価格 | ¥865 |
このことは誰も知らない──四百年の長きにわたる歴史の封印を解いたのは、東京からやって来た会計検査院の調査官三人と、大阪下町の空堀(からほり)商店街で生まれ育った少年少女だった。秘密の扉がついに開くとき、大阪が全停止する!? それは五月末日の木曜日、午後四時のことであった。『鴨川ホルモー』『鹿男あをによし』で知られる奇想天外な万城目ワールドの、これぞ真骨頂。映画化原作。特別エッセイ「なんだ坂、こんな坂、ときどき大阪」も収録。
本の概要(事実の説明)
ジャンルとしては、現代日本を舞台にした歴史ファンタジー、あるいはご当地エンタメ小説だと感じました。物語の中心にあるのは、「大阪には『大阪国』という秘密の国家が存在している」という大胆な前提です。大阪城の地下に広がるその国には、代々受け継がれてきた役割を背負う人々がいて、外の世界と微妙なバランスを取りながら存在し続けてきました。 そこにメスを入れようとするのが、会計検査院の調査官たちです。鬼のように容赦がない松平、柔らかさと鋭さを併せ持つ鳥居、そして一見頼りなさそうで掴みどころのない旭。それぞれ個性的な三人が、大阪のとある社団法人の補助金をめぐって調査を進めるうちに、「大阪国」の存在へと近づいていきます。35年前の検査では会計検査院側が敗れたという過去があることも、じわじわと緊張感を高めていました。 一方で、もうひとつの軸として描かれるのが、女の子になりたいと願う真田大輔と幼なじみの茶子、そして大輔の父親・真田幸一の物語です。セーラー服で登校する大輔、その大輔を全力で守ろうとする茶子。そこに、大阪国の総理大臣である父の存在が重なり、ジェンダーの葛藤と家族の物語が、「大阪国」の行方と自然に絡み合っていきます。 歴史上の豊臣・徳川・真田などにゆかりのある名字がさりげなく登場し、戦国時代の大阪の陣と現代の「大阪全停止」が重ね合わされているのも印象的でした。歴史好きならニヤリとするポイントが多く、そうでなくても「なんだかとんでもないことが起きている」というワクワク感で最後まで引っ張られる構成になっていると感じました。
印象に残った部分・面白かった点
いちばん強く心に残ったのは、「大阪国」という突拍子もない設定を突き詰めていくと、その中心にあるのはとても人間くさい「愛」だとわかってくるところでした。豊臣家の末裔を守り続けてきた男たちの世代を超えた忠誠心、故郷としての大阪を守ろうとする土地への愛、そして親が子を思い続ける親子愛。レビューの一つに「歴史を超えた世代愛、親子愛、地域愛」とありましたが、まさにその通りだと感じました。 会計検査院との攻防も、単なる正義対悪の構図にはなっていません。大阪国側に肩入れしたくなる場面があれば、松平たち検査官の論理も分かる。最後に松平が「我々の負けだ」「好きなだけ大阪国を守り続けたらいい」と判断する場面は、単なる敗北宣言以上の重みを持って胸に響きました。そこには、「正直であろうとした人たちへの敬意」が含まれているように思えました。 そしてもうひとつのハイライトは、大輔と茶子の関係です。大輔が「男でいること」に違和感を覚え、セーラー服で登校する決断をする。その選択に対して、茶子が悪ガキたちに徹底抗戦する姿は、ジェンダーを超えた「人としてのまっすぐさ」を感じさせてくれました。担任の後藤先生が「正直であることは難しい。これからは闘いだぞ」と告げる場面も含めて、「自分に正直に生きるって、こんなにも勇気がいることなんだ」としみじみ思わされました。 大阪城の地下に広がる秘密の通路や、大阪全停止の合図とともに街が一斉に動き出す描写も、純粋に物語として胸が高鳴るシーンでした。読んでいるあいだは、「大阪の男たちが本当にこんな秘密を守っているのでは?」と錯覚してしまうほどの説得力がありました。
本をどう解釈したか
私はこの作品を、「虚構が現実の隙間を埋めていく物語」として読みました。歴史的には徳川の城になり、その後再建された大阪城に、「実は太閤さんの城が、もうひとつの層として隠れているのではないか」。そんな二重構造の発想をそのまま小説全体に広げたような作品だと感じました。大阪国という虚構は、現実の大阪にある土地の記憶や、そこに暮らす人たちの無意識の連帯を形にしたもののようにも思えます。 同時に、「正直であること」の難しさと尊さを、さまざまな立場から描いた物語でもあると感じました。会計検査院の側には、税金の使われ方をただそうとする職業倫理があり、大阪国の側には、歴史と誇りを守ろうとするロイヤルティがある。大輔は自分の性自認に正直であろうとして、茶子は大輔を守るために「戦う」ことを選ぶ。どの立場も一方的な善悪ではなく、「正直でいたい」という願いと、「正直でいることのしんどさ」が同居しているように見えました。 大阪のおっちゃんたちの熱さと同じぐらい、大阪のおばちゃんたちも全部分かっていて見守っている、という構図も面白かったです。男性たちが密かに守っているつもりの秘密を、実は女性たちがだいぶ前から察していて、最後に大きな存在感を発揮する。この構図は、「家庭の中の力関係」や「見えていない支え」を象徴しているようで、思わずニヤリとしてしまいました。 歴史ロマン、ジェンダーの揺らぎ、地方都市への愛、税金と公共性。これだけ多くのテーマを、「大阪国」という一つの虚構でつないでみせる構成力に、改めて万城目学さんの巧さを感じました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えたあと、私の中に一番強く残ったのは、「正直であることは難しい。でも、それでも正直であろうとする人たちが好きだ」という気持ちでした。大輔がセーラー服を着て教室に立つまでの葛藤も、その姿を見てなお彼を守ろうとする茶子の行動も、自分の価値観を押しつけるのではなく、「この人はこうありたいんだ」と認める姿勢が感じられて、胸が熱くなりました。 また、「土地を愛する」ということについても考えさせられました。大阪国の男たちは、顔も知らないプリンセスを守るために、日常の裏で膨大な秘密を抱え続けています。それはもちろんフィクションなのですが、「自分が生まれ育った土地を誇りに思いたい」という願い自体は、とてもリアルだと感じました。大阪をよく知らない私でも、物語を通して「大阪城を見上げたくなる気持ち」が少し分かった気がします。 そして、「絶対にありえないような話を、大真面目に信じてみる時間」は、日常に必要だなと感じました。ファンタジーを読むことは、現実逃避というより、「現実を別の角度から見るための訓練」のようなものかもしれません。会計検査院のような固い制度も、大阪のおっちゃんたちのような泥くさい情熱も、両方が同じ世界の中で共存している。そう思うと、ニュースで見る世界も少し違って見えてきそうです。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この作品は、まとまった時間が取れる静かな休日に読むのがおすすめだと感じました。530ページを超えるボリュームがあることもあり、細切れに読むよりも、半日〜一日を使ってどっぷり大阪国の世界に浸かった方が、物語の熱量を素直に受け取れると思います。コーヒーやお茶を淹れて、ソファやベッドに腰を落ち着けつつ、「今日は大阪に小旅行するぞ」という気分で読み始めるのが似合う一冊でした。 また、休日の午後に、少し気分転換をしたいときにも向いていると感じました。会計検査院の堅いロジックと、大阪のおっちゃんたちの情の厚さ、大輔や茶子のまっすぐな決意が次々に押し寄せてくるので、読んでいるうちに自分の中の凝り固まった感覚がほぐれていくような感覚がありました。「最近ちょっと現実が味気ないな」と感じたときに開くと、世界の見え方が少し色鮮やかになるかもしれません。
『プリンセス・トヨトミ』(万城目学・著)レビューまとめ
『プリンセス・トヨトミ』は、大阪に「大阪国」という架空の国家をつくり上げ、そのありえない設定を通して、世代を超えた愛情や土地への誇り、人が正直に生きようとする姿を描いた物語だと感じました。会計検査院VS大阪国という図式にワクワクしながら読み進めるうちに、気づけば大阪という街と、そこで生きる人たちが少し愛おしく見えてきます。大阪に縁がある人も、そうでない人も、「こんな秘密が本当にあってもいいかもしれない」と、ニヤリとしながら楽しめる一冊でした。

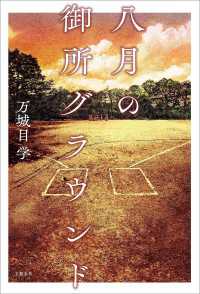
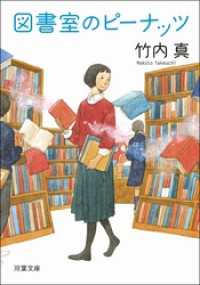
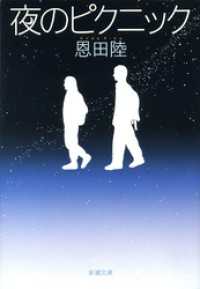
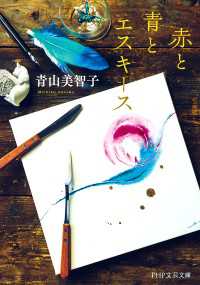
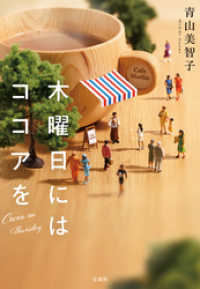
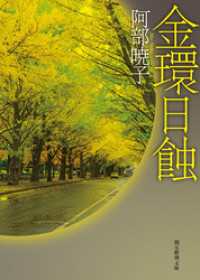


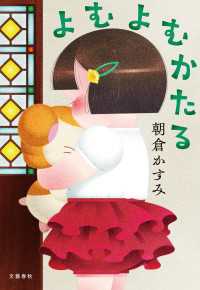

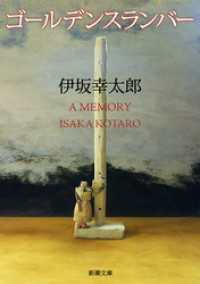
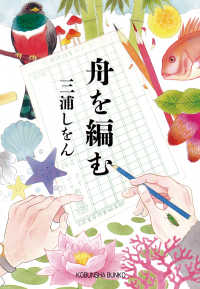
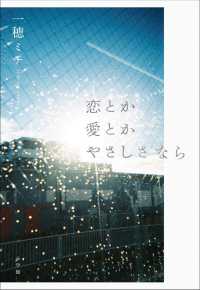
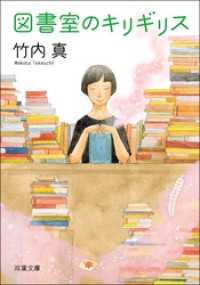
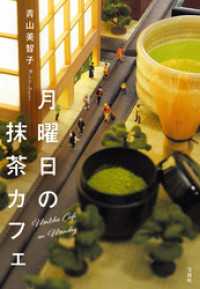

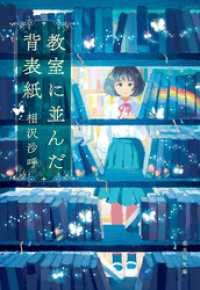


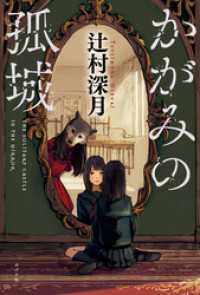
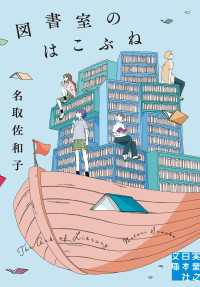
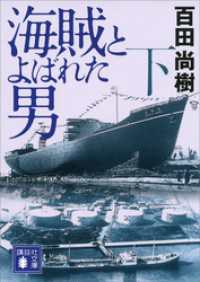
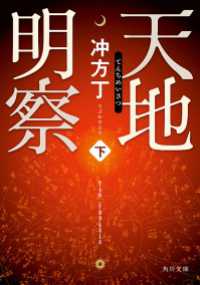



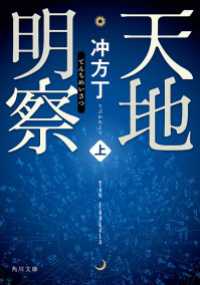
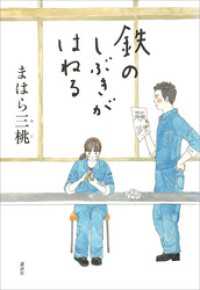
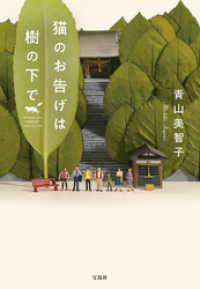

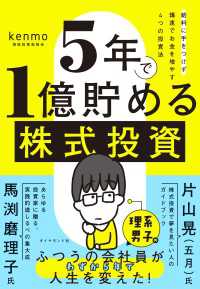

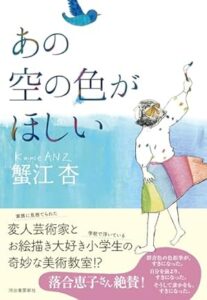

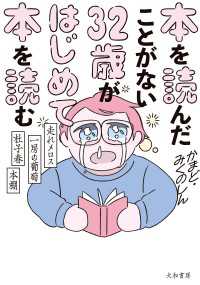
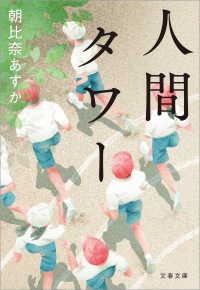


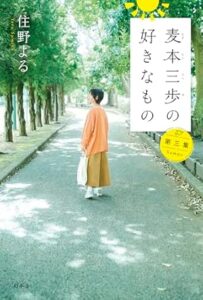
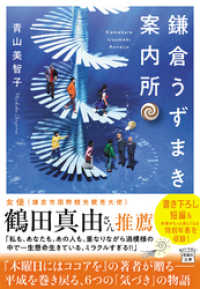


コメント