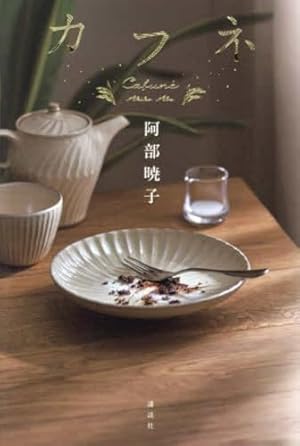
最愛の弟を突然失い、離婚をきっかけに生活も心も荒んでいた薫子。そんな彼女が出会うのは、弟の元恋人・せつなと、家事代行サービス会社「カフネ」での仕事でした。弟の死から物語が始まるので、最初はかなり重たい設定だと感じましたが、読み進めるほどに「これは喪失の物語であると同時に、再生の物語でもあるのだ」と思えるようになりました。 特に印象的だったのは、せつなが作る料理の描写です。最初は無愛想で、正直ちょっと付き合いにくそうな人物に見えるせつなが、キッチンに立つときだけは別人のようにテキパキと動き、温かな手料理を黙々と作り出していきます。その姿を見ているだけで、読んでいるこちらの心まで少しほぐれていくように感じました。 弟を失った喪失感、親との葛藤、自分のこれまでの生き方への違和感――そうしたものを抱えた薫子が、「誰かのためにご飯を作り、誰かと一緒に食べる」というごく日常的な行為を通して、少しずつ自分の居場所を見つけ直していく。その過程がとても丁寧に描かれていて、ページをめくるたびに胸がじんわりと温かくなりました。
【書誌情報】
| タイトル | カフネ |
|---|---|
| 著者 | 阿部暁子【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2024/05 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784065350263 |
| 価格 | ¥1,870 |
☆2025年本屋大賞受賞作☆【第8回未来屋小説大賞】【第1回あの本、読みました?大賞】一緒に生きよう。あなたがいると、きっとおいしい。やさしくも、せつない。この物語は、心にそっと寄り添ってくれる。最愛の弟が急死した。29歳の誕生日を祝ったばかりだった。姉の野宮薫子は遺志に従い弟の元恋人・小野寺せつなと会うことになる。無愛想なせつなに憤る薫子だったが、疲労がたたりその場で倒れてしまう。実は離婚をきっかけに荒んだ生活を送っていた薫子。家まで送り届けてくれたせつなに振る舞われたのは、それまでの彼女の態度からは想像もしなかったような優しい手料理だった。久しぶりの温かな食事に身体がほぐれていく。そんな薫子にせつなは家事代行サービス会社『カフネ』の仕事を手伝わないかと提案する。食べることは生きること。二人の「家事代行」が出会う人びとの暮らしを整え、そして心を救っていく。
本の概要(事実の説明)
『カフネ』は、現代日本を舞台にしたヒューマンドラマであり、「食」と「家事代行」を通じて孤立しがちな人々の心を描く小説だと感じました。物語は、弟・春彦の急死から始まります。努力で人生を切り開いてきた姉・薫子は、不妊治療と離婚を経験し、生きる意味を見失いかけていました。そこに現れるのが、弟の元恋人・小野寺せつなです。 第一印象は最悪と言っていいほど、薫子とせつなは噛み合いません。せつなはぶっきらぼうで遅刻もするし、愛想もない。ところが、薫子が体調を崩したことをきっかけに、せつなの部屋でふるまわれた料理が、すべてを少しずつ変えていきます。温かい手料理を前にしたときの薫子の身体と心のほどけ方は、とてもリアルで、「ああ、人ってこうやって“食べること”に救われるんだよな」としみじみ感じました。 やがて、薫子はせつなが働く家事代行サービス「カフネ」の手伝いをするようになります。「カフネ」が訪れる家々には、ネグレクト、介護疲れ、孤立、経済的困窮など、現代日本が抱える問題の縮図のような事情が詰まっています。けれど、この物語は「問題の列挙」で終わらず、そこに暮らす人たちの小さな希望や救いを丁寧にすくい上げていると感じました。 短編集のように読みやすい構成でありながら、物語の後半に向けて登場人物たちの背景が少しずつつながっていき、最後には伏線が怒涛のように回収される展開もあります。重いテーマを扱いつつも、読後感は不思議と爽やかで、「今の時代にこういう物語が求められるのもわかる」と思える一冊でした。
印象に残った部分・面白かった点
この物語でいちばん心に残ったのは、「誰かにご飯を作ってもらうこと」「誰かと一緒にご飯を食べること」の尊さでした。薫子がせつなの部屋で、久しぶりに温かな手料理を口にする場面は、ただの食事シーンではなく、凍りついていた心と身体がじんわりと溶け出していく儀式のように感じました。卵味噌を作ってみたくなる、という感想にもとても共感しました。 また、家事代行「カフネ」で訪れる各家庭の描写も印象的です。不安定な家庭環境の子ども、介護に追われる家族、孤独の中で暮らす高齢者……彼らの日常は決してドラマチックではないのに、ちょっとした仕草や言葉から、その人の人生の重さがにじみ出てきます。たった二時間の家事代行を終えたあと、「ありがとう」と言われたことで、薫子が自分の存在価値を少し取り戻していく描写も、とても胸に響きました。 そして何より、春彦という弟の存在です。みんなに好かれようとし、空気を壊さないように振る舞い続けたがゆえに、自分の心を削ってしまったような彼の生き方は、今の時代を象徴しているようにも思えました。彼が生前に残した「カフネ」へのつながりや、遺言書の意味が最後に明かされていく展開には、何度も涙をこらえきれませんでした。
本をどう解釈したか
『カフネ』は、単に「心温まるごはん小説」ではなく、現代の孤立と不安を背景にした“再接続”の物語だと感じました。核家族化、シングルでの子育て、老老介護、経済的な不安――そうした問題が静かに積もる中で、人は「自分一人でなんとかしなきゃ」とますます追い詰められていきます。 そんな世界の中で、「家事代行サービス」は単なる便利なサービスではなく、「誰かに頼ってもいい」というサインのように描かれています。自分ではどうにもできなくなった生活に、見知らぬ誰かが入り込み、掃除や料理をする。その行為は合理的な家事代行であると同時に、「あなたの暮らしは大切にされていいんですよ」というメッセージでもあるように思えました。 タイトルの「カフネ」が「愛する人の髪にそっと指を通す仕草」を意味するという説明もとても象徴的です。派手なドラマではなく、ほんのささやかなタッチ、ささやかな料理、ささやかな言葉。そうした“小さなケア”の積み重ねが、人をもう一度生き直させる力を持っているのではないか、と感じました。 また、不妊治療や離婚、家族とのぎこちない関係など、「うまくいかなかった人生」の断片があえて綺麗事ではなく描かれているところも印象的でした。分かりあえない親との関係を完全に解決するのではなく、それでも「見捨てずに向き合おうとする薫子の選択」が描かれることで、この物語は単なる癒やしにとどまらないリアリティを持っていると思いました。
読後に考えたこと・自分への影響
読後、強く心に残ったのは、「人は一人では生きていけない」という、どこまでもシンプルで、けれど忘れがちな真実でした。誰かにご飯を作ってもらうこと、誰かのために掃除をすること、たった二時間の家事代行で「ありがとう」と言われること。そうした小さな関わりの積み重ねが、人の自己肯定感や生きる力を支えているのだと改めて感じました。 また、「優しい人ほど、自分の本音を飲み込みすぎて傷ついていく」という描写にもハッとさせられました。空気を読みすぎるあまり、自分の気持ちを押し殺してしまう人は、現代に本当に増えているように思います。本書を読んで、優しさだけではなく、「自分の気持ちを言葉にする強さ」も同じくらい大切なのだと気づかされました。 「今がずっと続くわけではない」「明日はまったく違う日になりうる」という感覚も印象的でした。弟の死や、家事代行の現場で出会うさまざまな家庭の事情を通じて、「今この瞬間を大切に生きる」ことの重さが、説教くささではなく物語として伝わってきます。私自身も、身近な人にきちんと気持ちを伝えることや、小さな「ありがとう」を言葉にすることを、もっと意識したいと思いました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この本は、日々の生活に少し疲れてしまったとき、静かな時間の中でゆっくり味わいたい物語だと感じました。おすすめは、家事を終えた夜、温かい飲み物を片手にソファで読む時間です。ページをめくるごとに、張りつめていた心が少しずつ緩んでいき、最後には静かに涙がこぼれるような読書体験になると思います。 もうひとつおすすめなのは、ちょっと気持ちが不安定な週末の午後です。仕事や家庭のことに追われて、「自分のことを考える余裕なんてない」と感じているときこそ、この本の登場人物たちの姿が心に刺さるように思えました。彼らの不器用さや葛藤に寄り添ううちに、「自分も完璧じゃなくていい」「誰かに頼ってもいい」と少しだけ思えるようになるかもしれません。
『カフネ』(阿部暁子・著)レビューまとめ
弟の死、離婚、家族との確執、そして家事代行を通じて出会うさまざまな人たち。『カフネ』は、決して軽くはないテーマを扱いながらも、最後には「それでも人と一緒にご飯を食べて、今日を生きていこう」と思わせてくれる物語でした。泣きたい夜や、心が少しささくれ立っているときに、そっと寄り添ってくれる一冊だと感じました。
読後の余韻を深めるための読書サービス
この本は、読み終えた瞬間に何かが完結するというより、あとから静かに効いてくるタイプの一冊だったように感じました。
ページを閉じたあとも、ふとした瞬間に言葉や場面を思い出して、「もう一度考えてみたい」と思わせる余韻が残ります。
もし、そうした感覚をもう少し大切にしたいなら、文字とは違うかたちで触れ直すのも一つの方法です。
Audibleは、オーディオブックやポッドキャストを含む数十万作品が聴き放題で、30日間の無料体験があり、月額1,500円でいつでも退会できます。
移動中や家事の合間など、日常の中で考え続ける時間をつくりたい人には、無理のない選択肢だと思いました。

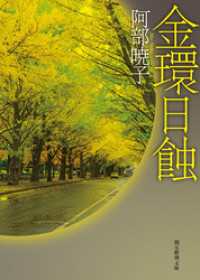
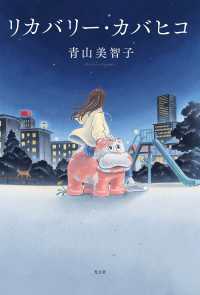
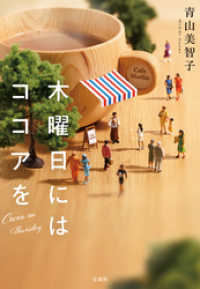

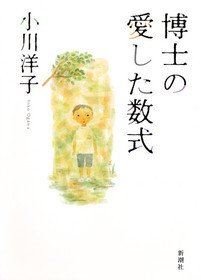


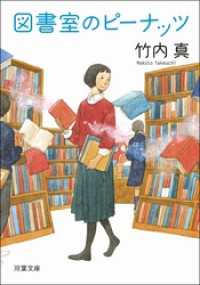

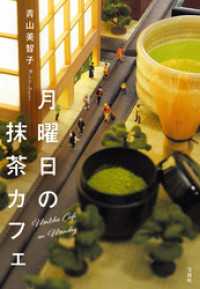
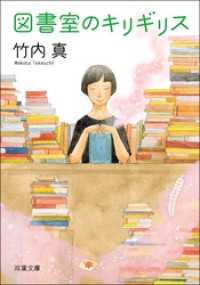
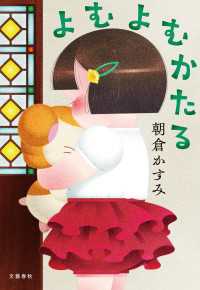
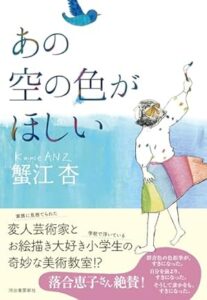
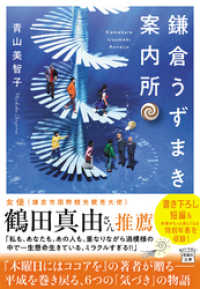

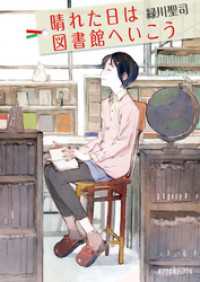
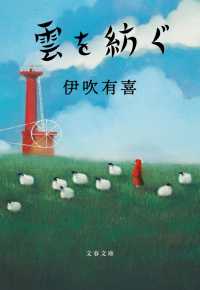
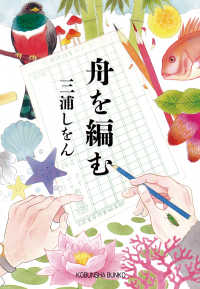
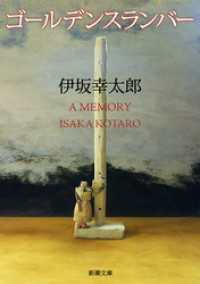
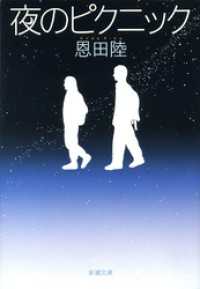
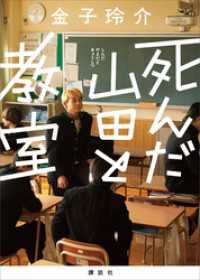
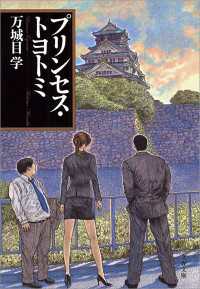
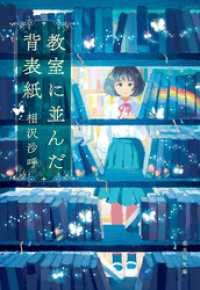

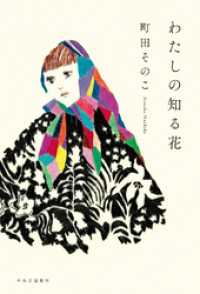
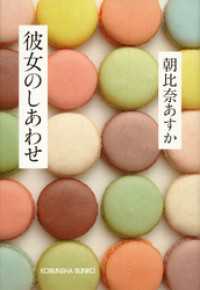

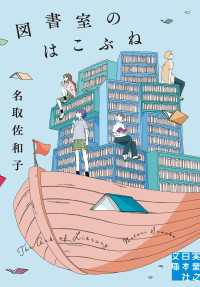
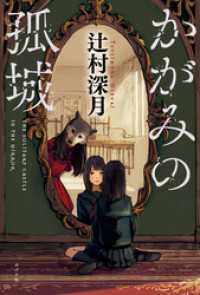
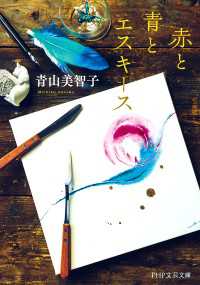
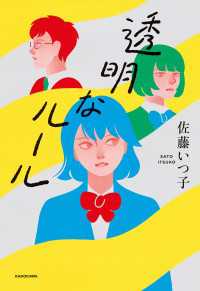
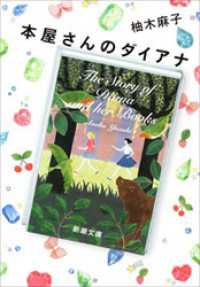
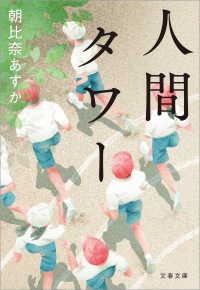
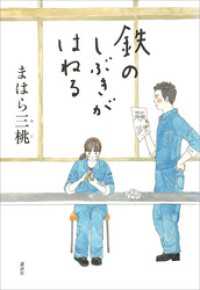

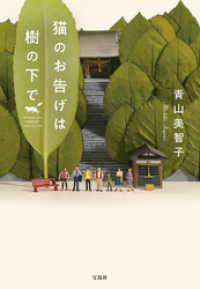
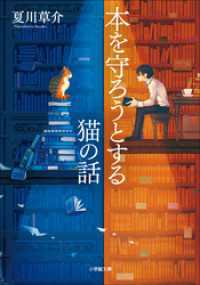
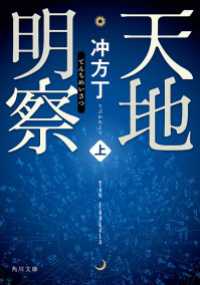
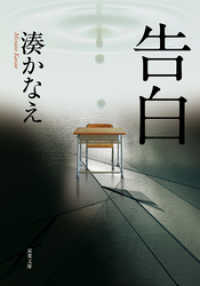


コメント