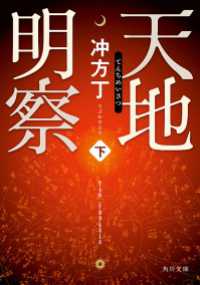
『天地明察(下)』は、上巻で芽生えたワクワクが、一気に「胸が熱くなる物語」へとスケールアップしていく後編でした。碁打ちの名門に生まれた渋川春海が、ついに改暦事業の総大将として前面に立ち、二十年という長い年月をかけて天と向き合っていきます。その道のりは想像以上に険しく、読みながら何度も心を揺さぶられました。 特に印象的だったのは、この物語が「一人の天才の物語」ではなく、「多くの人の志が重なり合って成し遂げられた物語」として描かれている点でした。保科正之や水戸公、酒井や堀田といった重臣たち、和算の関孝和や囲碁の本因坊、そして春海のそばに寄り添うえん。さまざまな立場の人たちが、それぞれのやり方で春海を支えていく姿が、静かな感動として胸に積もっていきました。 読み終えたときには、単に「良い歴史小説を読んだ」という満足感だけでなく、自分自身も少しだけ前向きに生きてみたくなるような、不思議な勇気をもらえた気がしました。
【書誌情報】
| タイトル | 角川文庫 天地明察 下 |
|---|---|
| 著者 | 冲方丁 |
| 出版社 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2014/12 |
| ジャンル | 歴史・時代小説 |
| ISBN | 9784041002926 |
| 価格 | ¥594 |
「この国の老いた暦を斬ってくれぬか」会津藩藩主にして将軍家綱の後見人、保科正之から春海に告げられた重き言葉。武家と公家、士と農、そして天と地を強靭な絆で結ぶこの改暦事業は、文治国家として日本が変革を遂げる象徴でもあった。改暦の「総大将」に任じられた春海だが、ここから想像を絶する苦闘の道が始まることになる――。碁打ちにして暦法家・渋川春海の20年に亘る奮闘・挫折・喜び、そして恋!! ※本書は2012年5月に発売された角川文庫版『天地明察』を底本に電子書籍化したものです。
本の概要(事実の説明)
本作は、徳川四代将軍家綱の時代に行われた改暦事業を題材にした歴史小説です。上巻では、碁打ち衆として暮らしていた春海が和算や天文に魅了され、その世界に足を踏み入れるまでが描かれました。下巻ではいよいよ、春海が改暦の総大将として日本独自の暦を作り上げる「本番」の時間が始まります。 物語は、春海の約二十年にわたる挑戦を追いながら進んでいきます。観測と計算の積み重ねによる試行錯誤、度重なる失敗と批判、支えてくれた人たちとの別れ、そして先人たちから託された志。「頼みましたよ」「頼まれました」という言葉のリレーが、そのまま物語の芯になっているように感じました。 歴史的な出来事を扱いながらも、文体は淡々としていて読みやすく、必要以上に難しい専門用語に寄りかからないのがありがたかったです。和算や暦法に馴染みがない私でも、登場人物たちの会話や感情を通して、自然とテーマに近づいていける構成だと思いました。歴史小説が苦手な人や、理系分野を敬遠しがちな人にも、手に取ってみてほしい一冊だと感じました。
印象に残った部分・面白かった点
下巻で最も心に残ったのは、春海が「一人では到底抱えきれないほどの思い」を背負いながらも、決して投げ出さずに歩み続ける姿でした。親しい人の死や、理不尽な中傷、政治的な駆け引き。そうした重圧を前にしても、春海は逃げる代わりに、ただひたすら「暦」と向き合い続けます。その姿がとても眩しく見えました。 また、「士気凛然、勇気百倍」という言葉も強く印象に残りました。これは単なる勇ましいスローガンではなく、幾度もの挫折と失敗を経た末に、それでも前を向こうとする人間の姿勢を象徴しているように感じました。読みながら、こんなふうに自分の仕事や日々の課題と向き合えたらいいな、と素直に思いました。 えんとの再会と関係の深まりも、物語を支える大きな要素でした。お互いに大切な人を失った後にもう一度出会い、静かに寄り添いながら春海を支えるえんの姿には、派手さはないものの、深い安心感がありました。改暦という大事業の陰で、こうした日常の温もりが丁寧に描かれていることも、本作の魅力だと感じました。
本をどう解釈したか
『天地明察(下)』は、単に「暦の物語」ではなく、「時間をどう信じるか」というテーマを描いた作品だと感じました。暦とは、昨日が今日になり、今日が明日へと続いていくことを信じるための仕組みです。その確信を支えるために、春海たちは星を見上げ、数式と格闘し、地道な観測を積み重ねていきます。 その姿は、現代の私たちが日々カレンダーに予定を書き込み、「その日がちゃんと来る」と信じて生きていることと重なって見えました。暦を作るという行為は、結局のところ「人が未来を信じるための土台をつくること」なのだと感じました。 そしてこの物語は、志がどのように受け継がれていくかも静かに描いています。建部や伊藤、安藤や保科たちの思いが、「頼みましたよ」「頼まれました」という短い言葉に凝縮され、それを春海が引き受け、さらに次の世代へと渡していく。その流れは、歴史を動かしていくのは結局、名も知られない多くの人の積み重ねなのだという事実を優しく教えてくれるようでした。
読後に考えたこと・自分への影響
読了後、私が強く感じたのは、「大きな仕事は一気に成し遂げられるものではなく、長い時間と多くの人の力で少しずつ形になっていく」という当たり前のことでした。それでも、その当たり前を物語の形でここまで丁寧に見せてくれる作品は、そう多くないように思います。 春海は、決して完璧な天才ではありません。頼りなかった青年が、幾度もの挫折と別れを経て、それでも逃げずに「頼まれた仕事」に向き合い続ける。その姿に触れることで、自分の目の前にある仕事や役割に、もう少し真摯に向き合ってみようかなという気持ちが生まれました。 また、何かを成し遂げるとき、「自分のため」だけでは心が折れてしまう場面が必ず来るのだと感じました。そのとき背中を押してくれるのは、自分を信じてくれた人の言葉や、託された思いなのかもしれません。春海が多くの人の志を引き受けて改暦をやり遂げたように、私もまた、誰かの期待に応える形で力を出せる瞬間があるかもしれないと、静かに希望をもらいました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この作品は、夜の静かな時間帯にじっくりと読むのがよく合うと感じました。外の音が遠のき、自分の呼吸とページをめくる音だけが聞こえるような夜に、春海たちが見上げた星空を思い浮かべながら読むと、改暦に挑む彼らの時間と自分の時間が、少しだけ重なったような不思議な感覚があります。 また、予定のない静かな休日に、上巻と合わせてゆっくり読み進めるのもおすすめです。日常の喧騒から少し距離を置き、江戸の人々の息遣いや、天を相手にした長い仕事の時間に浸っていると、自分の生活のリズムまで少し整ってくるように思えました。焦りを抱えているときや、今の仕事や生活に迷いがあるときにこそ、落ち着いた気持ちで開きたい一冊だと感じました。
『天地明察(下)』(冲方丁・著)レビューまとめ
『天地明察(下)』は、日本独自の暦作りという大事業の裏側で、一人の人間が多くの志を引き受けながら成長していく姿を描いた物語でした。淡々とした筆致の中に、死と挫折、友情と愛情、そして「精進せよ」「頼みましたよ」という言葉に込められた重みが静かに響きます。読み終えたあと、私もまた自分の持ち場で少しだけ粘ってみようと思える、清々しい余韻の残る一冊でした。
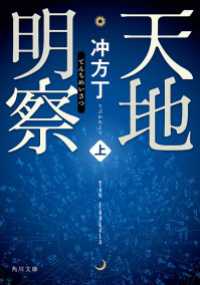

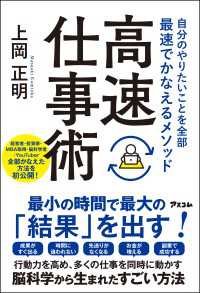
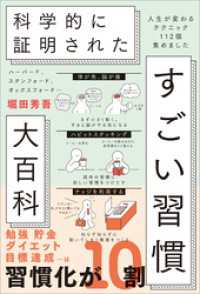
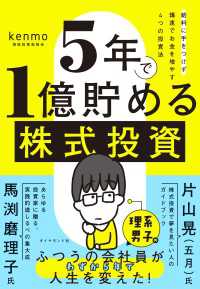
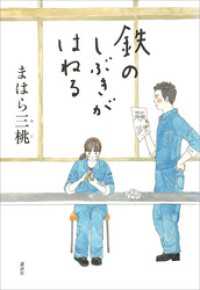

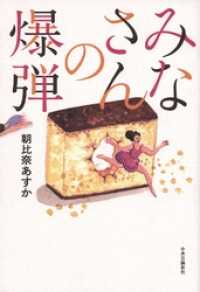
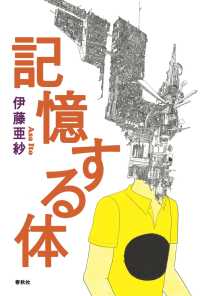


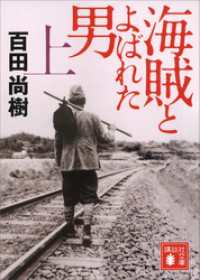

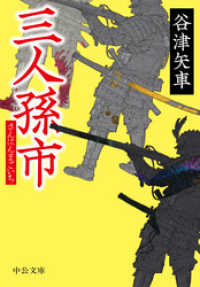
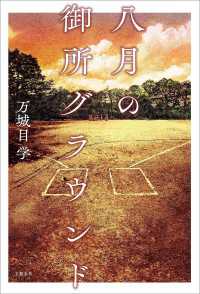
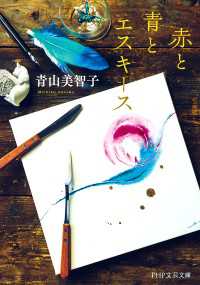
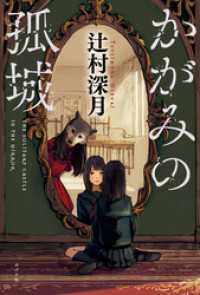
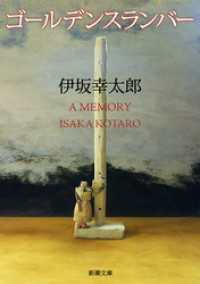


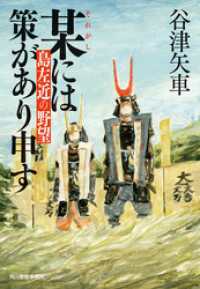
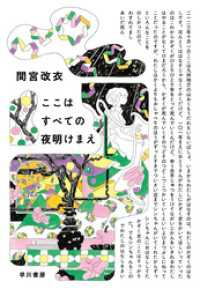

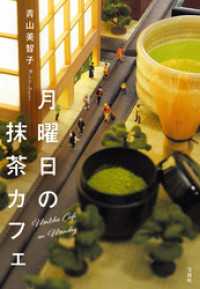
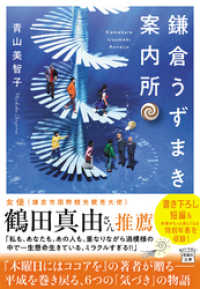


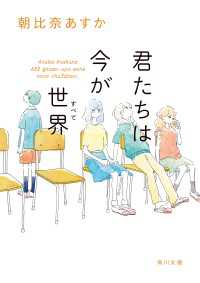

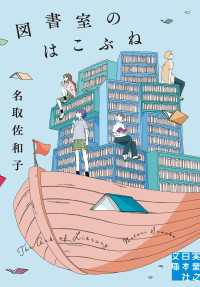
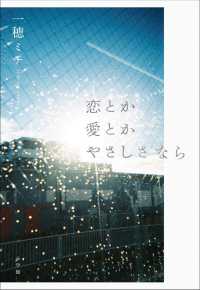
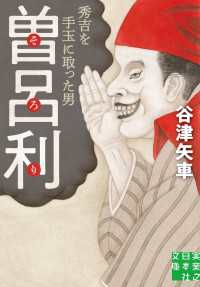
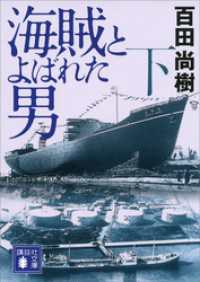


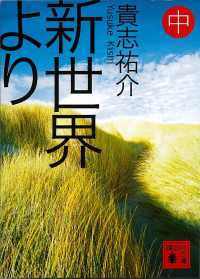
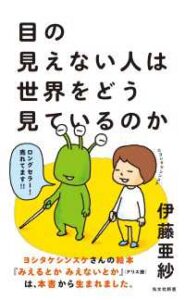
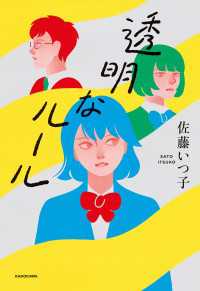
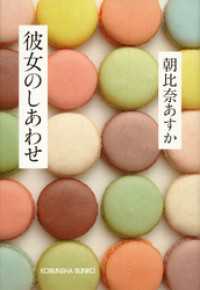


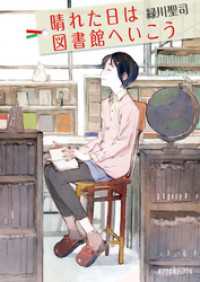
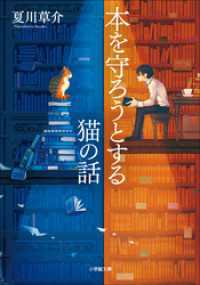

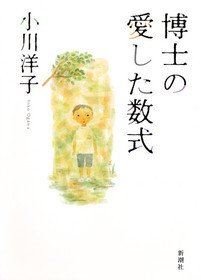
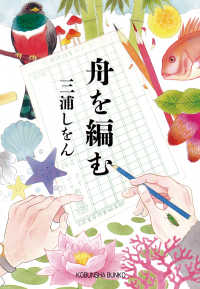



コメント