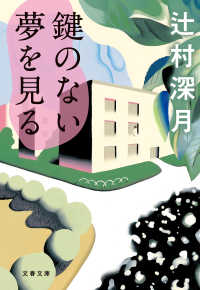
『鍵のない夢を見る』を読み終えたとき、まず出てきた言葉は「しんどいのに、すごく分かる」でした。ページ数としては決して分厚い本ではないのに、一気読みするには重く、でも途中で閉じてしまうこともできない、不思議な引力を持った短編集だと感じました。 どの物語にも登場するのは、地方のどこにでもいそうな女性たちです。仕事をしたり、恋愛をしたり、結婚や妊娠、子育てに向き合ったりしながら暮らしている「普通」の人たちなのに、気づけば泥棒や放火、逃亡、殺人、誘拐といった犯罪に足を踏み入れてしまう。その過程があまりにリアルで、読んでいて何度も胸がヒリヒリしました。 特に「石蕗南地区の放火」で描かれる笙子の勘違いと自意識には、読者として「いや、それは違うよ」と突っ込みたくなりつつも、どこか自分の中にも同じ種類の痛々しさがあるように思えて、目をそらしたくなりました。読後にすっきり爽快、というタイプの本ではありませんが、自分の中の小さな「闇」にそっと光を当てられたような、忘れがたい体験になりました。
【書誌情報】
| タイトル | 文春文庫 鍵のない夢を見る |
|---|---|
| 著者 | 辻村深月 |
| 出版社 | 文藝春秋 |
| 発売日 | 2015/07 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784167903985 |
| 価格 | ¥550 |
【ご購入者様限定・著者メッセージ画像プレゼント!(配布期間2025/11/1~11/30)】望むことは、罪ですか? 誰もが顔見知りの小さな町で盗みを繰り返す友達のお母さん、結婚をせっつく田舎体質にうんざりしている女の周囲で続くボヤ、出会い系サイトで知り合ったDV男との逃避行──。普通の町に生きるありふれた人々に、ふと魔が差す瞬間、転がり落ちる奈落を見事にとらえる五篇。現代の地方の閉塞感を背景に、五人の女がささやかな夢を叶える鍵を求めてもがく様を、時に突き放し、時にそっと寄り添い描き出す。著者の巧みな筆が光る傑作。第147回直木賞受賞作!
本の概要(事実の説明)
この作品は、五つの短編からなる直木賞受賞作です。それぞれ「仁志野町の泥棒」「石蕗南地区の放火」「美弥谷団地の逃亡者」「芹葉大学の夢と殺人」「君本家の誘拐」というタイトルが付けられており、その言葉通り、泥棒や放火、逃亡、殺人、誘拐といった行為が物語の核に据えられています。とはいえ、ジャンルとしてはいわゆる犯人当てのミステリーではなく、人の心が日常の中で少しずつ傾いていく過程を描いた心理ドラマだと感じました。 印象的なのは、登場人物たちが決して「特別な悪人」ではないことです。ちょっと自意識が強かったり、パートナーに甘えてしまったり、育児に追い詰められていたりと、どこかで見かけたことのあるような女性たちばかりです。そんな彼女たちが、ふとした一言や小さな不満、見栄や焦りをきっかけに、一線を越えてしまう。読んでいると「自分だったら絶対にしない」と言い切りたい一方で、ほんの少し条件が違っていたら分からないかもしれない、とぞっとするような感覚にも襲われました。 全体としては、女性の視点から見た地方都市の空気感が濃く描かれていて、日常と犯罪の距離の近さに驚かされます。軽快に読み飛ばせるタイプの短編集ではありませんが、人間の内側に潜む「ずれ」や「欲望」をじっくり味わいたい読者には、強く響く一冊だと思いました。
印象に残った部分・面白かった点
特に印象に残ったのは、「石蕗南地区の放火」と「君本家の誘拐」です。前者では、笙子という女性の自意識が物語を引っ張っていきます。彼女は自分を「ちゃんとしている側」だと信じていますが、その視線にはどこか優越感が混じり、周囲の人間を見下すような響きがにじんでいます。そのズレた正義感が、やがて取り返しのつかない方向へ転がっていくのを見ていると、心の中で何度もブレーキをかけたくなりました。彼女が最後まで勘違いに気づかないまま生きていきそうだと感じたとき、妙な切なさと怖さが同時に湧き上がりました。 「君本家の誘拐」は、育児に追い詰められた母親の視点が胸に迫ってきます。寝不足と疲労でボロボロになりながら、協力的とは言えない夫や周囲の期待と向き合う日々。自分の人生をコントロールできない感覚や、「良い母親」でいなければというプレッシャーが積み重なり、現実感が少しずつ薄れていく描写は、読んでいて何度も息苦しくなりました。そんな状態のなかで、後戻りできない一歩を踏み出してしまう怖さは、決して他人事ではないように感じました。 どの短編にも、「絶妙に嫌な人間」が登場します。最低な男たち、ズレた正義感を振りかざす女性、自分の欲望を正当化してしまう人。彼らの言動にはイライラさせられますが、その一方で「こういう人、現実にもいるよな」と納得してしまうリアリティがありました。その生々しさが、短編集全体の読後感を重くしながらも、強烈な印象を残しているのだと思います。
本をどう解釈したか
この本を読んでいて強く感じたのは、「鍵のない夢」というタイトルの意味です。五つの物語に登場する女性たちは、それぞれが自分なりの夢や理想を抱いています。素敵な恋人との未来や、安定した結婚生活、社会から認められたいという願望、ちゃんとした母親になりたいという思い。そのどれもが、一見するととても普通で、誰もが抱きそうな願いに見えます。 ただ、その夢には「鍵」がかかっていないのだと感じました。外側から簡単に揺さぶられ、他人の言葉や視線、世間の価値観に勝手に開け閉めされてしまうような、危うい夢です。自分の内側からしっかり形作ったものというより、周囲の期待や比較のなかで膨らんでしまった“借り物の夢”に近いのかもしれません。だからこそ、少し歯車が狂ったとき、一気に崩れ落ちて犯罪という形で表に出てしまう。その構造が、五つの物語を通して浮かび上がっているように思えました。 また、この短編集には「女の歪み」と同時に、「男のだらしなさ」や「社会の鈍感さ」も描かれていると感じました。最低な男たちに対する苛立ちを読者が共有しつつも、そこにだけ責任を押しつけて終わらせないのが辻村作品らしいところです。自意識の強さや、正義感の暴走、承認欲求といった要素が複雑に絡まり合い、「自分はまともだ」と思っている人ほど危ういのかもしれない、というメッセージを受け取ったように思いました。
読後に考えたこと・自分への影響
読後に一番強く残ったのは、「自分は大丈夫」と信じたい気持ちを少し疑ってみたほうがいい、という感覚でした。五つの物語の登場人物たちは、それぞれに歪んだ部分を抱えていますが、最初から極端におかしな人ばかりではありません。どの女性も、ほんの少し視野が狭くなっていたり、ちょっとだけ自分を良く見せようとしていたりするだけです。その積み重ねが、気づけば取り返しのつかないところまで自分を追い込んでしまう。そこが一番怖く、そして一番身近に感じたところでした。 同時に、「人は誰でも鍵のない夢を見ることがある」という指摘を突きつけられたようにも思います。たとえば恋人やパートナーに対する期待、子育てに対する理想、自分の正しさへのこだわり。どれも少し間違えば、自分自身を縛りつける鎖にもなり得ます。だからこそ、自分の感情がとても正しいものに思えて熱くなっているときほど、「これは本当に自分の言葉だろうか」と一歩引いて考えてみたいと感じました。 この短編集は、読んでいて爽やかになれるタイプの本ではありませんが、心のどこかに残っていたモヤモヤした感情に名前を与えてくれるような、そんな力を持っていると感じました。少ししんどいけれど、読んだことを後悔しない本、という読者の感想にもとても共感しました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
『鍵のない夢を見る』は、静かな夜に一人で向き合いたい一冊だと感じました。仕事や家事がひと段落して、家の中がようやく落ち着いた時間帯に、温かい飲み物を片手にページを開くと、短編ごとの重さや余韻をじっくり味わいやすいと思います。一気に読み切るのも可能ですが、それぞれの物語のあとに少し間を置いて、自分の感情を確かめながら読むほうが、この本とは相性が良いように感じました。 また、自分の中のモヤモヤと向き合いたいときにもおすすめです。日々の生活のなかで、ふとした瞬間に感じる嫉妬や劣等感、正義感といった感情は、表に出さないまま飲み込んでしまうことが多いと思います。この短編集を読みながら、その感情を少しだけ掘り起こして眺めてみる時間を持つと、自分自身の「鍵のない夢」の存在にも気づけるかもしれません。
『鍵のない夢を見る』(辻村深月・著)レビューまとめ
『鍵のない夢を見る』は、どこにでもいそうな女性たちが、少しずつ現実から踏み外れていく瞬間を描いた、痛くてこわくて、でも目を離せない短編集でした。自分は果たして“枠の外”にいるのか、とそっと問いかけてくるような一冊だと感じました。
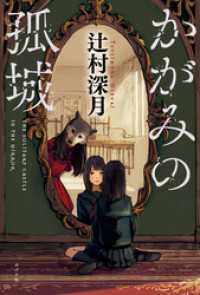
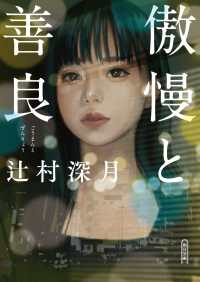
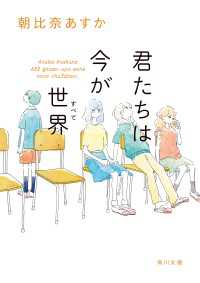


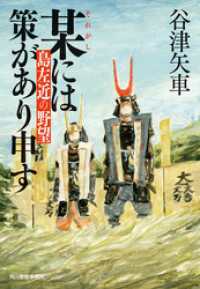
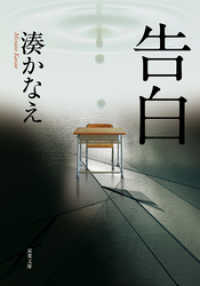


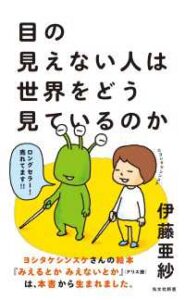
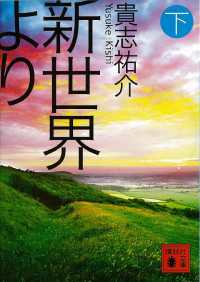

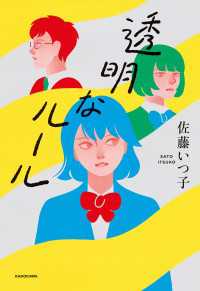


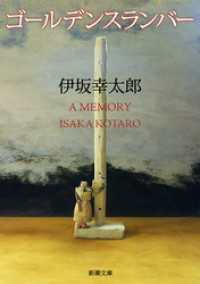
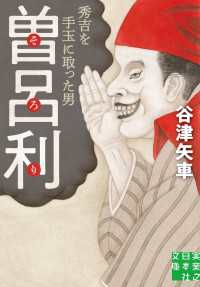


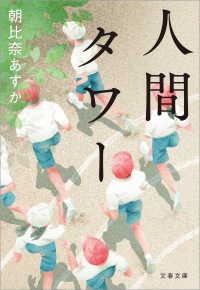
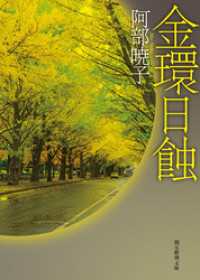
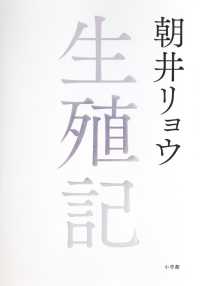
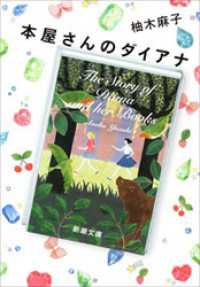

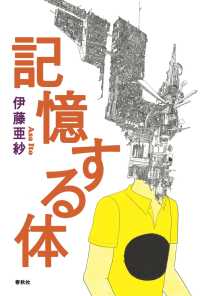
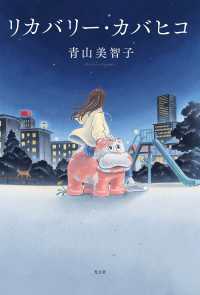
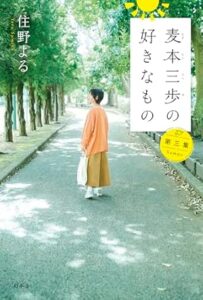
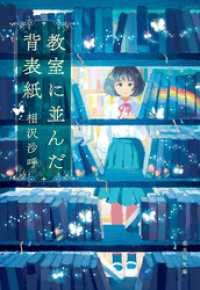




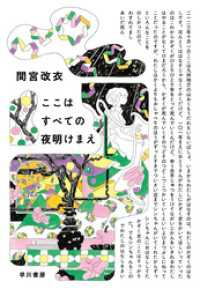
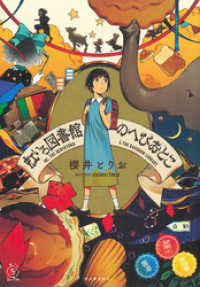
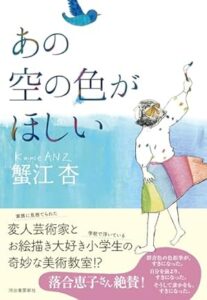
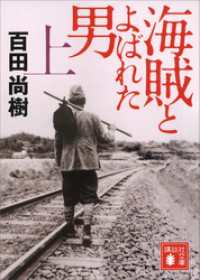

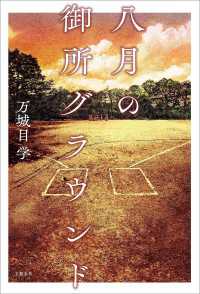

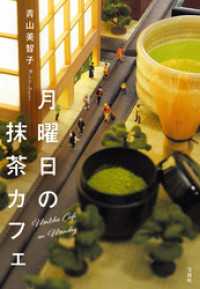
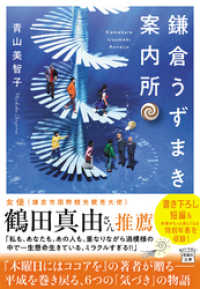

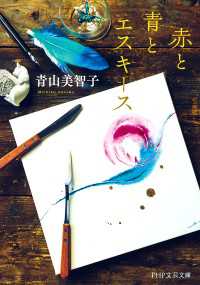
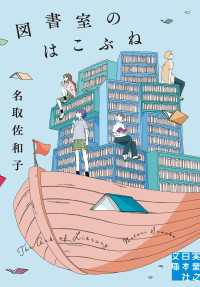

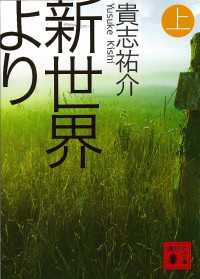
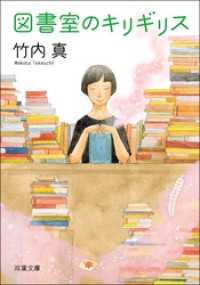
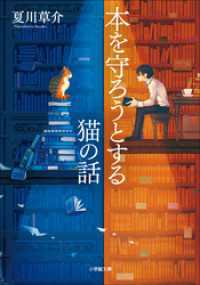
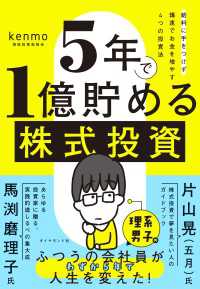
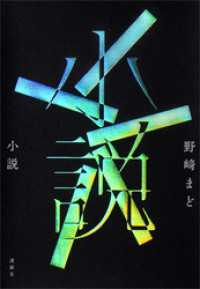
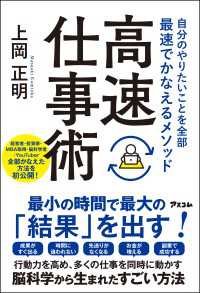
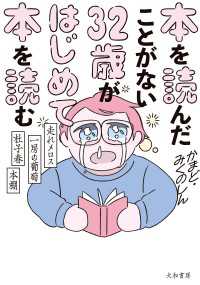
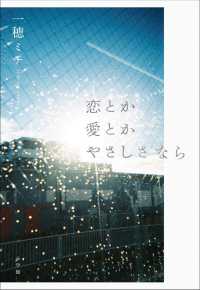
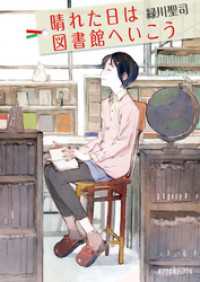


コメント