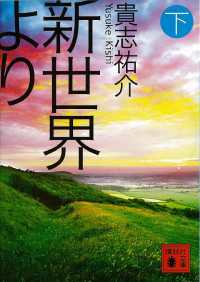
『新世界より(下)』は、上中巻で積み上げられてきた違和感や伏線が、一気に決壊するように回収されていく巻でした。読みながら、まさにページをめくる手が止まらないとはこのことだな、と何度も感じました。バケネズミとの全面戦争、悪鬼の出現、人間社会の崩壊の危機。その一つひとつの場面に、息が詰まるほどの緊張感がありました。 特に、スクィーラが裁かれる場面で放つ「私たちは人間だ」という言葉には、正直、胸を殴られたような衝撃がありました。ここまでずっと“醜く下等な存在”として描かれてきたバケネズミが、実は人間に改造された存在だったと分かった瞬間、それまで自分が無意識に彼らをどう見ていたかも含めて、価値観がひっくり返るような感覚になりました。 序盤で世界観の説明の多さに少し挫折しかけたことを思い出しながら、最後まで読んで本当に良かったとしみじみ感じました。ここまで徹底して「人間の恐ろしさ」と「知性の残酷さ」を描き切る物語は、なかなか出会えないと思います。
【書誌情報】
| タイトル | 講談社文庫 新世界より(下) |
|---|---|
| 著者 | 貴志祐介【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2015/03 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784062768559 |
| 価格 | ¥990 |
夏祭りの夜に起きた大殺戮。悲鳴と嗚咽に包まれた町を後にして、選ばれし者は目的の地へと急ぐ。それが何よりも残酷であろうとも、真実に近付くために。流血で塗り固められた大地の上でもなお、人類は生き抜かなければならない。構想30年、想像力の限りを尽くして描かれた五感と魂を揺さぶる記念碑的大傑作! PLAYBOYミステリー大賞2008年 第1位、ベストSF2008(国内篇) (講談社文庫)
本の概要(事実の説明)
下巻では、夏祭りをきっかけに始まったバケネズミの反乱が本格的な戦争へと発展し、物語はクライマックスに突入します。大人になった早季と覚は、かつて彼らを救ってくれた野孤丸や、奇狼丸、不気味な図書館端末であるニセミノシロモドキと共に、人類を滅ぼしかねない悪鬼に立ち向かうことになります。 戦闘シーンはひたすら苛烈で、悪鬼から身を隠しているときの静かな恐怖や、地下世界で未知の生物に追われる場面など、どこを切り取っても緊張の糸が張り詰めていました。中巻までで築かれてきた世界設定や歴史の断片が、ここで一気に意味を持ちはじめ、バケネズミの正体や人類がたどってきた過去が明かされていきます。 ただのバトルものでも、単純な勧善懲悪の物語でもなく、ここまで読んできたからこそ味わえる重さと深みがありました。ファンタジーやSFが好きな読者だけでなく、「人間とは何か」を考える物語が好きな人にもおすすめしたい一冊だと感じました。
印象に残った部分・面白かった点
印象に残った場面は数えきれないのですが、まず思い出されるのは戦争シーンの圧倒的な緊迫感です。悪鬼に追われながら、わずかな隙間に身を潜めてやり過ごそうとする場面では、自分まで呼吸が浅くなっていくのを感じました。どこにいても見つかれば一瞬で殺されるという状況が続き、ページをめくるたびに心拍数が上がっていくようでした。 そして、スクィーラの裁判は、物語全体の印象を決定づけるクライマックスの一つだと感じました。これまで奸智に長けた“敵役”として描かれてきた存在が、拷問にかけられながらも「私たちは人間だ」と叫ぶ姿には、恐怖と同時に強い共感すら覚えました。彼の行動を完全に肯定することはできないものの、奴隷として扱われ、常に命を握られてきた側の視点を突きつけられたようで、胸の奥がざらつくような違和感と痛みが残りました。 一方で、奇狼丸の生き様も強く印象に残りました。伝統と誇りを重んじる彼は、最後まで“武人”として振る舞い、その決断と最期には静かな美しささえ感じました。スクィーラと奇狼丸という対照的な二人のバケネズミが、どちらも人間以上に“人間らしい”と感じられたのは、この物語ならではの妙味だと思います。
本をどう解釈したか
下巻を読みながら強く感じたのは、「人間とは何か」「どこまでを人間とみなすのか」という問いが、物語の中心に据えられているということでした。呪力を持つ人間たちは、自分たちを“神に近い存在”のように位置づけ、その特権を守るために、呪力を持たない人間に動物の遺伝子を組み込んでバケネズミとして支配してきました。この構図を知ったとき、私自身も彼らの傲慢さに対して強い嫌悪感を覚えました。 スクィーラの反乱は、単なるモンスターの蜂起ではなく、奴隷として扱われた側の「当たり前の反発」とも読めます。彼のやり方は過激で、多くの犠牲を生んだことは確かですが、それでも「彼らにもそうする理由があったのではないか」と考えさせられる描き方がされていました。 また、攻撃抑制や愧死機構といった仕組みは、一見すると戦争を防ぐための“平和装置”のようにも見えますが、実際には人を徹底的にコントロールするための鎖でもあります。自分たちが作り上げた仕組みによって、さらに大きな悲劇を招いてしまう人間の姿には、文明や技術を手にした私たち自身の危うさが重なって見えました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えたあと、まず浮かんだのは「身の丈に合わない力を持つことの怖さ」でした。呪力という圧倒的な力を手にした人間たちは、最初こそそれを使いこなしているつもりでいても、長い時間の中で結局、自分たちの恐怖と支配欲に負けていったように思えました。その帰結としてのバケネズミの存在は、まさに人類の罪の結晶のようでした。 また、誰かを“人間ではないもの”として扱った瞬間に、どこまでも残酷になれてしまうという構造にも、強い警告を感じました。作中の人間たちがバケネズミを獣や奴隷としか見てこなかったように、現実の世界でも、ラベル一つで人を上下に分けてしまう場面は少なくありません。自分自身も知らないうちに誰かを“下に見ていないか”と、ふと立ち止まって考えさせられました。 さらに、スクィーラに向かって「犠牲になった人間に謝って」と言ってしまう早季の言葉にも、複雑な感情を覚えました。早季は人間社会の中で生きてきた登場人物なので、その反応はとても自然に思えますが、読者としては、そこに人間側のエゴや限界が滲んでいるようにも感じました。その“どうしようもなさ”も含めて、物語の余韻になっているのだと思います。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この下巻は、静かな環境でじっくり向き合いたい物語だと感じました。できれば夜、家の中が少し落ち着いた時間帯に、スマホやテレビから離れて読み進めるのがおすすめです。暗い部屋でスタンドライトだけをつけ、外の音が遠くに感じられるような状況で読むと、物語世界の緊張感と孤独感がより濃く染み込んできます。 また、自分の心と向き合いたいときにも向いている一冊だと思いました。読みながらどうしても“人間側”に感情移入してしまう瞬間もあれば、バケネズミ側の理屈にうなずいてしまう場面もあり、その揺れ動きこそがこの作品の魅力です。読み終わったあとに少し時間をとって、自分がどこに共感し、どこに違和感を覚えたのかを振り返ると、より深く味わえると感じました。
『新世界より(下)』(貴志祐介・著)レビューまとめ
『新世界より(下)』は、怒涛の展開で読者を最後まで走らせながら、「人間であることの重さ」と「知性の残酷さ」を容赦なく突きつけてくる完結編でした。読み終えたあとに残るのは単純なカタルシスではなく、暗い余韻と、それでも考え続けたくなる問いの数々です。時間をかけてでも、最後までたどり着いて良かったと心から思える物語でした。
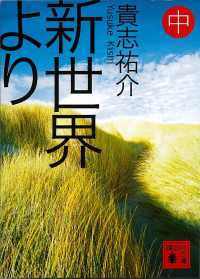
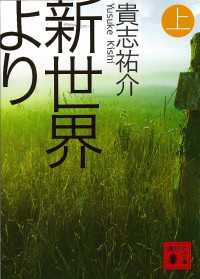


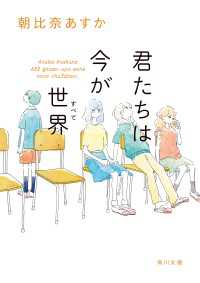

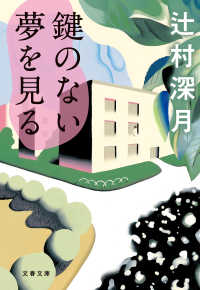
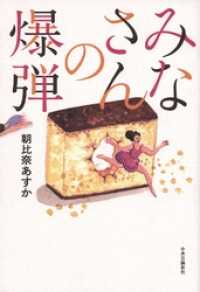
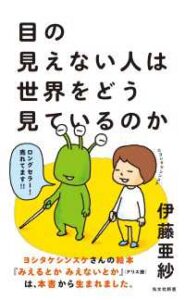


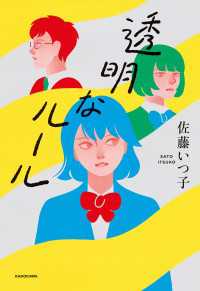
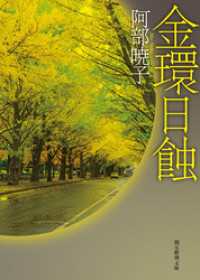
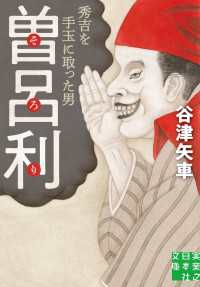
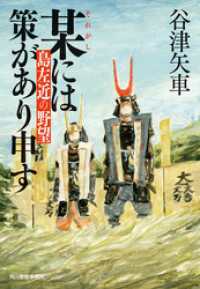


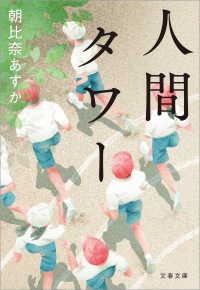
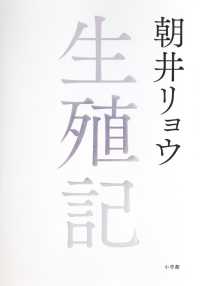
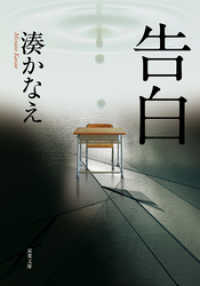



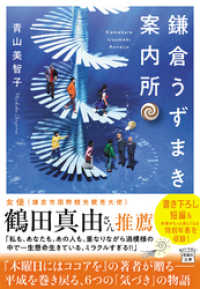


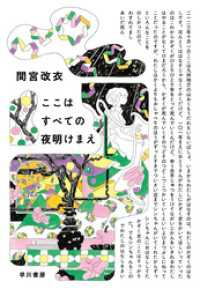
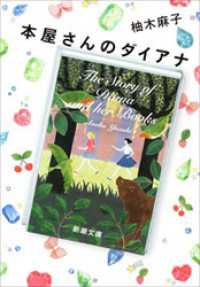
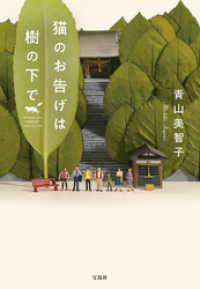


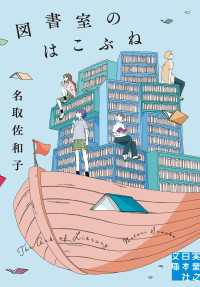
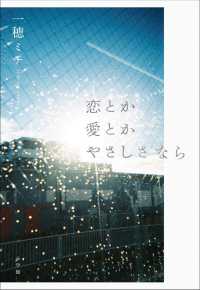

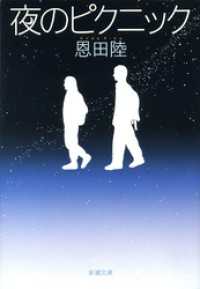
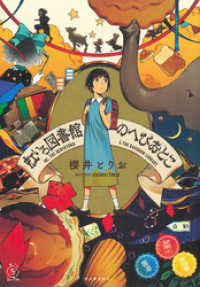
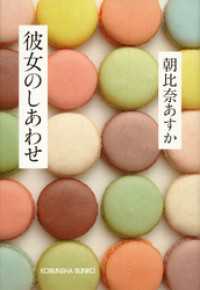
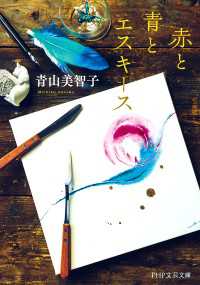
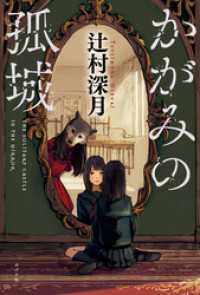
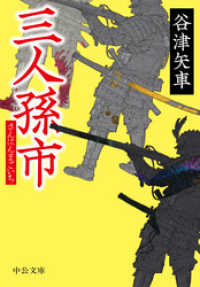
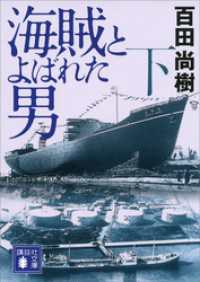

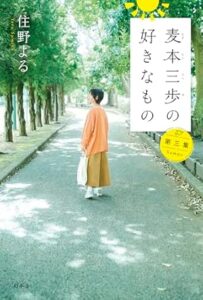
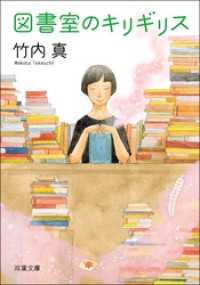
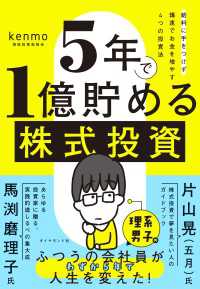
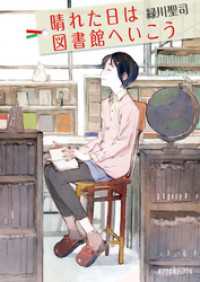
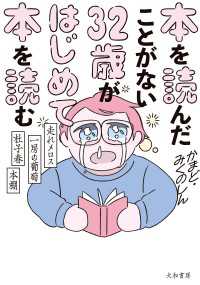
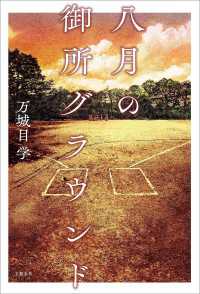
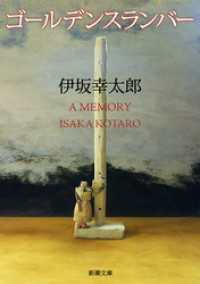
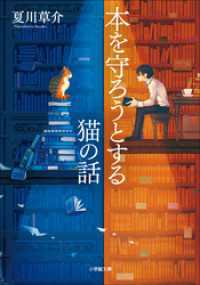




コメント