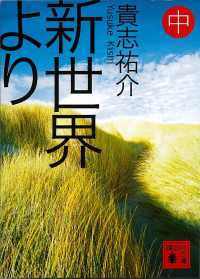
『新世界より(中)』は、上巻で提示された不穏な空気が、いよいよ確かな“事実”として姿を現していく巻だと感じました。文明が崩壊した千年後の日本で、呪力という強大な力を持つ人間たちが築いた社会の本質が、早季と仲間たちの視点を通して少しずつ剥がれ落ちていきます。 読み始めた最初の数章は、どこか懐かしさのある世界観の中に潜む違和感が、ようやく言語化されていく過程に胸がざわつきました。呪力という力によって守られてきたように思えた社会が、実は“子どもたちを徹底的に管理し、淘汰することでしか維持できなかった世界”だと明らかになっていく。読んでいて、背筋が冷えるような感覚がありました。 なにより、上巻で一緒に成長してきた仲間たちが、目の前から“失われていく”衝撃が大きかったです。記憶ごと消されることの理不尽さ、その不可逆性の重さがじわじわと胸に広がり、読み進めるほどにつらさが増していきました。
【書誌情報】
| タイトル | 講談社文庫 新世界より(中) |
|---|---|
| 著者 | 貴志祐介【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2015/03 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784062768542 |
| 価格 | ¥880 |
町の外に出てはならない――禁を犯した子どもたちに倫理委員会の手が伸びる。記憶を操り、危険な兆候を見せた子どもを排除することで実現した見せかけの安定。外界で繁栄するグロテスクな生物の正体と、空恐ろしい伝説の真意が明らかにされるとき、「神の力」が孕(はら)む底なしの暗黒が暴れ狂いだそうとしていた。(講談社文庫)
本の概要(事実の説明)
本作は千年後の日本を舞台としたディストピアSFで、人間たちは“呪力”と呼ばれる超能力を用いて暮らしています。しかし、その力はあまりにも強大であるため、社会は子どもを厳しく選別し、ときには排除することで安定を保っていました。物語は、渡辺早季の手記という形式で語られ、彼女の12歳からの体験が時系列に沿って進んでいきます。 中巻では、上巻で少しずつ見えてきた社会の歪みが本格的に明らかになります。町の外に出てはならないという禁を破ったことで、倫理委員会が子どもたちに介入し、記憶の操作や強制的な処分といった、これまで遠い存在だった仕組みが生々しく描かれます。 呪力を持つことが祝福ではなく“管理される側の証”であることに気づいたとき、物語の見え方が大きく変わりました。誰もがただ平穏に生きていただけなのに、その裏では恐怖と排除のシステムが動いていたのだと思うと、胸が締め付けられました。
印象に残った部分・面白かった点
もっとも印象に残ったのは、瞬の存在が物語全体を覆う不穏さの象徴として描かれていく点でした。彼が“業魔”と判断され、姿を消したあとの描写が特につらく、記憶から彼の存在が消されていく過程は、あまりにも静かで残酷だと感じました。 瞬が本当に業魔になってしまったのか、あるいは“そう判断されただけなのか”は作中で明確には語られず、だからこそ読者に大きな余韻を残します。早季たちの中にあったはずの思い出が、触れた瞬間に霧のように消えていく描写は、記憶の価値や、人が人であるための核のようなものを揺さぶりました。 また、真理亜と守が町から姿を消す展開も胸に迫りました。成績不振を理由に“処分されかける”守が逃げ、彼を追いかけた真理亜も町に戻らず自分たちの未来を選ぶ姿には、彼らなりの必死の選択があったのだと感じました。ふたりが残した手紙の言葉に、切実さと諦めと覚悟が混ざり合っていて、胸が熱くなると同時にとても悲しかったです。
本をどう解釈したか
読んでいて強く感じたのは、この作品が“力を得た人間がたどりうる未来”について非常にシビアな視点を持って描いているということでした。呪力という強大な能力を得たことで、人間はより豊かになったのではなく、むしろ自らを追い詰める社会を作り上げてしまったのだと思えてきます。 瞬や真理亜、守といった子どもたちは、単純に社会に適応できなかった弱者ではなく、むしろ“社会が彼らを排除するしかない仕組みになっていた”と考える方がしっくりきました。力を持つ者は危険で、危険を回避するためには徹底的に管理しなければならず、その管理が過剰になるほど自由が消える。その矛盾が物語全体に濃く影を落としているように思えました。 倫理委員会や教育委員会の描写にも、人間が恐怖を理由に合理性を正当化しようとする姿が強く表れていました。未来の日本という設定でありながら、一歩間違えば現代にも通じる構造があることに思い至ると、この世界は決して遠い存在ではないのだと気づかされます。
読後に考えたこと・自分への影響
中巻を読み終えて、私は「安定した社会とは何か」という問いが頭から離れませんでした。人々が平和に暮らすために必要なものが、自由や個の尊厳を犠牲にしてまで維持すべきものなのかどうか。それを判断する基準そのものが、時代や状況によって簡単に変わりうることに怖さを感じました。 また、仲間を失った早季たちの姿に触れ、記憶とはどれほど大切なものなのか、そしてその記憶が奪われることがどれほど残酷なのかを改めて考えさせられました。物語の描写を通して、思い出の価値や、人と人とのつながりがどんなに脆いものかを痛感しました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この巻は、落ち着いた環境でじっくり読みたい物語だと感じました。夜の静けさが満ちる時間にページを開くと、物語の不穏な空気や緊張感がいっそう濃く伝わり、早季たちと同じ視線で世界に入り込めるような没入感がありました。静かな休日にゆっくり読み進めるのも向いていて、自分のペースで深いテーマを咀嚼しながら物語を追うことができる気がします。
『新世界より(中)』(貴志祐介・著)レビューまとめ
中巻は『新世界より』の核心部分に踏み込み、早季たちの成長と喪失の物語が一気に加速します。管理社会の冷たさ、自分たちの力への問い、仲間の行方など、重いテーマが折り重なっていましたが、そのぶん読み応えは抜群でした。下巻でどんな結末が待ち受けているのか、胸の高鳴りと不安を抱えたまま次の巻へ進みたいと感じました。
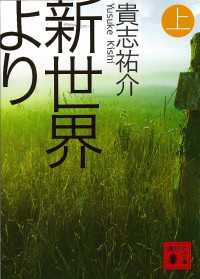
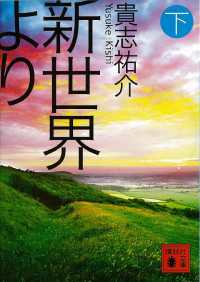
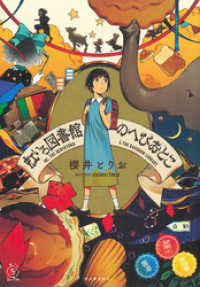
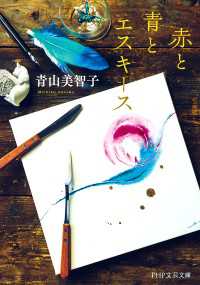

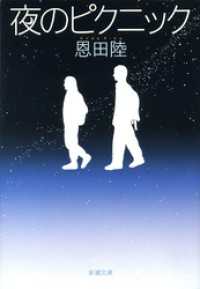

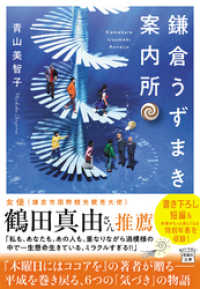

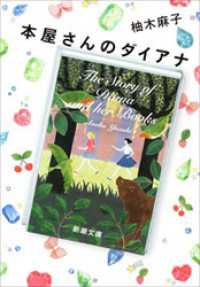
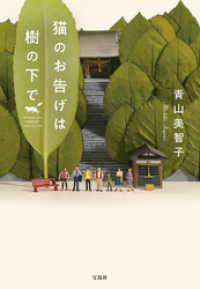
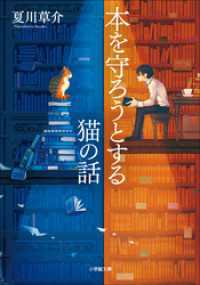
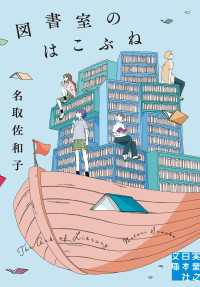
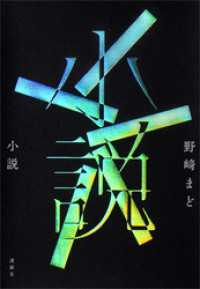
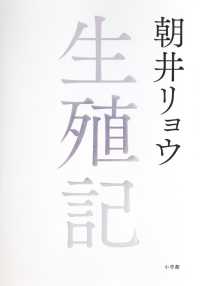

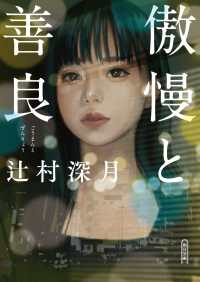
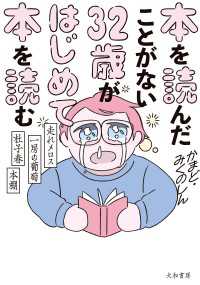
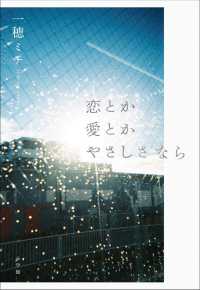
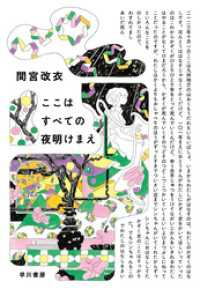
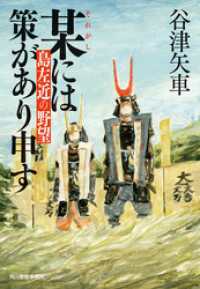


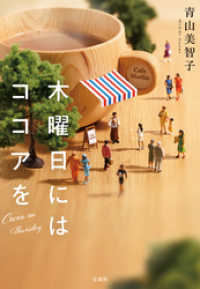
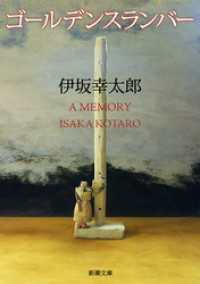
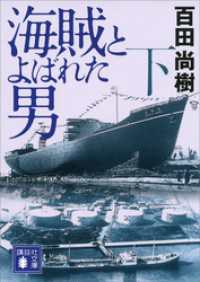

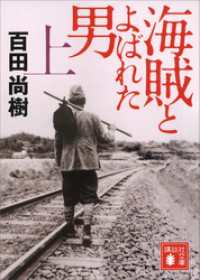

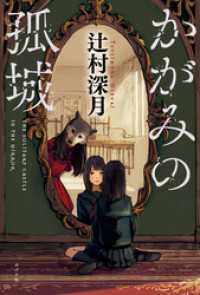
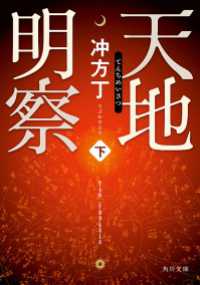
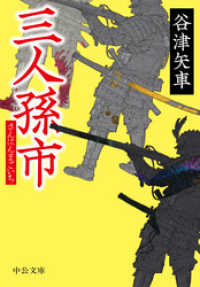
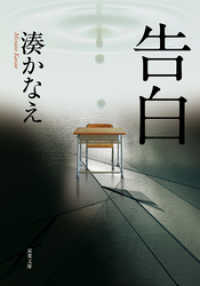



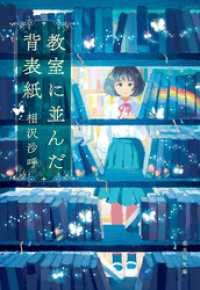


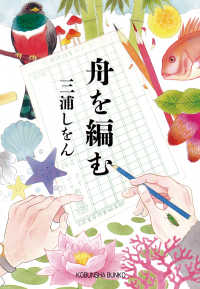

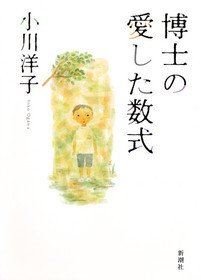
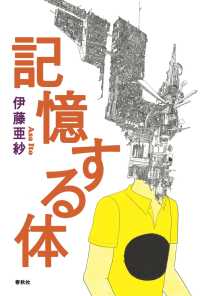
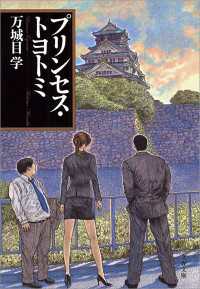

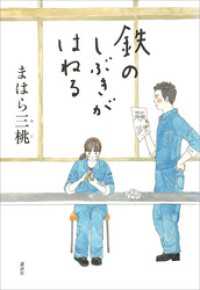



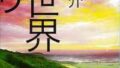
コメント