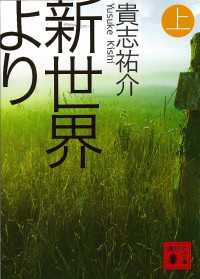
『新世界より(上)』は、読み始めてすぐに “世界観そのものに飲み込まれる” 作品だと感じました。 千年後の日本という未来を舞台に、自然の美しさと不穏な社会構造が同時に立ち上がり、ページをめくる手が止まらなくなりました。 最初は、呪力や奇妙な生物の設定を飲み込むのに少し時間がかかりましたが、ミノシロモドキとの出会いを境に一気に世界が開き、作品の持つ深い暗部が見え始めます。「この社会はなぜこうなったのか?」という疑問が湧き、読み手としても物語とともに真実へ近づいていく感覚がありました。 この“説明から没入へ”の移行がとても巧みで、プロローグ的な上巻でありながら、すでに大きな渦に巻き込まれているような高揚を感じました。
【書誌情報】
| タイトル | 講談社文庫 新世界より(上) |
|---|---|
| 著者 | 貴志祐介【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2015/03 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784062768535 |
| 価格 | ¥902 |
1000年後の日本。豊かな自然に抱かれた集落、神栖(かみす)66町には純粋無垢な子どもたちの歓声が響く。周囲を注連縄(しめなわ)で囲まれたこの町には、外から穢れが侵入することはない。「神の力(念動力)」を得るに至った人類が手にした平和。念動力(サイコキネシス)の技を磨く子どもたちは野心と希望に燃えていた……隠された先史文明の一端を知るまでは。 (講談社文庫)
本の概要(事実の説明)
本作は 第29回日本SF大賞受賞作。 舞台は千年後の日本。人々は“呪力”と呼ばれる念動力を日常的に使い、村は僧院的な組織によって運営されています。美しい自然の中で、早季たち子どもは「選別」されながら育っていく仕組みです。 あらすじは、12歳の早季と仲間たちが全人学級に進級し、実技を通して呪力を学ぶことから始まります。しかし、キャンプでミノシロモドキに出会ったことで、それまで隠されていた歴史の“真実”を知ってしまい、物語は一気に危険な領域へ動き始めます。 上巻はあくまで序盤ですが、「この世界はただのファンタジーではない」と気づかされる伏線が随所に張り巡らされており、未来社会の倫理・哲学・政治が濃密に描かれています。 SFが好きな方はもちろん、ディストピア作品に惹かれる読者には強くおすすめしたい一冊です。
印象に残った部分・面白かった点
物語のなかで特に心に残ったのは、まず「世界そのものが美しく、その裏で静かに恐ろしい」という感覚でした。自然は豊かで、村の営みはどこか素朴で温かいのに、実際は“監視と選別”によって保たれた秩序の上に成り立っている。そのギャップが読み進めるほどに不穏さへと変わり、物語の深い影をつくっています。 ミノシロモドキと出会って世界の真実を知る場面は、その象徴のようでした。それまでの世界観が一気に裏返り、先史文明の崩壊、PK能力者の暴走、暗黒時代の到来といった歴史が語られる流れは、読んでいて背筋が冷えるほど。これまでの“丁寧な説明”が一瞬で緊張へ切り替わる、圧巻の転調でした。 一方で、体育祭やキャンプで見られる早季たちの関係は、世界の残酷さとは対照的に純粋で柔らかく描かれています。呪力という強大な力を扱う子どもたちが、仲間と笑い合ったり、ささいなことで悩んだりする姿は、どこにでもいる少年少女そのもの。その無邪気さがあるからこそ、彼らが置かれている“選別のシステム”がより切なく感じられました。 中でも衝撃的だったのは、瞬の存在が不穏さを帯びていく展開です。彼が“悪鬼”化した可能性に気づいた瞬間、物語全体の空気が変わり、早季の戸惑いや恐怖がまるでこちらの胸にも入り込んでくるようでした。ページを戻って読み返してしまうほど、静かで深い恐怖が漂っていました。この作品は、一つ一つの設定より“感情の動き”が怖く、切ない。そこに強い余韻が残りました。
本をどう解釈したか
本作を読みながら感じたのは、これは単なる未来SFではなく、 「強大な力を持つ人間が、どうすれば共存できるか」 という問いそのものだということです。 呪力という能力は便利で、強く、圧倒的です。 しかしそれは同時に、人間を簡単に破滅へ導く毒にもなります。 だからこそ、教育という名の“選別”や“記憶操作”が導入され、 社会は恐怖をベースにした秩序で保たれている。 この構造は、現代社会の管理・監視・情報統制を想起させ、 「自由とは何か」「人間の本質はどこにあるのか」という問いへの入り口としても機能しているように感じました。 未来を描いているのに、どこか古い価値観(寺や僧院、祭礼)が残る世界観は、 「進化と退行は同時に起こる」と言われているようで、とても興味深かったです。
読後に考えたこと・自分への影響
上巻を読み終えたとき、 「力を持つことは幸せなのか」 という問いが心に残りました。 早季たちは呪力のおかげで豊かな生活をしていますが、 その裏側では“淘汰されて消えていった子どもたち”がいる。 幸福の上に成り立つ犠牲を見ないふりして生きる社会は、 現実の教育や競争と重なる部分が多いように思えました。 また、バケネズミたちの社会構造を見ていると、 種族間の力の非対称さがどれほど残酷かを突きつけられ、 「共存とは何か」という問いが深まります。 世界の仕組みが明かされるにつれて、 “知ることの怖さ”と“それでも知りたいという欲望”が生まれる—— それがこの作品の大きな魅力だと感じました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この作品は、静かな空気の中でじっくり沈み込むように読むのが最適です。 とくに夜、部屋の灯りだけでページをめくると、 作品の持つ「美しく不気味な空気」に完全に包まれます。 あるいは、自分の内面に向き合いたいときにも合う本です。 世界の“真実”が少しずつ暴かれていく過程が、こちらの思考も刺激し、 現実世界の構造について考えずにはいられなくなります。
『新世界より(上)』(貴志祐介・著)レビューまとめ
『新世界より(上)』は、圧倒的な世界観と丁寧な伏線によって、
読者を静かに、しかし確実に深淵へ引きずり込む作品でした。
上巻でここまで濃い余韻を残す小説は珍しく、続巻への期待が自然と膨らみます。
未来社会と人間の本質に興味がある方には、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
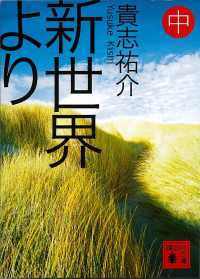
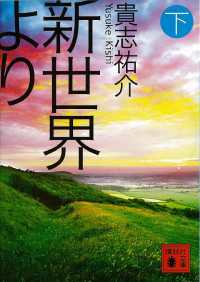
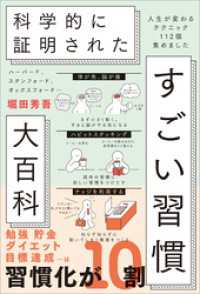

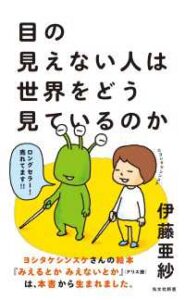


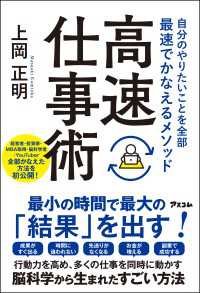


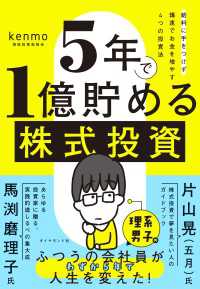

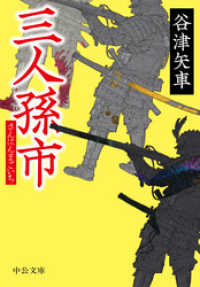
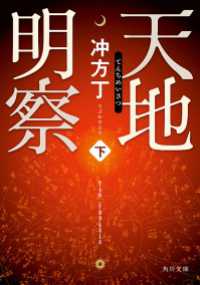
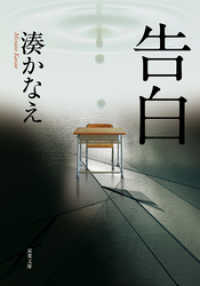
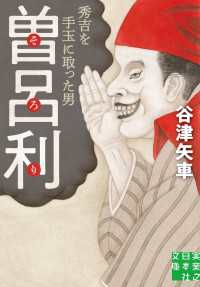
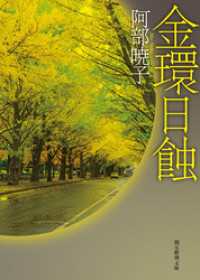

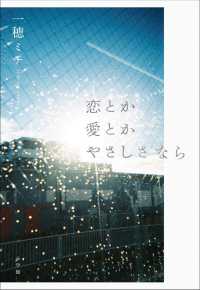


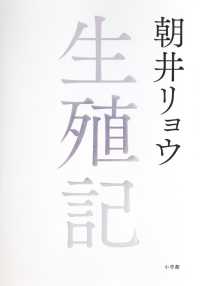
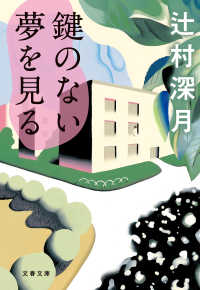
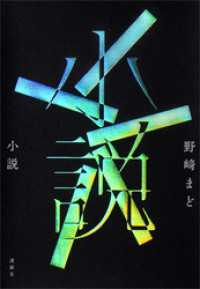
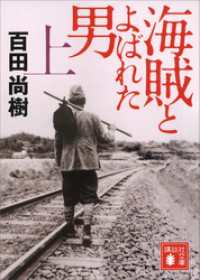

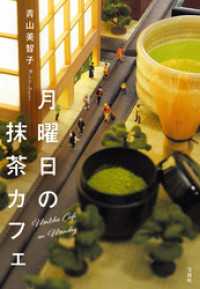
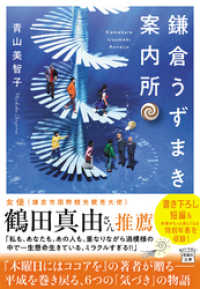
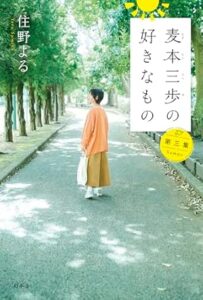



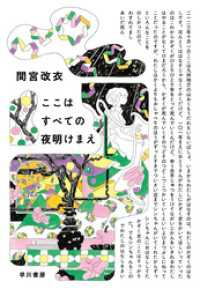

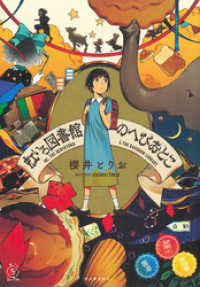
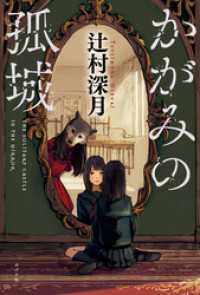
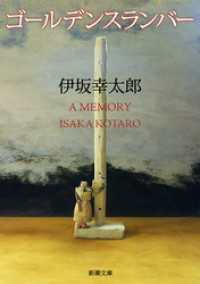
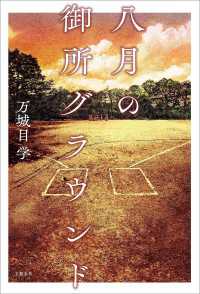
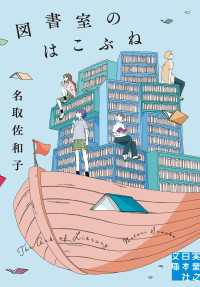
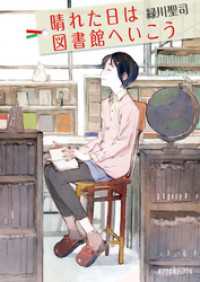

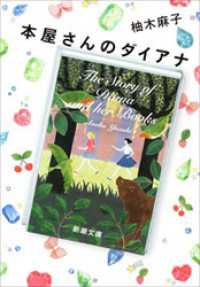
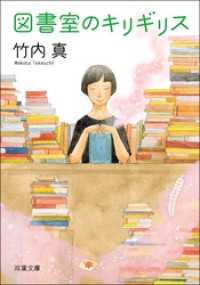


コメント