
『たまごを持つように』は、九州の中学校弓道部を舞台にした、とても静かでまっすぐな青春小説でした。読んでいるあいだ、弓道場の張りつめた空気と、「きゃん」「ぱん」と響く弦音が、紙の向こうからこちらにじわっと伝わってくるように感じました。派手な事件はほとんど起きないのに、胸の奥は何度も小さくふるえる――そんなタイプの物語です。 主人公の早弥は、人一倍不器用で、つい力を入れすぎてしまうタイプの女の子。天性のセンスを持つ実良、何でもそつなくこなすハーフの春と比べると、自分だけが遅れているように見えてしまう。その劣等感のリアルさに、私も何度も「わかる」とうなずきながら読み進めました。 タイトルにもなっている「たまごを持つように」という言葉は、弓を握るときの力加減を示す合言葉です。割れてしまいそうな卵をそっと支えるように、自分の力をコントロールすること。読んでいくうちに、それは弓道だけでなく、人との距離の取り方や、自分との向き合い方にもつながっていく言葉なのだと感じました。
【書誌情報】
| タイトル | たまごを持つように |
|---|---|
| 著者 | まはら三桃【著】 |
| 出版社 | 講談社 |
| 発売日 | 2017/03 |
| ジャンル | 絵本・児童書・YA・学習 |
| ISBN | 9784062153218 |
| 価格 | 1,265 |
手の内は「握卵(あくらん)」。自信が持てず臆病で不器用な初心者、早弥。ターゲットパニックに陥った天才肌、実良。黒人の父をもち武士道を愛する少年、春。弓も心も、強く握らず、ふんわりと握って。たまごを持つように弓を握り、手探りで心を通わせていく中学弓道部の男女3人。弓道への情熱、不器用な友情と恋愛。こわれやすい心がぶつかりあう優しい青春小説。
本の概要(事実の説明)
本作は、中学生の弓道部を描いた青春小説です。舞台は九州の中学校。弓道が大好きな3人――不器用だけどコツコツ努力する早弥、天性の才能を持ちながらも気まぐれな実良、アフリカ系アメリカ人の父を持つ春――が、実力者の先輩・由佳の背中を追いながら、九州大会優勝と全国の舞台を目指していきます。 早弥は、どうしても力が入りすぎてしまうクセを直すために、「たまごを持つように」弓を握る感覚を身につけようと、うずらの卵を持ち歩いたり、日常生活でもあえて左手を使ったりと地道な工夫を重ねていきます。一方で実良は、スランプである「早気」に悩まされ、自分の才能を信じきれなくなっていく。春は、ハーフゆえの視線とも向き合いながら、まっすぐに弓道に向き合っていきます。 周りを支える大人たちも印象的です。凛とした存在感を放つ御歳75歳の坂口先生、サッカー部出身で弓道は素人ながらも、顧問として一生懸命勉強しながら生徒に寄り添う澤田先生。それぞれの立場から、子どもたちの成長を静かに応援しています。弓道の専門用語や試合の流れも丁寧に描かれていて、弓道未経験でも十分ついていける構成だと感じました。 中学生向けの作品ではありますが、「努力と才能のバランスに悩む人」「部活での人間関係にモヤモヤしている人」には、大人でも刺さるテーマが多い一冊だと思います。
印象に残った部分・面白かった点
いちばん印象に残ったのは、3人それぞれの「弓道との距離」の描き方です。早弥は、一度にたくさん進めない自分をよくわかっていて、「一歩一歩しか歩けないのなら、長い間歩いていればいい」という気づきにたどり着きます。才能のある仲間に追いつけない焦りと、それでも歩みを止めない強さが、とても静かに、でも力強く描かれていました。 実良のスランプもリアルでした。読者からの感想に「こんなにすぐに治んねーよ」とあったように、実際の早気はそんなに簡単なものではないのだと思います。それでも、自分が「早気である」と認めたくない気持ちや、頭ではわかっているのに体が言うことを聞かないもどかしさは、とてもよく伝わってきました。弓道をやっていない私でも、「ああ、こういう状態ってあるよね」と共感できる描写でした。 春は、スポーツも勉強も音楽もできる「万能」タイプですが、決して嫌な優等生にはなっていません。アフリカ系アメリカ人の父を持つハーフとしての視線や、武士道への興味など、彼なりの背景があるからこそ、チームのバランスが取れているように感じました。ロバートさんの武士道の話から、「武という字は戦いを止めるという意味」という言葉が出てくる場面も印象的で、弓道という競技の奥行きを感じさせてくれます。 そして、由佳先輩やライバル校の歩、坂口先生や澤田先生など、脇役たちもそれぞれ魅力的です。特に、専門知識のない状態から顧問を任され、必死に弓道を学びながら生徒を支えようとする澤田先生の姿は、「大人も完璧じゃないけれど、一緒に成長している」という安心感を与えてくれました。
本をどう解釈したか
この物語を通して強く感じたのは、「才能」と「努力」をどちらか一方のものとして扱わない視線です。実良のように早く上達する人は、ときに「天才」と片付けられがちですが、その裏にはスランプの怖さや、期待されることのプレッシャーもある。一方の早弥は、なかなか結果が出ない苦しさを抱えながら、それでも毎日弓と向き合い続ける。「一歩一歩しか歩けないのなら、長い間歩いていればいい」という言葉には、努力を「鈍くささ」として切り捨てない優しさがあるように思えました。 また、「たまごを持つように」という比喩は、弓の握り方だけではなく、人との関係の持ち方にも重なっていきます。強く握りしめれば割れてしまうし、雑に扱えば落としてしまう。相手にも自分にも、適度な余白を残すような力加減が必要だという感覚です。実良との衝突や、春との距離感、先輩の引退など、さまざまな出来事を通して、早弥たちは少しずつその“力の抜き方”を学んでいきます。 弓道そのものも「武は戦いを止めるもの」という武士道の考え方と結びつけられています。矢を放つまでの静かな所作、丹田に心気を集める感覚、集中するとふっと体が軽くなる瞬間――それらは、相手を倒すためというより、自分自身を整えるための行為として描かれていました。ここに、まはら三桃さんらしい、やわらかくも芯のある倫理観を感じました。 全体として、物語は大きく揺れ動くドラマではなく、小さな揺らぎを丁寧にすくい上げていくタイプの作品です。その「淡さ」が物足りないと感じる読者もいるかもしれませんが、中学生たちの心の動きを「武道らしい静けさ」の中で描きたいという意図なのだろう、と私は解釈しました。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えてまず残ったのは、「一度にたくさん進めなくてもいい」という、ちいさな安心感でした。どうしても日常の中では、結果の出るスピードで自分を評価しがちです。早く上達する人や、何でもそつなくこなす人を見ると、つい自分を「劣っている側」に置いてしまう。けれど、早弥のように一歩一歩しか進めない人だからこそ見える景色もあるのだと、この物語に教えられた気がします。 また、「武は戦いを止める」という言葉から、競争との付き合い方についても考えさせられました。大会で勝ち負けがつく世界にいながらも、彼らの矢は、誰かを打ち負かすためだけではなく、自分の弱さや迷いと向き合うためにも放たれている。これは、勉強や仕事など、日常のあらゆる「勝ち負け」にも通じる感覚だと感じました。 弓道の描写そのものからは、「体の使い方」と「心の置き方」が連動していることも伝わってきます。力を抜く練習、呼吸を整える時間、矢をつがえる所作。そうした一つ一つを追いかけているうちに、私自身も少し呼吸がゆっくりになっていることに気づきました。スポーツものなのに、どこか瞑想的な読後感が残るのも、この作品の面白さだと思います。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この本は、静かな時間にゆっくりページをめくりたくなるタイプの作品です。できれば、休日の午後、窓からの光がやわらかく差し込むような時間帯に、温かい飲み物を横に置きながら読むのがおすすめです。派手な展開で一気読みするというより、弓道場の静けさや、早弥たちの息づかいを感じるペースで、少しずつ読み進めたくなります。 もう一つおすすめなのは、ちょっと自分に自信がなくなっているときや、「自分だけ足踏みしている気がする」と落ち込んでいるときです。周囲のスピードに追いつけないもどかしさや、「どうせ自分なんて」と思ってしまう気持ちに、この物語はそっと寄り添ってくれます。読み終えたあと、「今の一歩でも、ちゃんと前に進んでいるのかもしれない」と、ほんの少しだけ自分を許せるようになるかもしれません。
まとめ
『たまごを持つように』は、弓道を題材にした作品でありながら、スポ根的な熱さよりも、「不器用な自分をどう受け入れていくか」という静かなテーマをじっくり描いた青春小説だと感じました。早弥・実良・春、それぞれのスタイルで弓道と向き合う3人と、彼らを見守る大人たちの姿に、自分の学生時代や今の自分の姿を重ね合わせながら読める一冊です。弓道経験の有無にかかわらず、「一歩一歩しか歩けない自分に悩んでいる人」に、そっと手渡したくなる物語でした。
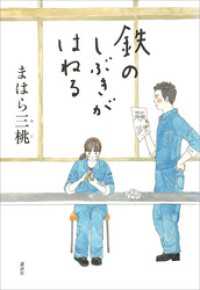
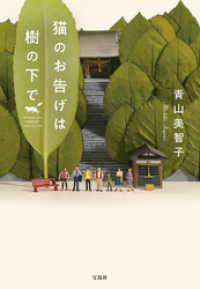
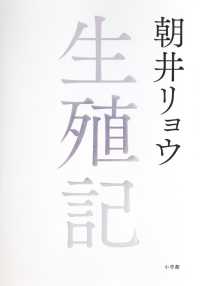

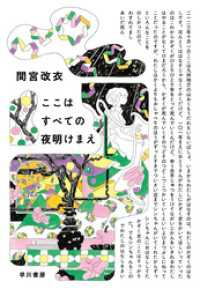
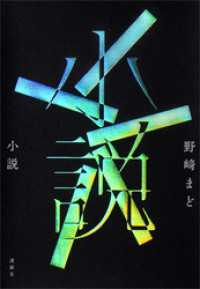
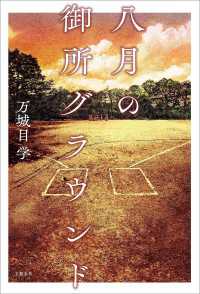

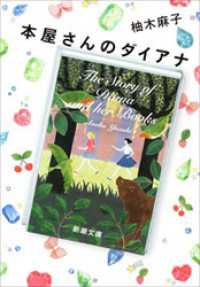
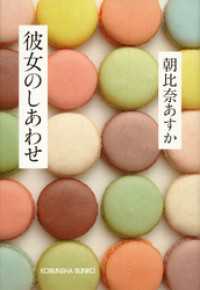
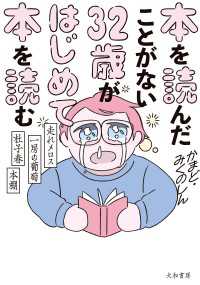

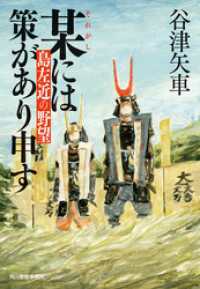
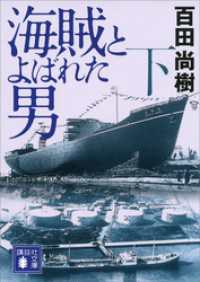
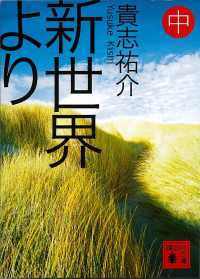

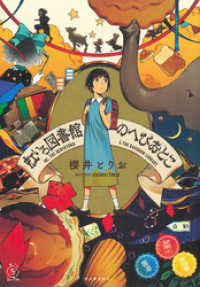
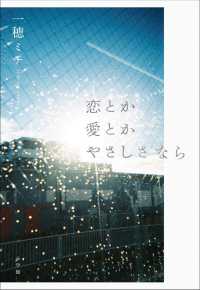

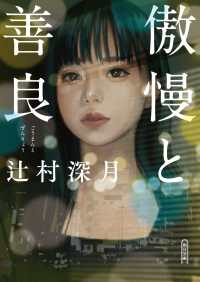
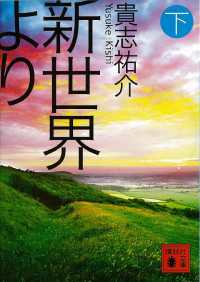
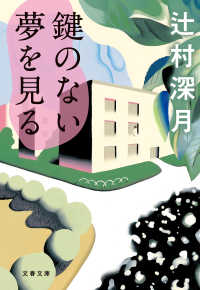

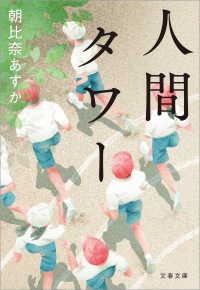
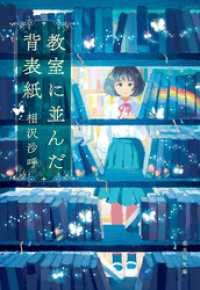
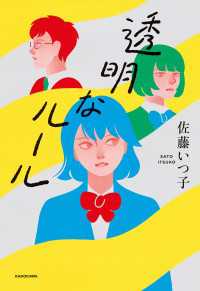
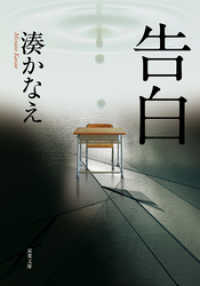
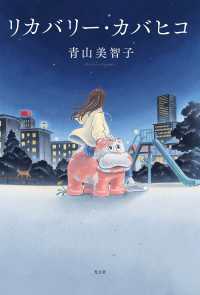


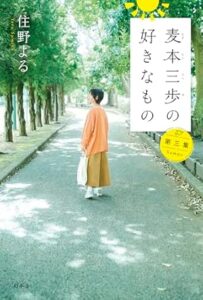
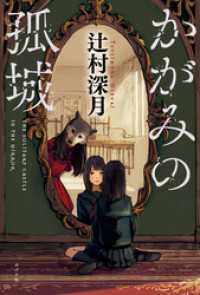


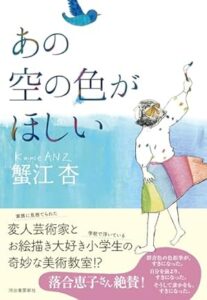
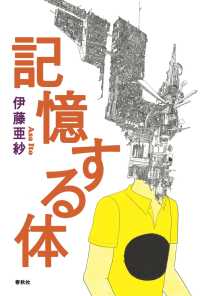

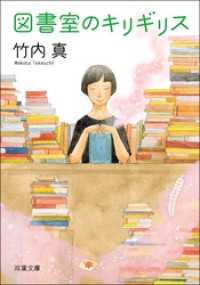
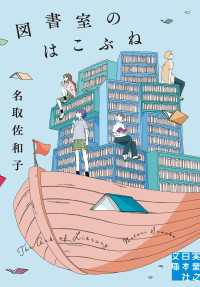
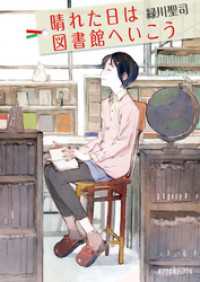
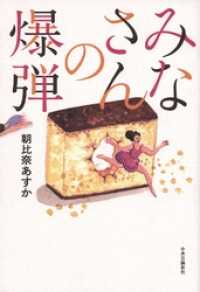

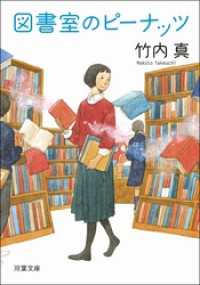
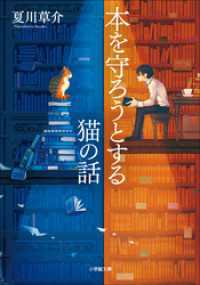
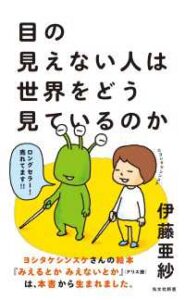
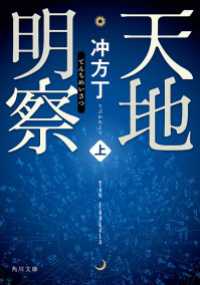
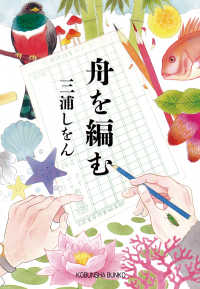

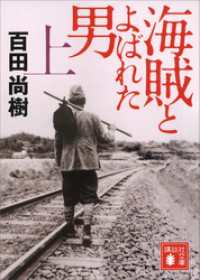




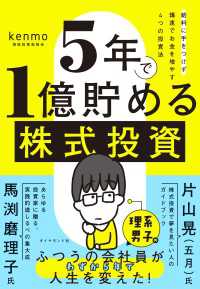

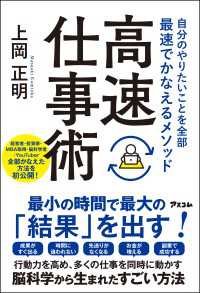



コメント