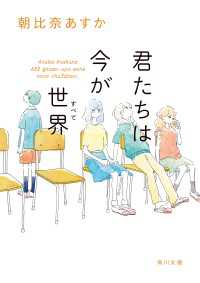
学級が崩れかけ、担任の声は届かず、言葉は花火のように打ち上がっては誰かを傷つける——そんな教室の気配を、この小説は容赦なく連れてきます。読みながら、私は何度も胸の奥を握られるような苦しさを覚えましたが、ページを閉じることはできませんでした。 「今、あなたを理解して守ることはできるけど、その先はあなた自身が変わらないと何も変わらない。」という趣旨の言葉に、私ははっとさせられました。支援と自立、肯定と変化の促し——どちらも欠かせない現場の現実が、人物たちの視線と言葉に宿っていると感じました。 教室は彼らの“世界のすべて”です。だから判断は苛烈で、噂は熱を帯び、善意も暴力に変わることがある。その閉塞を描き切りながら、なお小さな回復の芽を諦めない本だと感じました。
【書誌情報】
| タイトル | 角川文庫 君たちは今が世界 |
|---|---|
| 著者 | 朝比奈あすか【著者】 |
| 出版社 | KADOKAWA |
| 発売日 | 2021/07 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784041111529 |
| 価格 | ¥836 |
六年三組の調理実習中に起きた洗剤混入事件。犯人が名乗りでない中、担任の幾田先生はクラスを見回してこう告げた。「皆さんは、大した大人にはなれない」先生の残酷な言葉が、教室に波紋を生んで……。
本の概要(事実の説明)
本作は、学級崩壊の瀬戸際にある小学6年3組を舞台にした連作短編集です。いじられ役として笑いを取る快楽に呑まれる子、優等生として“正しさ”に縛られる子、カリスマ性に振り回される子、発達や気質の違いから「問題児」と呼ばれてしまう子——視点は入れ替わり、読者は教室の四隅を歩くように彼らの心へ近づきます。 親の価値観やSNSの炎が背後から圧をかけ、教師も疲弊する。調理実習の「洗剤事件」など幾つかの出来事が導火線となり、関係の綻びが露わになります。とはいえ、物語は断罪に向かいません。後半には、それぞれの“良さ”や可能性が掬い上げられ、彼ら自身の手で少しずつ現状を切り替える兆しが見えます。 読者対象は大人も子どもも、とりわけ保護者や教育現場の方には鋭く響く内容だと感じました。
印象に残った部分・面白かった点
まず、担任の「皆さんは、どうせ大した大人にはなれない。」という挑発的な言葉です。暴言として切り捨てるのは簡単ですが、私はその裏にある疲弊と絶望、そして未熟さへの苛立ちが混ざった人間の叫びを見たように思えました。 “めぐ美”の章は、カリスマ的存在への憧れと反発が同居する複雑な感情を丁寧に書き出し、小学生特有の光と毒を同時に映します。嫌悪だけで切らず、好意と嫉妬の揺らぎを肯定する筆致に救われました。 「言葉を、打ち上げ花火みたいに使う。」というフレーズも忘れがたいです。場を沸かす快楽の裏で、誰かの肌に火の粉が落ちる。SNS時代の“拡散の軽さ”まで含んだ怖さに、私は背筋を伸ばしました。
本をどう解釈したか
私はこの小説を、「見る」ことの倫理を問う作品として読みました。人は他者の“表側”を都合よく切り取って判断してしまう。けれど本作は、同じ人物に別の光を当てる視点移動で、読者の認知を揺さぶります。いじめる側にも、いじられる側にも、家庭と過去があり、未熟さと可能性がある。 また、支援と自立の線引きについても示唆的でした。「あなたはあなたのままで愛される」と「今より良い自分になりなさい」は矛盾しません。自己肯定の足場があって初めて、変化へ踏み出せる——この二段構えが、現場のリアルだと感じました。 さらに、教師像の更新も描かれます。切り捨てではなく、“目の前にいる子どもを見捨てない”姿勢へ。教育は劇的な救済より、日々の観察と微調整の積み重ねだと改めて思いました。
読後に考えたこと・自分への影響
読後、私が強く意識したのは次の三点です。 1. 言葉の温度管理:場を取るための一言が、誰かの未来を削ることがある。発する前に、相手の耳まで届いたときの温度を想像したいと感じました。 2. 側面ではなく全体を見る:見えている断片で判断せず、内側の事情を想像するクセをつけること。誤読はゼロにならないからこそ、保留する勇気が要ると感じました。 3. 時間軸で支える:即効性を求めず、離れず、見放さず。小さな変化を拾い続ける伴走が、子どもにも大人にも必要だと思いました。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
この作品は、静かな夜に一人でじっくり向き合う時間に読むのが似合います。 部屋の灯りを少し落として、ページをめくるたびに心の奥を静かに照らしてくれるような感覚があります。登場人物たちの痛みや葛藤が、自分の記憶のどこかと重なり、思わず呼吸を整えたくなる瞬間が訪れます。
『君たちは今が世界』(朝比奈あすか・著)レビューまとめ
教室は小さな世界であり、彼らには世界のすべてです。だから残酷で、だから救える。
本作は、断罪でも美談でもなく、未熟さと可能性の同居をまっすぐ描き切りました。言葉の重さを確かめたい夜に、そっと開きたい一冊です。
小学生の娘を持つ母親として、読みながら何度も胸が締めつけられました。
「うちの子も、こんなふうに誰かに傷つけられたり、逆に知らないうちに誰かを傷つけてしまうことがあるのかもしれない」と思うと、登場人物の姿が他人事ではなくなります。
この本を通して、子どもの心に寄り添うことの難しさと、見守る覚悟の大切さを改めて感じました。
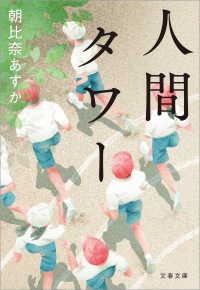
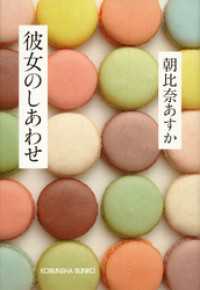
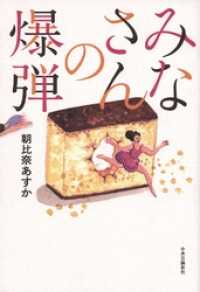
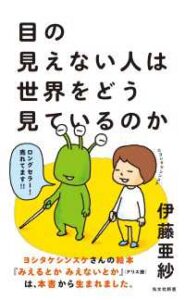
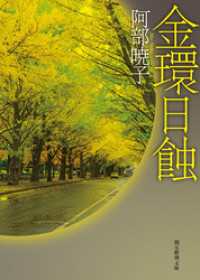

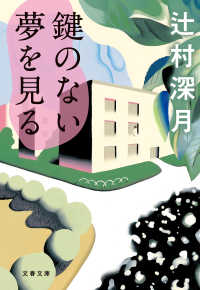

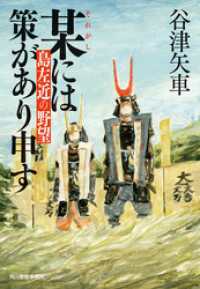
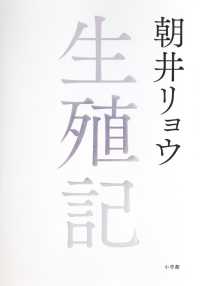




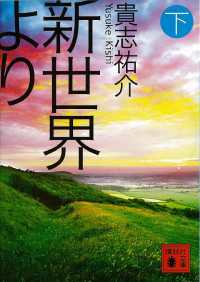
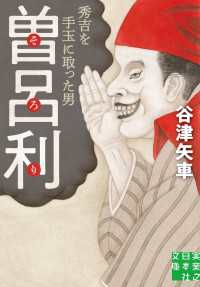
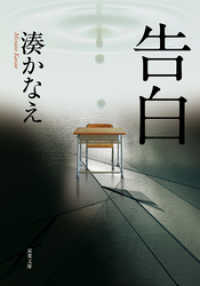
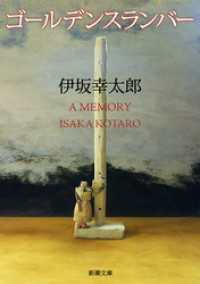


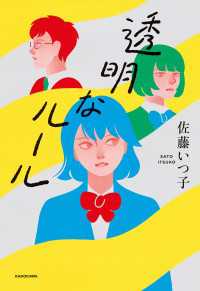
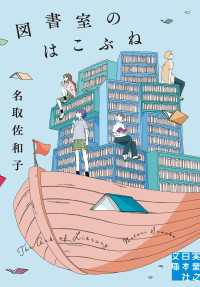

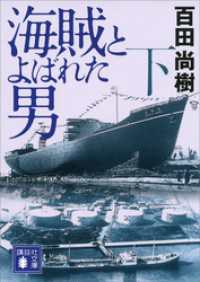
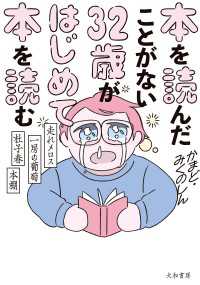

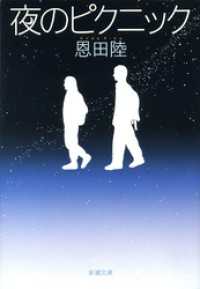
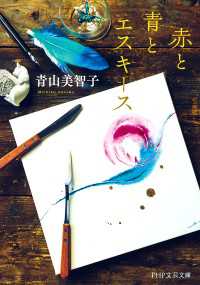

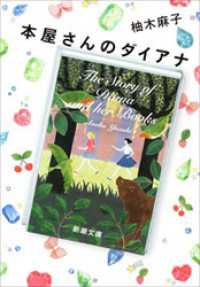
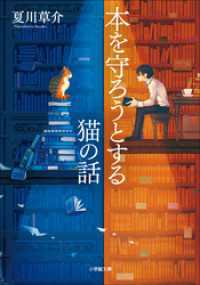
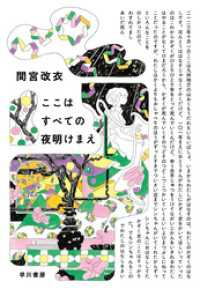
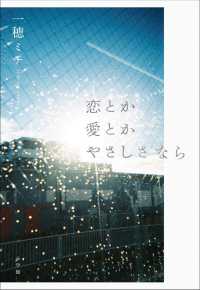


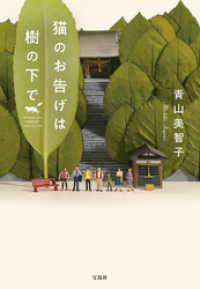
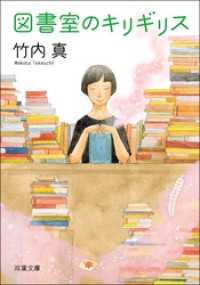


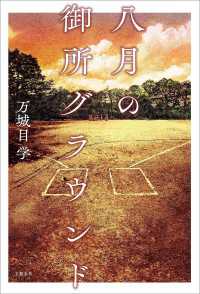
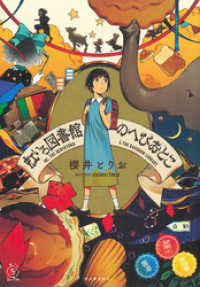

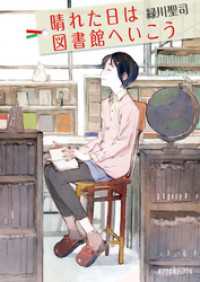



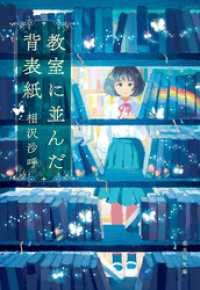
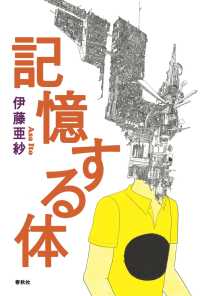
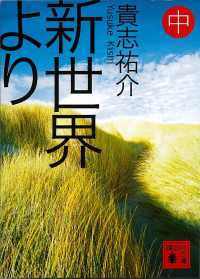
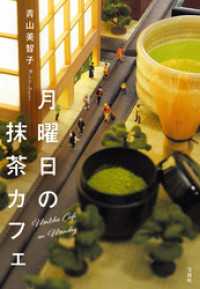
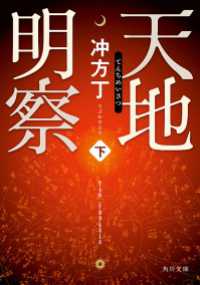
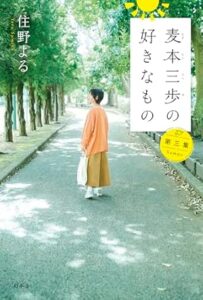
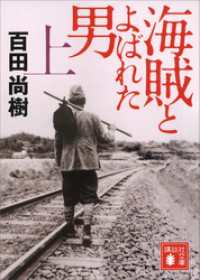
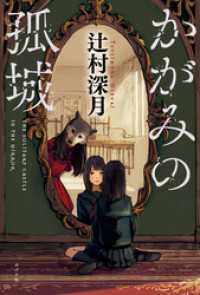

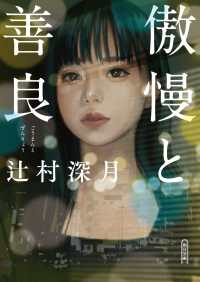
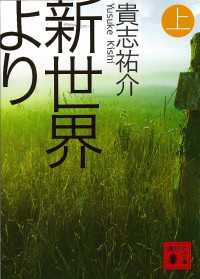
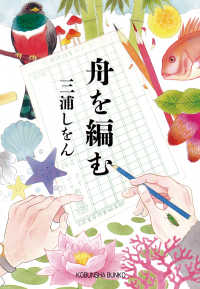

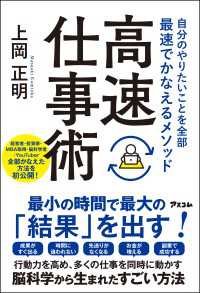

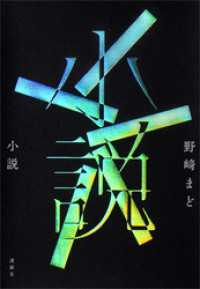


コメント