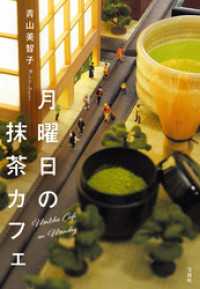
最初の一杯の湯気に、胸の奥がふっとゆるみました。『木曜日にはココアを』の続編である本作は、定休日の月曜に「抹茶カフェ」へと姿を変えたマーブル・カフェから始まります。京都の茶問屋・福居堂の若旦那・吉平が点てる抹茶と、和菓子屋の大奥さま・タヅさんの温かな気配。そこに偶然居合わせた人々の心が、季節の移ろいとともに静かにほどけていくのを、私はページ越しに何度も感じました。 読み進めるほど、「縁って、種みたいなもの」という言葉が胸に根づいていきます。小さな言葉や行動が、いつのまにか誰かを救い、それが別の誰かへ渡っていく。十二編がつながって円になる構成は、日常の見えない連鎖をそっと可視化してくれるようでした。読後、私は少しだけ丁寧に言葉を選びたくなりました。抹茶のほろ苦さに似た、優しさの余韻がゆっくり残ります。
【書誌情報】
| タイトル | 宝島社文庫 月曜日の抹茶カフェ |
|---|---|
| 著者 | 青山美智子【著】 |
| 出版社 | 宝島社 |
| 発売日 | 2023/06 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784299044099 |
| 価格 | ¥760 |
3年連続「本屋大賞」にノミネートされた青山美智子さんの最新文庫本。川沿いの桜並木のそばに佇む喫茶店「マーブル・カフェ」。その「マーブル・カフェ」が定休日の月曜日にだけ「抹茶カフェ」を営むことに。ついていない携帯ショップの店員、妻を怒らせてしまった夫、恋人と別れたばかりのシンガー、時代に取り残されたと感じている京都老舗の元女将……。思い悩む人々が誰かの何気ない言葉で前向きな気持ちになっていく――。人は知らず知らずのうちに、誰かの背中を押している。――これは、一杯の抹茶から始まる、東京と京都をつなぐ12ヵ月の心温まるストーリー。『木曜日にはココアを』のおなじみのメンバーも登場する、シリーズ続編がついに文庫化です。※本書は2021年9月に刊行された単行本『月曜日の抹茶カフェ』を文庫化したものです。
本の概要(事実の説明)
本作は、京都と東京を行き来する十二編の連作短編集です。抹茶カフェのイベントに呼ばれた吉平を起点に、携帯ショップの女性店員、ミドサー夫婦、大学生、老夫婦、職人たちが、月ごとの情景とともにバトンをつないでいきます。各編は独立して読めつつ、登場人物や言葉、小さな仕草が数珠つなぎにリンクし、最後は語りが一周して起点に戻る——短編なのに長編の手応えがある構成が心地よいです。 テーマは「ご縁」と「気づき」。タヅさんの言葉や、和菓子・水無月の季節感、抹茶の甘味と苦味の対比が、人生の旨味をやさしく照らします。派手な事件はありませんが、誰もが抱く小さな不全感やぎこちなさが確かに描かれ、読者に近い体温で届く一冊だと感じました。穏やかな読書時間を求める人、連作の“繋がる快感”が好きな人に向きます。
印象に残った部分・面白かった点
強く心に残ったのは、十月の一節——「この世に生まれ落ちたときから、僕たちはただどこまでも繋がり続けている」。作品全体の核が一文に凝縮され、胸が熱くなりました。八月の老夫婦の「ええしごと、してるな」という言葉も忘れられません。数字では測れない仕事の価値を、そっと肯定するやわらかな眼差しに救われます。 大学生の「デルタの松の樹の下で」では、周りに合わせて自分を見失った孝晴が、友人の言葉で一歩を踏み出す場面に、私も背中を押されました。雨音を聞き分けるように、相手の“話すペース”を待つ登場人物の成熟にもハッとします。さらに、宮沢賢治の紙芝居や「イソギンチャク探偵とクマノミ婦警」といった小さなモチーフが、章を超えて灯りのように連鎖していく仕掛けが見事。最後の章で物語が“シュッと”まとまる瞬間、思わず頷きました。
本をどう解釈したか
私には、この作品が「時間と場所を越える“連鎖の倫理”」を描いているように思えました。出会いは偶然に見えて、誰かが誰かへ手渡した小さな善意の連続の上に成り立っている。だからこそ、私たちは“今ここ”の言葉と態度を丁寧にする責任があるのだ——抹茶の一服に込められた礼法は、その姿勢の比喩です。 また、甘味と苦味のバランスが語り全体を支えています。思い通りにならない現実の「苦み」を消すのではなく、和菓子の「甘み」と調和させることで旨味に変える。その配合を探る過程こそが人生であり、縁の育ち方なのだと感じました。登場人物に“悪人”がほとんどいないのは、世界を善悪で断ち切らず、関係の編集(編集し直し)として描くため。青山作品の連作形式は、その思想の器なのだと思います。
読後に考えたこと・自分への影響
読み終えて最初に浮かんだのは、「急がなくていい」という感覚でした。縁は種で、芽吹きにも季節がある。焦って引っ張るのではなく、相手の速度を尊重すると、関係は思いがけない実りをもたらす。老夫婦のひと言や、職人の手つき、若者の逡巡——どれもが誰かの未来をそっと支える“栄養”でした。 同時に、言葉の扱い方も見直したくなります。「何を言うか」と同じくらい「何を言わないか」。沈黙が育てる信頼もある。自分の中の“ほろ苦さ”を否定せず、甘さと合わせて味わえるようになること——それが成熟なのだと感じました。明日から私は、誰かの一日を少しだけ整える挨拶を増やし、季節のお菓子を分かち合い、短いメールにも一行の余白を残してみようと思います。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
おすすめは、静かな休日の午後。湯のみを手に、窓辺の光にページを透かしながら読むと、章ごとの季節感が身体にやさしく染み込みます。もう一つは、夜にじっくり。照明を落としてBGMは控えめに。抹茶の泡のきめを見るように、言葉の細かな粒立ちに気づけます。 章を一つ読むごとに本を閉じ、余韻を小皿の和菓子で受け止める——そんな読み方が似合います。読み終えたら最初の章へ少し戻ってみてください。どこかで拾い損ねた“種”が見つかり、あなたの日常にも、小さな芽が顔を出すはずです。
『月曜日の抹茶カフェ』(青山美智子・著)レビューまとめ
『月曜日の抹茶カフェ』は、人と人との“ご縁”を抹茶の香りとともに描いた、やさしく温かな連作短編集です。
何気ない言葉や行動が誰かを救い、その思いやりがまた次の人へとつながっていく。
読後には、人生の苦みも甘みも愛おしく感じられ、心がふっとやわらぐようでした。
静かな休日や眠る前に読むのにぴったりな一冊です。
読後の余韻を深めるための読書サービス
この本は、読み終えた瞬間に何かが完結するというより、あとから静かに効いてくるタイプの一冊だったように感じました。
ページを閉じたあとも、ふとした瞬間に言葉や場面を思い出して、「もう一度考えてみたい」と思わせる余韻が残ります。
もし、そうした感覚をもう少し大切にしたいなら、文字とは違うかたちで触れ直すのも一つの方法です。
Audibleは、オーディオブックやポッドキャストを含む数十万作品が聴き放題で、30日間の無料体験があり、月額1,500円でいつでも退会できます。
移動中や家事の合間など、日常の中で考え続ける時間をつくりたい人には、無理のない選択肢だと思いました。
一方で、「まず全体像を整理してから向き合いたい」「もう少し軽い入口がほしい」と感じることもあります。
flierは、1冊約10分で読める要約が用意されていて、毎日1冊ずつ追加されます。
ビジネスや教養を中心に4,200冊以上(ゴールドプラン)が揃っており、音声要約にも対応しているので、通勤中や眠る前の時間にも取り入れやすいです。
全体像をつかむための入口としては flier。
一冊の内容を、時間をかけて味わい直すなら Audible。
その時の気分や読み方に合わせて選ぶのが、いちばん自然だと感じました。

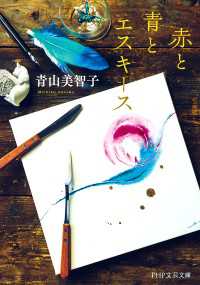
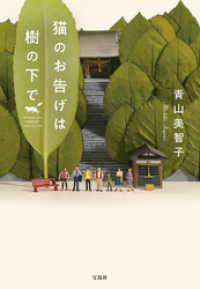

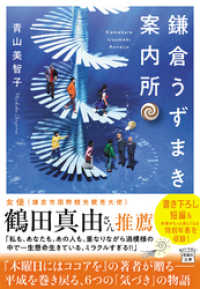
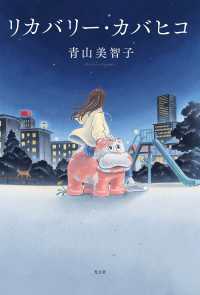

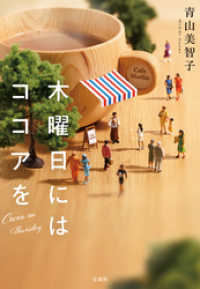

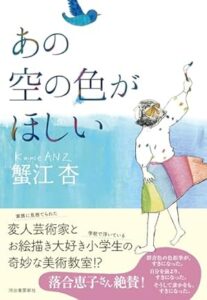

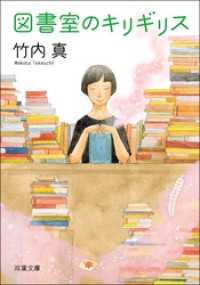

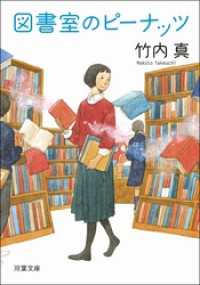
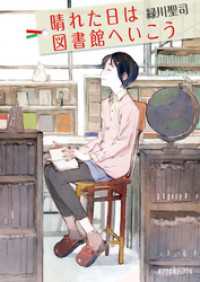
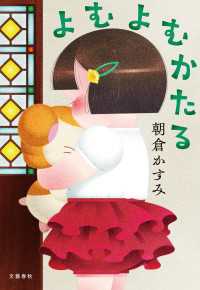


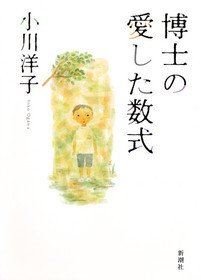
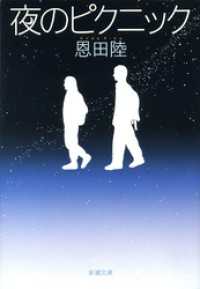
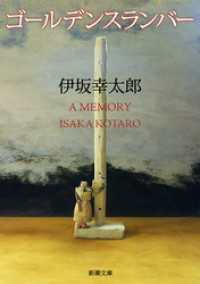

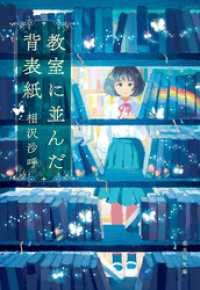
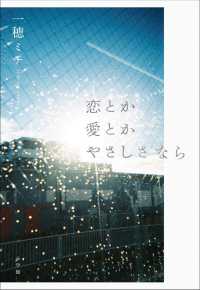
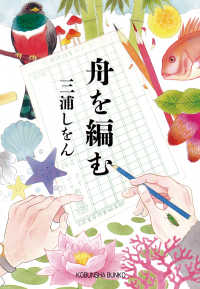

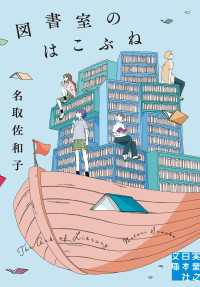
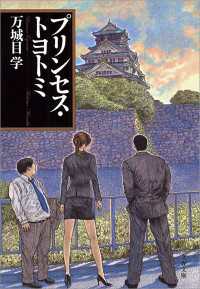
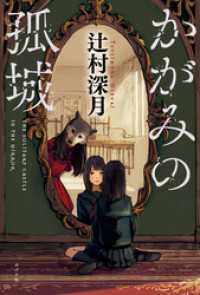

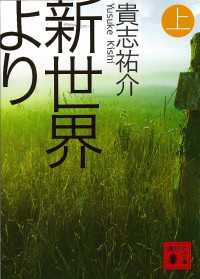




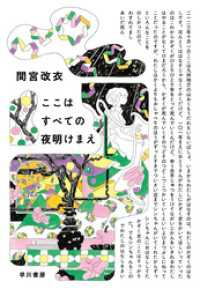

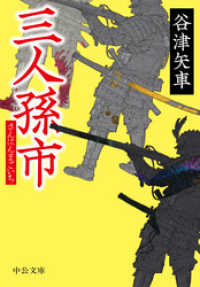

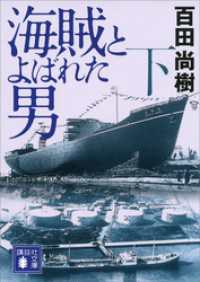
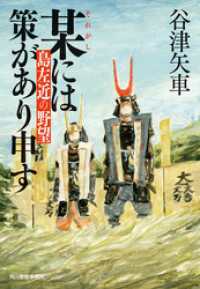
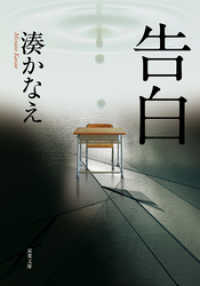


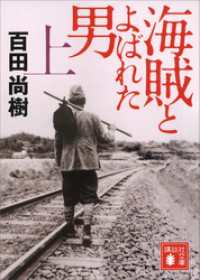
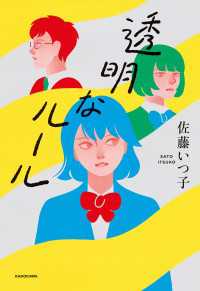
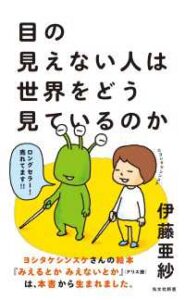
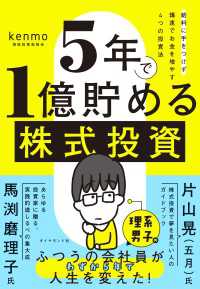
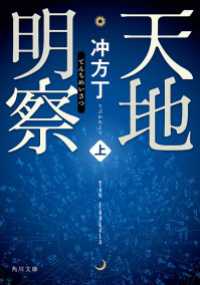

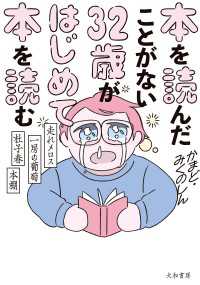
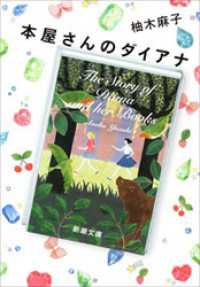



コメント