
読後にまず感じたのは、「橘玲らしさ、炸裂」という一言でした。 『HACK』は、社会のルールを知り尽くしたうえで、その隙間を軽やかにすり抜けるような知性の物語です。読んでいて何度も「こんな風に世界を見られたら」と思わされました。 ビットコインやサイバー犯罪といった現代的な題材が散りばめられ、同時に「公権力とは何か」「自由とはどこにあるのか」という哲学的な問いも潜んでいます。久しぶりに橘玲の小説を読んで、社会の裏側を覗くようなゾクゾクする感覚を味わいました。
【書誌情報】
| タイトル | 幻冬舎単行本 HACK |
|---|---|
| 著者 | 橘玲【著】 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
| 発売日 | 2025/10 |
| ジャンル | 文芸(一般文芸) |
| ISBN | 9784344045286 |
| 価格 | ¥2,090 |
一般読者から、「圧倒的な没入感」「世界の解像度が上がる」というレビュー続々! 今度の「マネーロンダリング」は、暗号資産(=仮想通貨=クリプト)! これが令和の冒険ミステリーだ!!橘玲11年ぶりの書き下ろし長編。2024年、秋。暗号資産で得た利益への課税を逃れ、バンコクで暮らすハッカーの樹生(たつき、30歳)は、大麻ショップの屋上で日本人の情報屋・沈没男(ちんぼつおとこ)から相談を受ける。彼は、特殊詐欺で稼いだ違法資金を、ビットコインを使ってマネーロンダリングしたい、というのだ。頭脳明晰だが退屈な日々を送る樹生は、その話に乗ることにした。彼にとってはハッキングもマネロンもクリプト(暗号資産)もすべて「ゲーム」だった。そんな樹生は、五年前のスキャンダルで失踪した元アイドル咲桜(さら)がバンコクにいることを知り、そして彼女から連絡を受けたことがきっかけで、国際的な「陰謀世界」へと迷い込んでいく――。樹生にとって、最初は取るに足らないゲームのはずだった。彼に近づく検察と公安の諜報機関。北朝鮮のハッカー集団ラザルス。関知せず動かないタイ警察。なぜか樹生にコンタクトを取り続ける伝説のハッカーHAL(ハル)---。ハッキング技術を駆使した、目眩くマネーロンダリング手法と、二重三重に仕組まれた罠と裏切りで、狙い狙われるのは、10億円が500億、そして2500億円へと瞬く間に膨れ上がる北朝鮮の暗号資産マネー――。
本の概要(事実の説明)
『HACK』は、橘玲による久々の長編小説で、サイバー社会とグローバル経済を背景に描かれた知的サスペンスです。 ビットコイン、キャバクラに通う大学生、そして国家のシステムをすり抜ける天才的な「ハッカー」たち。現代日本の経済的停滞や倫理の空白を、軽妙かつ冷徹な筆致で描いています。 テーマとしては「欺く知性」や「制度を乗りこなす者と従う者の差」。橘作品に通底する「社会構造の不条理」への眼差しが、今回も鋭く光ります。 難しい経済用語も多いのに、なぜかすっと頭に入ってくるのは、著者の語り口がエッセイで培われたものだからでしょう。彼のノンフィクションを読んできた読者にとっては、まるで理論が小説の中で“実験”されているような感覚です。
印象に残った部分・面白かった点
印象的だったのは、「現金」という存在への独特の視点でした。 橘は「完璧な帳簿がないからこそ現金が使われている」と描写します。普段当たり前のように使うお金を、社会の“余白”として描く発想にハッとさせられました。 また、「詭弁ですよ」という一節から始まる税制度のシーンも強烈です。 国家の制度はあえて“余白”を作り、その中で人々を泳がせる。必要があれば捕まえ、そうでなければ自由にさせる――まさに現代社会のリアルを突き刺す描写でした。 橘玲の知的挑発はいつも痛快で、読んでいるうちに「自分はどこまで自由なのか?」と問い直したくなります。
本をどう解釈したか
この小説のタイトル「HACK」には二重の意味があると感じました。 ひとつは、テクノロジーの文脈での“ハッキング”。 もうひとつは、社会そのものを“乗っ取る”という象徴的な行為です。 米国のメガテック企業が世界をハックしたように、物語の登場人物たちは国家や制度の「裏側」にアクセスしていく。 そこには単なる犯罪や反逆ではなく、「知の使い方」に対する倫理的な問いがあります。 知識を持つ者が世界をどう変えるのか。あるいは、どのように“欺く”のか。橘玲はその境界線の危うさを、小説という形式で提示しています。 私はこの作品を、社会の構造を理解するための“思想実験”のように感じました。読後には、不気味な静けさと同時に、自分の中の倫理観が少し揺らぐような感覚が残ります。
読後に考えたこと・自分への影響
この本を読み終えて強く思ったのは、「小市民にも小市民なりのHACKがある」ということでした。 世界を変えるのはメガテックの天才たちだけではありません。 日常の中にも、自分なりの思考や選択で“ハック”できる余白がある。たとえば、情報の受け取り方を変える、常識を疑ってみる、制度の仕組みを学んでみる――それだけでも世界の見え方は変わる。 橘玲の作品は、読者に「自分で考えろ」と突きつけてきます。 その挑発的な姿勢こそが、彼の魅力であり、『HACK』という作品の真のメッセージなのだと感じました。 読み終わる頃には、自分の中の「思考のOS」がアップデートされたような気がします。
この本が合う人・おすすめの読書シーン
『HACK』は、静かな夜に読むのがおすすめです。 日中の雑念が消えた時間、デスクライトの下で一人、ページをめくる。 社会の裏側をのぞくような感覚を、じっくり味わえます。 また、カフェや旅先で読むのもいいでしょう。 都会の喧騒の中でこの本を開くと、「この世界も誰かにハックされているのかもしれない」という不思議な感覚に包まれます。 知的刺激を求める夜、何かを変えたいと思っているとき、橘玲の『HACK』は確実にあなたの思考を揺さぶります。
橘玲『HACK』レビューのまとめ
橘玲『HACK』は、社会を見抜く知性と、それを使いこなす覚悟を問う小説。
軽快なストーリーの中に、鋭い思想と倫理が潜む“現代の寓話”のような一冊です。
読後の余韻を深めるための読書サービス
この本は、読み終えた瞬間に何かが完結するというより、あとから静かに効いてくるタイプの一冊だったように感じました。
ページを閉じたあとも、ふとした瞬間に言葉や場面を思い出して、「もう一度考えてみたい」と思わせる余韻が残ります。
もし、そうした感覚をもう少し大切にしたいなら、文字とは違うかたちで触れ直すのも一つの方法です。
Audibleは、オーディオブックやポッドキャストを含む数十万作品が聴き放題で、30日間の無料体験があり、月額1,500円でいつでも退会できます。
移動中や家事の合間など、日常の中で考え続ける時間をつくりたい人には、無理のない選択肢だと思いました。
一方で、「まず全体像を整理してから向き合いたい」「もう少し軽い入口がほしい」と感じることもあります。
flierは、1冊約10分で読める要約が用意されていて、毎日1冊ずつ追加されます。
ビジネスや教養を中心に4,200冊以上(ゴールドプラン)が揃っており、音声要約にも対応しているので、通勤中や眠る前の時間にも取り入れやすいです。
全体像をつかむための入口としては flier。
一冊の内容を、時間をかけて味わい直すなら Audible。
その時の気分や読み方に合わせて選ぶのが、いちばん自然だと感じました。

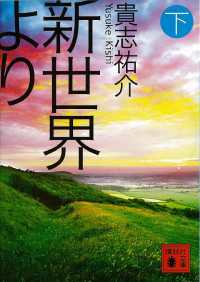
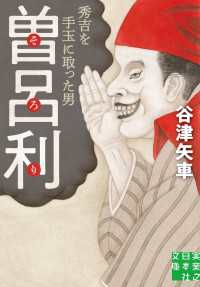
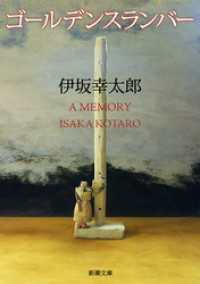

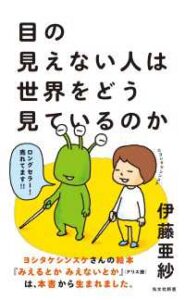
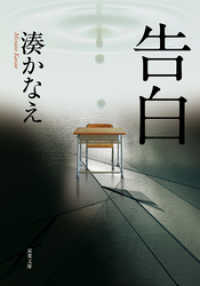

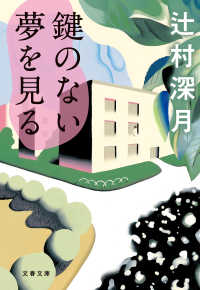
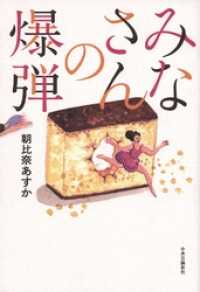
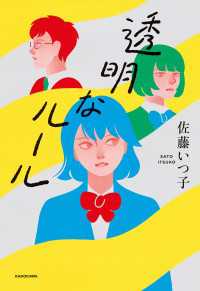
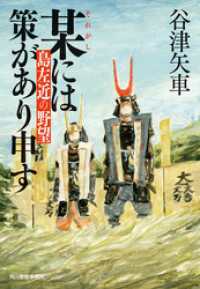



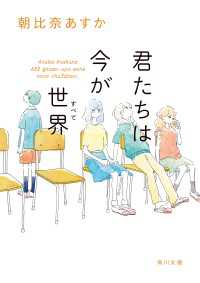
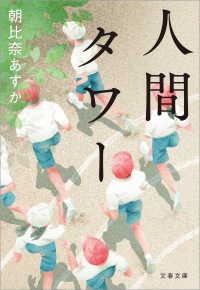

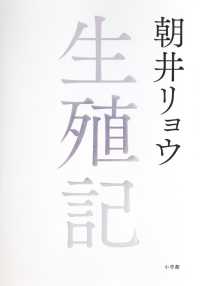

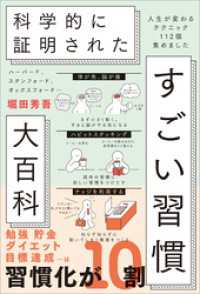
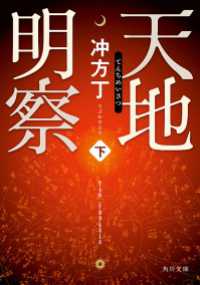

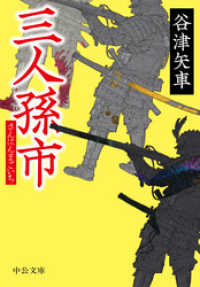
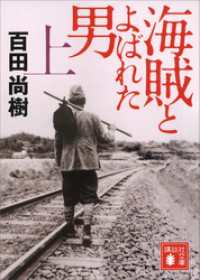
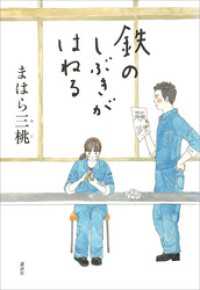

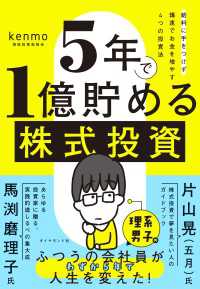

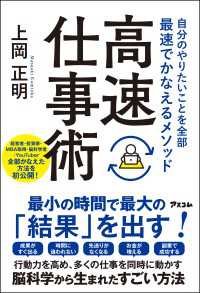

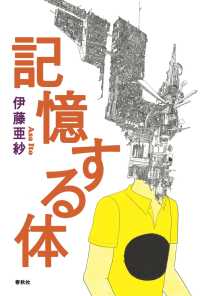

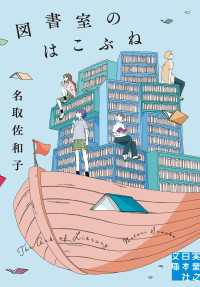
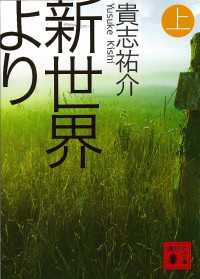
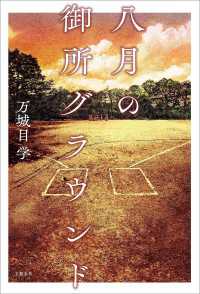

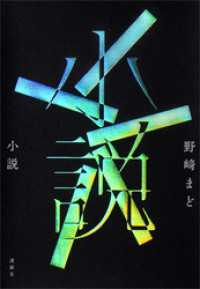
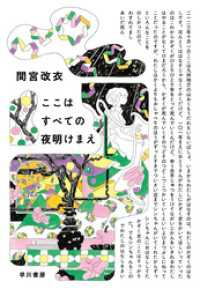
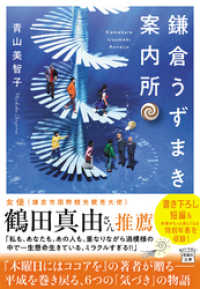
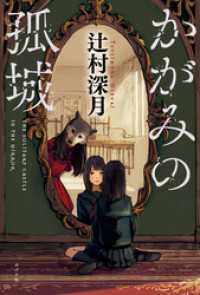
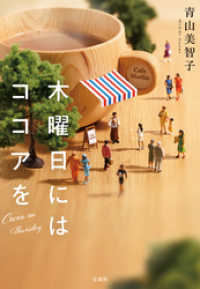
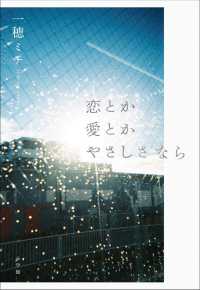

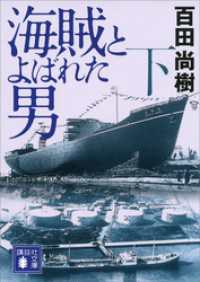
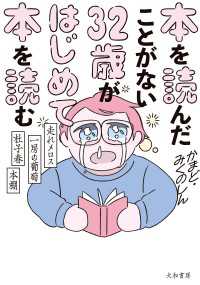
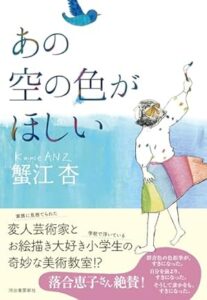

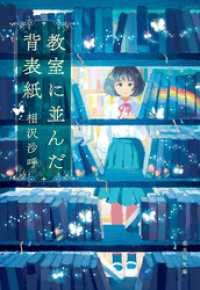

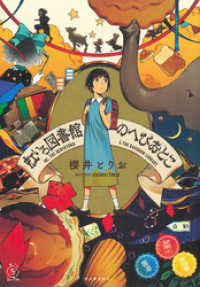
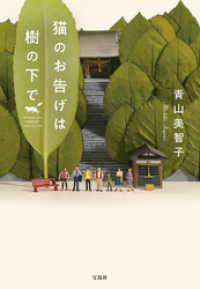


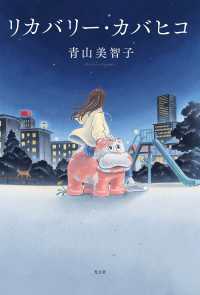
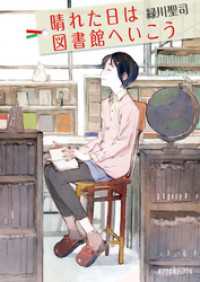



コメント