「最終面接も通過、あとは内定だけ…」そんなタイミングで行われる“リファレンスチェック”。
この一通の電話やメールが、あなたの採用を大きく左右するかもしれません。
近年、日本企業でも導入が進んでいるリファレンスチェック(推薦者照会)は、前職の上司や同僚など“第三者の評価”を通じて、候補者の人物像を裏付ける手段として注目されています。
でも、こう思ったことはありませんか?
「推薦者がうっかり余計なことを言ったら…?」
「仲が良い同僚に頼めば大丈夫だよね?」
「現職にバレたらどうしよう…」
実際には、推薦者の選び方や事前の準備次第で“印象が大きく変わる”こともあれば、“内定が取り消される”ことすらあるのです。
この記事では、リファレンスチェックの実施企業や質問内容、依頼方法のポイントに加えて、「リファレンスチェックで評価が変わってしまったリアルな実話」を4つご紹介します。
さらに、失敗しないための準備ステップや、企業側の視点・トレンドにも触れ、転職活動中のあなたが安心してリファレンスに臨めるよう、実践的な知識を網羅しています。
これから転職活動を進める方も、「今ちょうどリファレンスを依頼された…!」という方も、ぜひ最後まで読んでみてください。
あなたの印象は、まだ変えられます。
リファレンスチェックで印象が変わった体験談4選
リファレンスチェックは“形式的な手続き”ではなく、あなたの印象を大きく左右するプロセスです。
ここでは、実際に「推薦者の発言によって採用評価が変わった」4つのリアルな体験談をご紹介します。
思わぬ落とし穴にハマってしまったケースも……。
成功と失敗の分岐点はどこにあったのか?
具体的なエピソードから学びましょう。
体験談① 営業部・28歳女性|元上司が“雑さ”を強調してしまった
大手メーカー系 IT ベンチャーの法人営業部で働いていた A さん(28 歳・女性) は、入社 5 年目に、もっとキャリアアップしたいと転職活動を開始しました。
書類選考・一次・二次面接と順調に突破し、最終面接では VP of Sales (営業担当副社長)が「カルチャーフィットも抜群。ほぼ内定だね」と笑顔で握手──。
その直後に届いたのが 「リファレンスチェックを行いたいので推薦者リストをください」 というメールでした。
A さんは、
「数字で評価してくれるあの部長に頼めば間違いないはず。売上 120%達成の立役者って言ってくれてたし…」
と、推薦者に選んだのは元上司の「営業部長(50 代男性)」
ところが、この部長は 成果至上主義で細部に厳しい タイプ。
リファレンス会社からの電話でこう話したといいます。
- 「A はフットワークが軽くて契約を取りに行く姿勢は一流」
- 「反面、提案書の誤字や CRM への入力漏れが散見された」
- 「数字を優先するあまり、顧客フォローが後手になることがあった」
部長としては 長所短所を公平に 伝えたつもりでしたが、受け取った選考側は 「顧客志向<数字優先」でクレームリスクがある人物 と判断。
結果、最終評価会議で “採用見送り” が決定しました。
A さんは後日、部長から「正直に答えたら悪かったのか?」と言われショックを受けます。
しかし振り返ると、部長との 1on1 は最低限で、自身の成長や改善努力を十分に共有していなかった と痛感。
「そこを補足してほしい」とお願いさえしていれば…と大きな後悔が残りました。
✔ どうすればよかったか? ― 実践ステップ
- 相手選び
- 部長ではなく、日常的に同行し自分の改善を認めてくれた 課長 や シニア先輩 を推薦。
- 事前説明
- 「次の会社はスタートアップで“顧客体験”を重視している」と背景共有。
- 自分が取り組んだ 提案書テンプレート改善 や 顧客フォロー自動化 施策を資料で共有。
- 意図共有
- 「リファレンス回答が最終判断に直結するので、強みと改善中ポイントをバランスよく伝えてください」と依頼。
- Zoom で 15 分リハーサルを行い、想定質問と回答ニュアンスをすり合わせる。
体験談② 開発部・33歳男性|コードレビューに厳しかった上司に依頼して失敗
B さん(33 歳・男性) は Web 系 SIer の開発部在籍。
PHP/Laravel をメインに 6 年、サブリーダーとして要件定義からリリースまで担当してきました。
次は プロダクト志向のベンチャーでフルスタックエンジニア を目指し、CTO 面接まで通過。
ここでも最後の壁がリファレンスチェックでした。
推薦者は「技術にうるさい直属上司(40 代前半男性)」
B さんは「実力を一番見ているのは上司だから」と依頼しましたが、この上司は “完璧主義で 1 行のコードスタイルにも妥協しない” 性格。
リファレンス電話で…。
- 「B の成長意欲は高いが、可読性より開発スピードを優先しがち」
- 「レビューで指摘すると反論し、納期ギリギリで修正対応することがある」
──と 技術課題を中心 に回答。
ベンチャー側は「スピード重視は歓迎だが、指摘への受け止めが弱いのは文化に合わない」と判断し、不採用に。
B さんは Slack で「残念だったが事実だから仕方ない」と上司から DM を受け取り、ショックと後悔が入り混じる結果に…。
✔ どうすればよかったか? ― 実践ステップ
- 相手選び
- 同じプロジェクトの プロダクトオーナー や テックリード で、モダン開発スタイルを理解している人物に依頼。
- 事前説明
- ベンチャーが重視するのは 課題解決の速さ+チームワーク。
- 過去に ペアプロ で品質を担保した事例や CI/CD 導入 でレビュー負荷を下げた成果を共有。
- 意図共有
- 「技術負債を返済する姿勢と、レビュー指摘を学びに変えたエピソードを強調してほしい」と具体的に要請。
体験談③ マネジメント部門・35歳女性|“仲の良い同僚”が逆効果
C さん(35 歳・女性) は、事業企画部で チーム 8 名 を率いるマネージャー。
海外展開中の外資系企業に応募し、英語面接もクリア。
リファレンス先として「プライベートでも仲良し」の同僚 D さんを指名しました。
推薦者の一言が採用側に誤解を与える
D さんは気さくな性格。
調査電話で冗談まじりに…
「C は指示が速いけど、たまにタスクを丸投げして “お願いね〜” で終わることあるんです(笑)」
と笑い話を披露。
採用担当は “Delegative Manager(丸投げ型マネジャー)” と懸念し、当初予定の マネージャー職 から シニアアソシエイト職 へポジションを変更。
C さんは “降格オファー” と受け取り辞退しました。
✔ どうすればよかったか? ― 実践ステップ
- 相手選び
- 同僚ではなく、チームメンバーで直接指導を受けた 部下(成長をフォローした実績を語れる人)が最適。
- 事前説明
- 外資で見られるのは「People Development」。部下育成で KPI を 120%達成した事例を共有。
- 意図共有
- 「軽い冗談は誤解を生むので、事実をビジネスライクに伝えていただけると助かります」とお願い。
体験談④ 経理部・42歳男性|リストラの真相が誤って伝わる
製造業で 経理課長 を務めていた D さん(42 歳・男性)。
会社の組織再編で「希望退職」を選択し、スタートアップの CFO アシスタント職へ応募しました。
推薦者には「経理部長(50 代男性)」を指名。
ところが、部長はリファレンス電話でこう語りました。
「構造改革で退職対象に上がっていた」
「最後の年度でチームの残業管理が不十分だった」
D さんは「円満退社だった」と説明していましたが、面接先が受け取ったのは 「パフォーマンス低下 → 希望退職対象」 という印象。
結果、内定は取り消し。
✔ どうすればよかったか? ― 実践ステップ
- 相手選び
- 部長よりも、共同プロジェクトで財務改善を行った 外部監査対応リーダー など第三者性の高い推薦者を選ぶ。
- 事前説明
- 希望退職は「自発的なキャリアシフト」であり、経費削減策のプロジェクトを完遂→退職 という流れを共有。
- 意図共有
- 「再編時の評価はプラスだった」ことを数字(残業 25%削減)で補足してもらうよう依頼。
まとめ|リファレンスチェックで印象が変わる理由と対策のコツ
リファレンスチェックは 「第三者の一言」が採用結果を左右 する最終審査。
リファレンスチェックで“印象のズレ”や“評価の誤解”を防ぐためには、事前の準備が何よりも重要です。
特に大切なのが、次の3つのステップを丁寧に実行することです。
- 推薦者の選定
- 事前説明
- 意図共有
① 推薦者の選定
まず最も重要なのは、「誰に頼むか」です。リファレンスチェックでは、あなたの仕事ぶりや人柄を“客観的に評価できる人”に依頼することが求められます。
単に仲が良いという理由ではなく、実務をよく知っていて、あなたの強み・貢献を具体的に語れる人物を選びましょう。
上司や同僚、部下、外部パートナーなど、職種や経験年数に応じて適切な推薦者が異なりますが、大切なのは“あなたの価値をきちんと説明してくれる人”であること。
そうすることで、単なる主観的評価ではなく、事実に基づいた信頼性の高いコメントを企業に届けることができます。
② 事前説明
推薦者があなたをどう語るかは、事前の説明内容に大きく左右されます。
リファレンス先企業のカルチャーや職務内容、評価されそうなポイント(たとえば「マネジメント力」「協調性」「スピード感」など)を事前に共有することが不可欠です。
可能であれば、資料や職務要件のスクリーンショットを用意したり、「こういう質問をされるかもしれません」「そのときはこういうエピソードを伝えていただけると助かります」といったように、質問想定とエピソードのセットで伝えておくのが理想です。
この準備によって、推薦者が企業の意図を汲み取りやすくなり、「ちょっとズレた例え」や「評価軸と違う話題」で印象を損ねてしまうリスクを防げます。
③ 意図共有
最後に、「リファレンスチェックが合否に影響する」という現実を、推薦者にしっかり伝えておくことが大切です。
「ちょっと軽く頼んでみた」ではなく、「あなたの回答が、私の未来を左右する可能性がある」ことを明確に共有しましょう。
さらに、可能であれば事前に模擬インタビューを行い、どのような質問が来そうか、そのときにどう答えてもらえると良いかを練習しておくとベストです。
このように準備することで、推薦者も「自分の発言に責任がある」と真剣に向き合ってくれるようになり、余計なネガティブ発言や、誤解を招く発言を未然に防ぐことができます。
この3ステップを丁寧にこなすだけで、リファレンスチェックが“不安要素”から“内定後押しの材料”へと大きく変わることを、実例でもお分かりいただけたはずです。
選考後半に差しかかるタイミングこそ、自分の強みと魅力を“他者の口から”正しく伝えてもらうための戦略的なアクションが求められます。
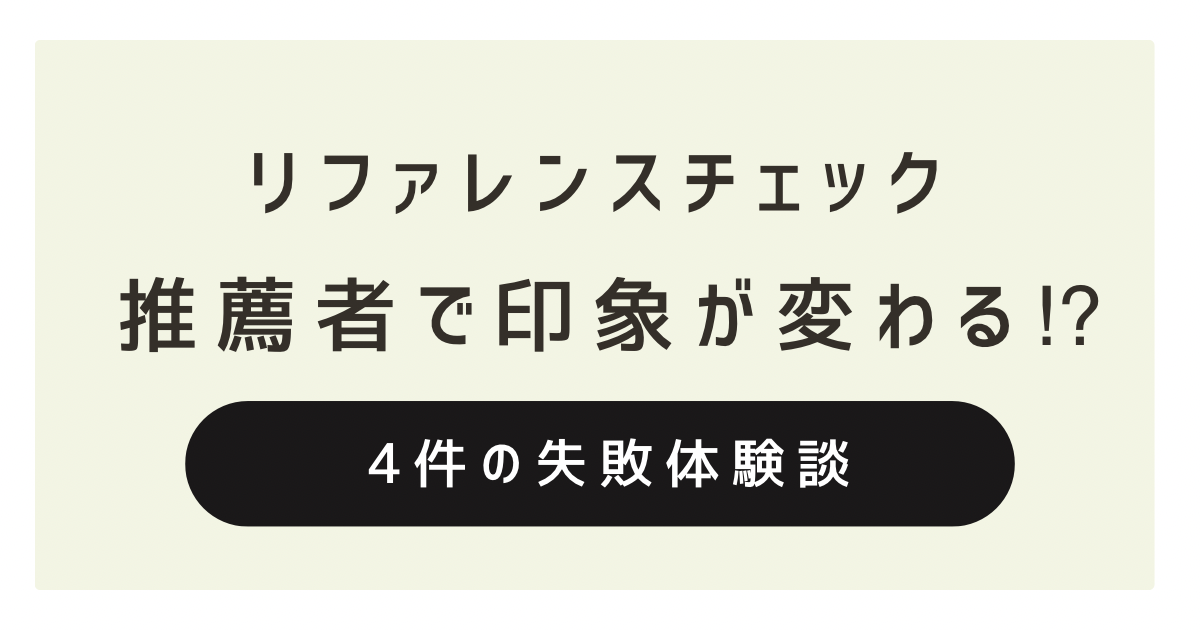
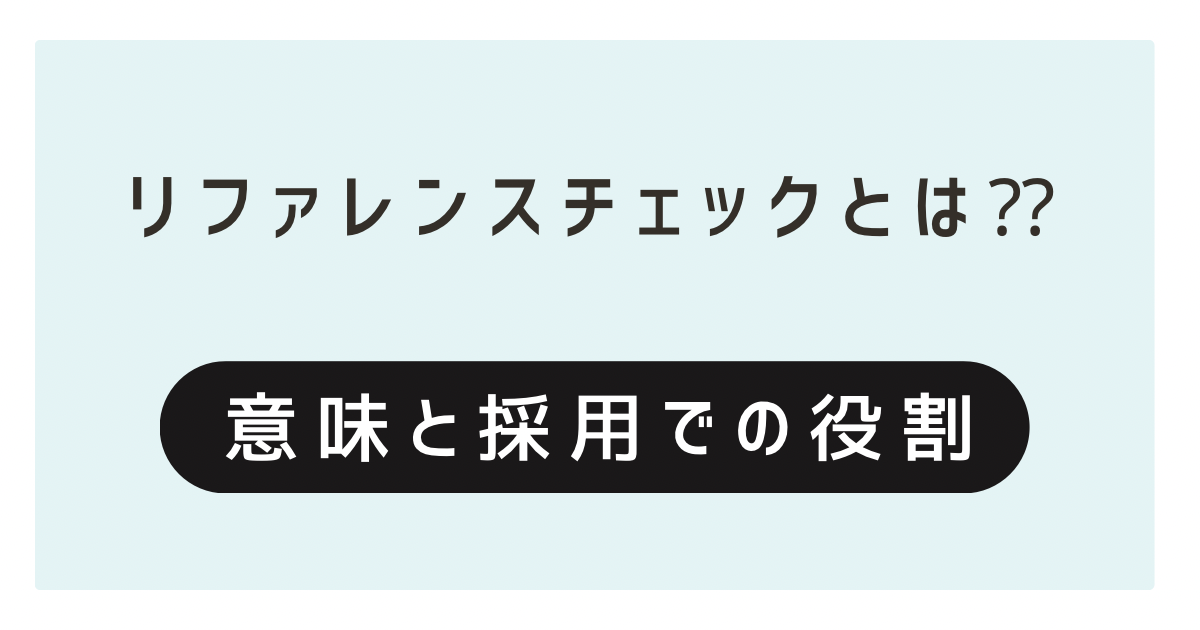
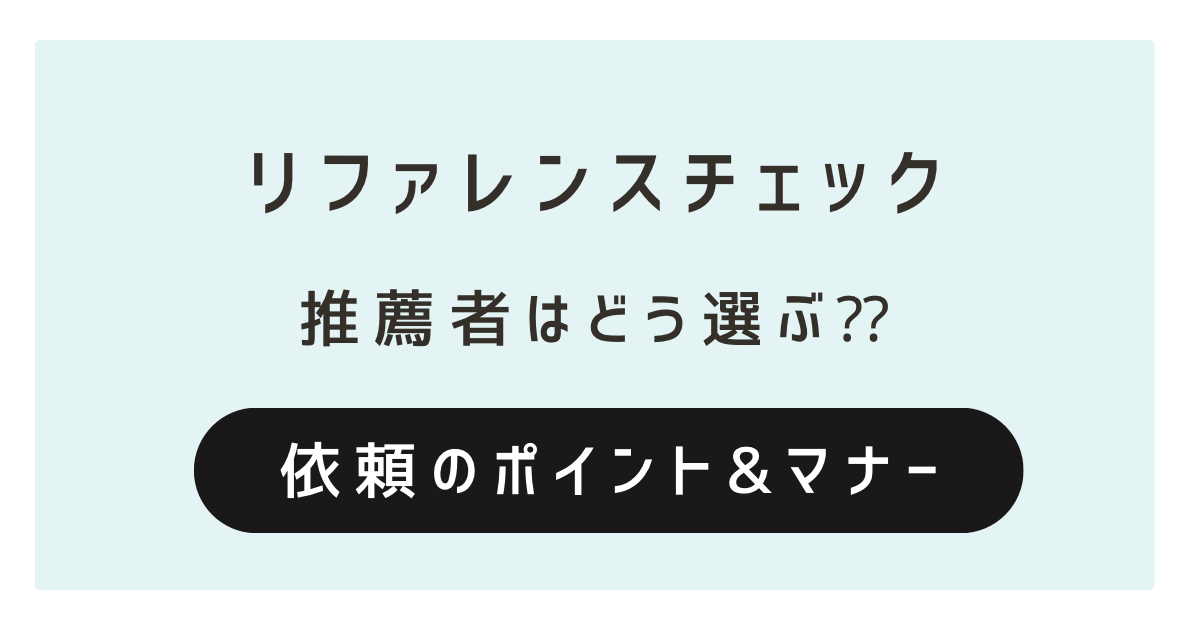
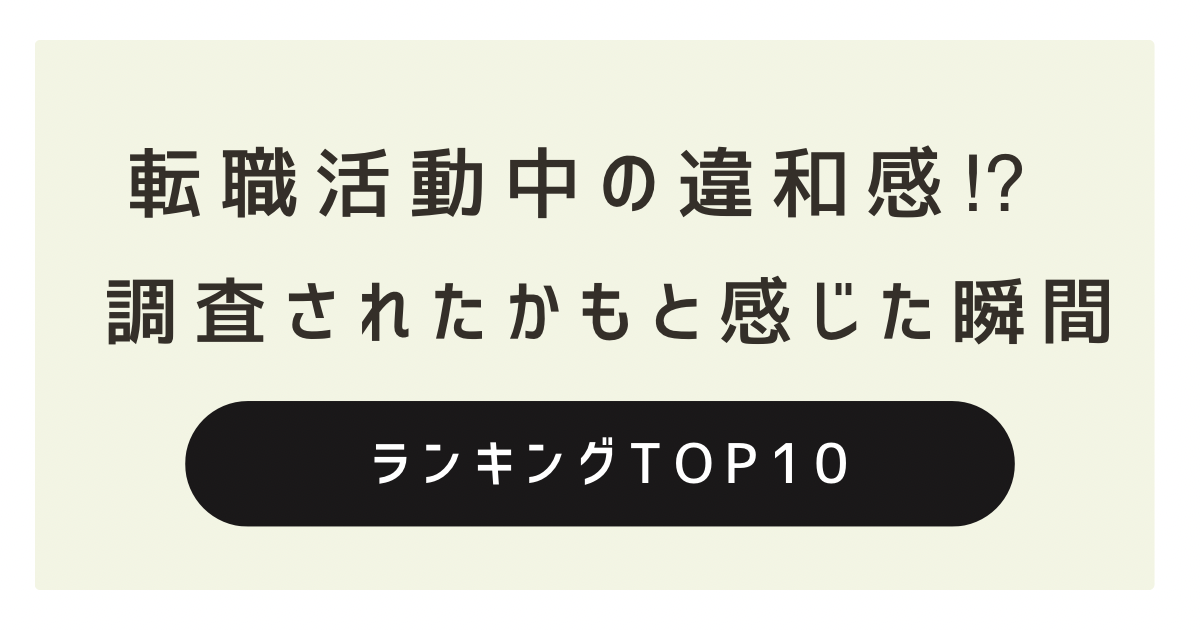
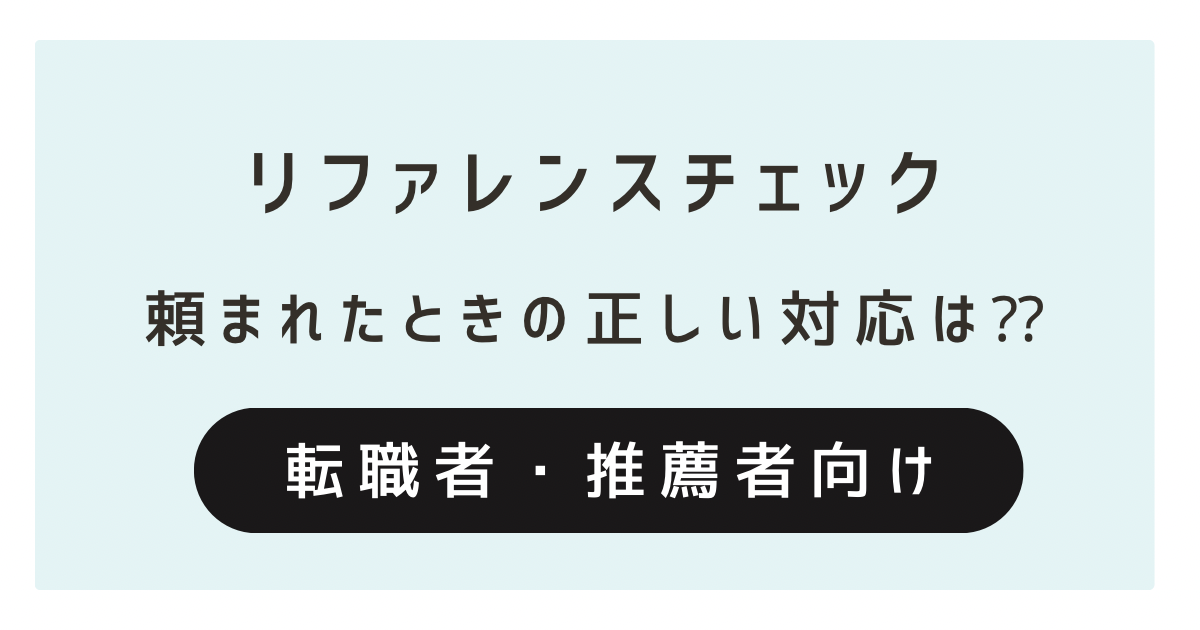
コメント