就職活動や転職の面接で「バックグラウンドチェック」や「リファレンスチェック」という言葉を耳にしたことはありますか?
「採用前に過去を調べられる」「SNSや職歴まで見られる」と聞いて、不安になる人もいるでしょう。「もしかして違法なんじゃないか?」という疑問もよく聞きます。
本記事では、「バックグラウンド チェックとは何か」「リファレンスチェックとは何か」を整理したうえで、日本国内でそれらが違法になるのかどうかを、判例や法律、実例を交えて解説します。
「バックグラウンドチェック 採用」「バックグラウンドチェック 内定取り消し」「リファレンスチェック 違法」など気になるキーワードにも触れます。
読み終わるころには、「どこまで調べられるか」「何がリスクか」「自分はどう対応すればいいか」がはっきりするはずです。
バックグラウンドチェックとは・リファレンスチェックとは
バックグラウンドチェックとは
「バックグラウンドチェック」は、採用(新卒・中途)や契約・入社後などのフェーズで、候補者の過去の経歴、信用情報、犯罪歴、破産歴、訴訟歴、SNSでの公の発言、職歴・学歴などを調査するプロセスを指します。日本語で言えば「採用調査」「身元調査」「バックチェック」など。
「バックグラウンドチェック どこまで」調べるかは、企業のポジションや業務内容、法的制限などによって変わります。実際、調査内容は「職歴」「学歴」「破産歴」「犯罪歴」「SNSの投稿」「信頼性・人物像」など多岐にわたることがあります。
リファレンスチェックとは
一方「リファレンスチェック」は、候補者が提示する推薦者(前職上司・同僚・取引先など第三者)や、現職・過去の職場で実際に関わった人から、候補者の勤務状況・成果・人柄・業務遂行能力・コミュニケーション能力などを聞き取る調査です。バックグラウンドチェックの中の1手法と位置付けられることも多いです。
リファレンスチェック実施にあたっては、「候補者の同意」「どの推薦者にするか」「どの質問をするか」がポイントとなります。
日本における法制度とチェックの合法性
調査が「違法になるかどうか」は、どういう法律が適用されるか・どのように実施されるかによります。
ここでは主に以下の法律や制度が関係します。
- 個人情報保護法
- 職業安定法
- 労働契約法
- 憲法における差別禁止、プライバシーの権利
個人情報保護法
個人情報保護法は、個人を特定できる情報(個人データ)を取り扱う場合、その個人から適切に同意を得ること、目的を明らかにすること、必要な範囲での利用に限定すること、不要になったら適切に廃棄することなどを定めています。
また、「要配慮個人情報」というカテゴリ(健康・病歴・信仰・犯罪歴など)に属する情報は、特に慎重な取扱いが必要で、通常は本人の同意無しに取得・利用すると違法となる可能性が高くなります。
※参考:e-Gov法令検索. 「個人情報の保護に関する法律」. “第27条”.
職業安定法
職業安定法第5条の5などで、「求職者・採用候補者の個人情報を収集・保管・使用するときは、その業務の目的を達成する必要な範囲内で」「目的を明示し」「本人の同意を得ること」が規定されています。
労働契約法/解雇・内定取り消しのルール
日本では「内定」も労働契約の一形態とみなされ、「解雇権濫用法理」も働く場合があります。内定後に一方的に内定を取り消すには、合理的かつ客観的な理由が必要とされます。単に印象が悪かった、ちょっとしたSNSの書き込みだけ、採用の「予想外」だったといった理由では認められないケースが多いです。
憲法・差別禁止・プライバシー
出身地、国籍、信条・宗教など、採用と直接関係がない属性を調査・選考材料とすることは憲法上の差別禁止や職業選択の自由、信教の自由などに抵触する可能性があります。プライバシーの権利も含まれます。
違法になるケース・グレーゾーン|企業がやりがちなNGチェック例
「バックグラウンドチェック」「リファレンスチェック」は一歩間違えると法的トラブルに発展するリスクがあります。ここでは、実際に問題となりやすい違法・グレーゾーンの例を具体的にご紹介します。
【NG①】本人の同意なしに調査を実施
【NG例】
「内定者に黙って、前職の上司に電話して在籍確認」
「応募者のSNSを勝手にチェックして情報を保存」
【なぜ違法?】
→ 個人情報保護法・職業安定法により、本人の同意なく個人情報を収集・利用するのは禁止されています。
無断で調査会社に外注した場合も同様に違法となる可能性があります。
【NG②】採用と関係のない情報を調査
【NG例】
「婚姻状況や家族構成まで聞き出す」
「信仰・宗教・思想などを面接で探る」
【なぜ違法?】
→ 要配慮個人情報(センシティブ情報)に該当する内容は、特別な同意がない限り収集禁止。
また、憲法で保障される信教の自由・差別禁止にも抵触するおそれがあります。
【NG③】情報を無断で第三者に提供する
【NG例】
「調査会社に候補者の履歴書情報を勝手に共有」
「推薦者を本人に伝えずにヒアリング」
【なぜ違法?】
→ 外部委託先に個人情報を渡す場合も、本人の同意が必要です。
また、委託管理責任を怠ると、企業に行政指導や損害賠償請求が来ることも。
【NG④】SNSやネット上の情報を過度に監視
【NG例】
「TwitterやInstagramを隅々まで漁って“印象”で判断」
「非公開情報や友人間の投稿を無理やり取得」
【なぜ違法?】
→ SNSは公開情報ならばチェック可能ですが、プライバシー侵害と紙一重。
不適切な引用や過剰な判断は、名誉毀損や個人の権利侵害になる恐れがあります。
【NG⑤】内定後に結果だけで取り消す
【NG例】
「雰囲気が合わなそうだから内定取り消し」
「SNSで過去にネガティブ発言があった」
【なぜ違法?】
→ 労働契約法に基づき、内定取り消しには“合理的理由”が必要です。
明確な経歴詐称などがない限り、後出しで内定を取り消すのはリスク大です。
【NG⑥】説明責任を果たさず一方的に落とす
【NG例】
「リファレンスチェックの結果が“微妙”だから不採用。でも理由は説明しない」
【なぜ違法の可能性?】
→ 法律違反とは言い切れないものの、透明性・公正性を欠く選考として企業の信頼を損ないます。
口コミサイトやSNSで炎上し、レピュテーションリスクにつながることも。
ワンポイント:企業が違法にならないための対策
これらはすべて、「調査そのものが悪い」のではなく「やり方」に問題があるため、同意・目的・範囲・使い方がクリアであるかが鍵になります。
「どこまで調べられるか」:調査内容の範囲と実例
「バックグラウンドチェック どこまで」「バックグラウンドチェック 内容」というキーワードで調べると、実際に企業が調査する範囲・内容には相当な幅があります。ここでは、調査されやすい項目例と、どこまでが許容範囲かの見極め方を具体例で示します。
よく調べられるバックグラウンドチェックの項目
企業が採用前に実施するバックグラウンドチェックでは、以下のような項目が比較的よく調査対象になります。どれも採用の適性や信頼性を見極めるために活用されています。
学歴の確認
- 卒業証明書の有無
- 在籍期間と卒業年度
- 大学・高校名、専攻・学部
- 学歴詐称がないか(中退を卒業と偽るなど)
職歴・在籍確認
- 勤務していた企業名・部署名
- 入社日と退職日(時系列の整合性)
- 雇用形態(正社員/派遣/業務委託など)
- 退職理由の確認(リファレンスチェックでヒアリングされる場合も)
勤務態度・業績・人物評価
- リーダーシップや責任感の有無
- チームでの協調性・対人関係スキル
- 勤務状況(遅刻・早退・欠勤の頻度など)
- 上司や同僚の評価(推薦者のコメント)
SNSやインターネット上の公開情報
- Twitter/Instagram/Facebook/Xなどの投稿内容
- 炎上歴・過激な発言の有無
- 公開プロフィールや写真からの印象
- 過去の活動や副業履歴の把握
信用・コンプライアンス関連
- 破産歴・債務整理歴(官報で調査)
- 訴訟歴(裁判所記録などから照会)
- 反社会的勢力との関係有無(反社チェック)
- 経歴・資格証明との整合性チェック
必要に応じて、これらの調査項目は外部の調査会社に委託される場合もあります。
特に外資系企業や大手企業では、このようなチェックをルーティンとして取り入れているケースが多く見られます。
企業側が「調べない・調べるべきでない項目(または慎重に扱うべき)」
実例
- 採用候補者が履歴書に「前職・在職中」と記載していたが、実際には在籍期間や入社日が異なっていたケースを、バックグラウンドチェックで発覚。
- SNSでの発言や投稿内容が公であり、業務や企業イメージに影響を及ぼす可能性があると判断され、企業が調査対象とすること。
- 外資系企業では「現職にバレる」「内定後チェック」「在籍確認」が組み込まれていることも多く、「バックグラウンドチェック 現職 バレる」という不安が聞かれる。
デジタル・スマホ・SNS関連の調査
「バックグラウンドチェック スマホ」「android」「iphone」「SNS」などのキーワードを元にすると、スマホアプリの動作でバックグラウンドチェックという言い方をされるケースと「採用目的でのチェック」が混同されることがあります。
技術的な意味で「バックグラウンドで動くアプリ」の権限チェック等とは異なりますが、採用背景のチェックでスマホでのSNSを確認するケースがあるのは事実です。
こういった場合も「公開されている情報か」「本人の同意があるか」が重要。
プライバシー権の観点から、無断でスマホにアプリを入れさせて調べる、あるいは連絡先・写真を無断で閲覧するなどは明らかに違法・不適切になります。
チェックを受ける人の立場から、不安と「落ちる確率」「バレるかどうか」
チェックされる側、応募者・転職希望者の不安は多いです。「落ちる」「秘密が漏れる」「現職にバレる」「同意なしでされる」など。ここでは実情と対処法を整理します。
不安としてよくあるもの|候補者が感じやすい心配ポイント
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックを受ける立場になると、さまざまな不安がつきまとうものです。ここでは、多くの転職者・求職者が抱える代表的な不安を整理してご紹介します。
採用に落ちるのではないかという不安
現職にバレるリスクへの恐れ
同意を取らずに勝手に調査されるのでは?
結果がいつ来るか分からず不安になる
SNS投稿など、過去の言動が原因で不利になるのでは?
推薦者に頼みにくい、断られるかもという心配
こうした不安を減らすには、「何を調査されるか」「どう同意を求められるか」を事前に企業に確認することが大切です。
また、SNSの過去投稿を整理したり、信頼できる推薦者を早めに相談したりすることで、備えることができます。
落ちる確率・何が原因で不採用になるか
数字で明確な統計は日本では限定的ですが、複数の記事から以下の傾向が読み取れます。
- 転職や中途採用で経歴詐称が発覚することはそれなりに起きており、企業側はそれを避けたいという意識がある。
- 「バックグラウンドチェック 落ちる」原因としては、虚偽の職歴・学歴、反社会的勢力等の関係、大きな犯罪歴、破産歴・訴訟歴など。これらが明らかであれば、不利になる可能性が高い。
- ただし、多くの企業はまず「書類・面接」で絞るため、バックグラウンドチェックが直接「落ちる原因」になることはそれほど多くないという意見もあります。CHECKされる頻度・重視される度合いは企業によってまちまち。
チェック後の内定取り消しは合法か?
「バックグラウンドチェック 内定取り消し」というキーワードがある通り、内定取り消しが実際に起きるケースもあり、それが合法・違法かは具体的事情によります。
合法とされるケース
- 経歴・学歴詐称:履歴書や職務経歴書に明らかな虚偽があり、それが入社前に判明した。
- 重大な犯罪歴や反社会的勢力との関係など、企業の信用を著しく損なうものや業務上支障があるもの。
- 必要な職務能力・資格を欠いていたことが判明した場合など。これらは合理的な理由として認められることがあります。
非合法・無効とされる可能性のあるケース
- 内定後に「印象が合わない」「雰囲気に馴染まなさそう」「遅刻が多いらしい」という主観的・曖昧な理由のみを理由とする内定取り消し。
- 採用選考と関係ない情報(病歴、信条、プライバシーの範囲内の私生活など)が理由である場合、合理性・社会的相当性を欠くと判断されること。
- 同意なしに調査を行い、その結果を理由に内定を取り消す場合、調査方法そのものが違法とされるため、取り消しも無効になる可能性。
内定取り消しリスクを下げる方法(企業側・候補者側の対策リスト)
バックグラウンドチェックやリファレンスチェックの結果によって「内定が取り消される」可能性を完全にゼロにすることはできませんが、リスクを最小限に抑える方法はあります。ここでは、企業側と候補者側のそれぞれに向けた具体的な対策リストをご紹介します。
企業側の対策リスト
内定取り消しが“違法”と判断されないようにするには、以下のポイントを押さえましょう。
候補者側の対策リスト
不安を減らし、内定取り消しリスクを下げるために、以下の準備をしておきましょう。
「内定取り消し」には法的なリスクも精神的なダメージも伴います。
企業も候補者も、調査の透明性”と“誠実なコミュニケーション”を大切にすることで、トラブルを避け、スムーズな採用につなげることができます。
実施企業や採用現場の実態
実際に日本でバックグラウンドチェック・リファレンスチェックを採用している企業や、チェックの普及度・手法には特徴があります。
普及度・外資系 vs 日系
外資系企業やグローバル企業では、リファレンスチェックを採用プロセスの標準にしているところが多い。特に幹部職・管理職ポジションなど。
一方、日系中小企業・スタートアップではコスト・手間・違法性への不安などから、あまり徹底していないところも多い。
調査会社を使うケース
調査会社に委託することで、職歴学歴の確認、データベース照合(破産歴・訴訟歴など)、SNS調査などを包括的に行うことが可能。
ただし、委託先の調査機関が適切に運用していなかった場合、違法行為・情報漏えい・プライバシー侵害のリスクがあるため、企業側には委託管理責任がある。
採用のタイミング
多くの企業は「内定前」にチェックを済ませたいと考えており、内定通知後では法的リスク・候補者の反発を招く恐れが高くなるため。
また、「内々定」段階でリファレンスチェックやバックグラウンドチェックを行う旨を求人票や面接時に説明しておく企業もあり、候補者にとって透明性を持たせる例が増えている。
まとめ
結論としては、バックグラウンドチェック・リファレンスチェック自体は日本国内で原則として違法ではありません。
ただし、調査をする人・企業が「同意を得る」「目的を明示する」「必要な情報に限定する」といったルールを守らなければ、個人情報保護法・職業安定法・労働契約法などに抵触する可能性があります。
違法になるケースはだいたい「本人の同意なし」「採用と無関係な・差別につながる情報の調査」「結果を使った内定取り消しが合理性を欠く」「プライバシー侵害が強い」など。
チェックされる側としては、自分の職歴・学歴・SNS公開内容を整えておくこと、推薦者との関係性を保っておくこと、またチェックの内容・方法を質問できるように準備することが重要となります。
あなたの場合はどうでしょうか?
自分の職歴に詐称はないか、SNSの投稿に後で後悔しそうなものはないか、一度見直してみませんか?
面接・内定の話が進んだら、「バックグラウンドチェック/リファレンスチェック」の実施タイミング・内容・同意方法を企業に確認することをお勧めします。
候補者として、自分がどの情報を提供するか・推薦者として誰を使うか、事前に準備しておくと安心です。
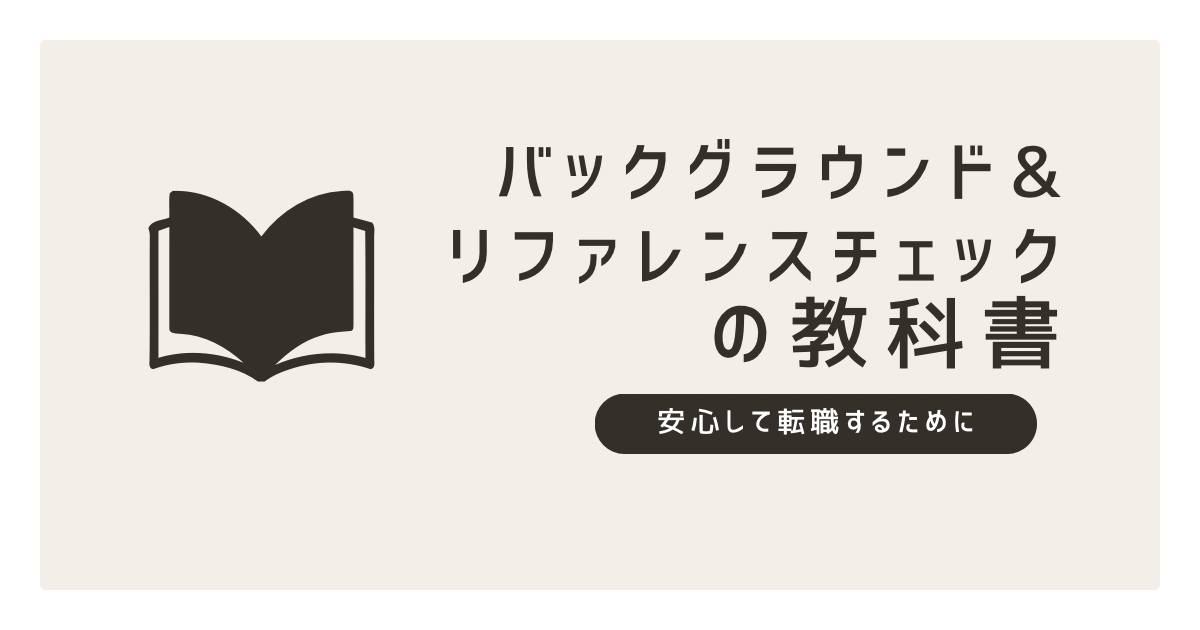
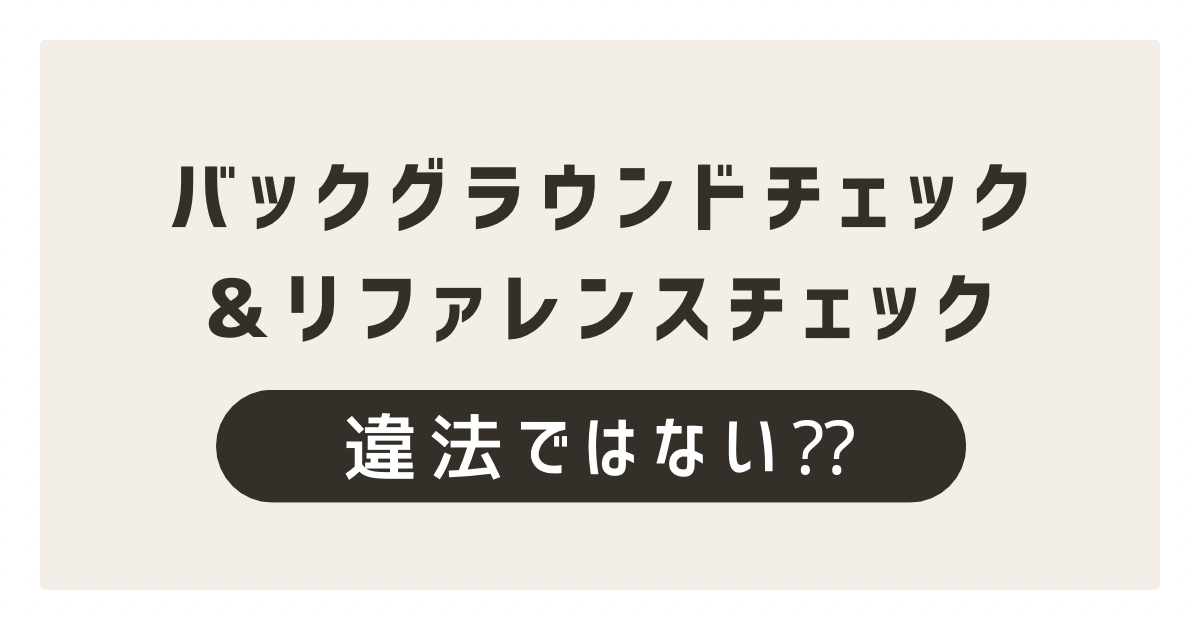
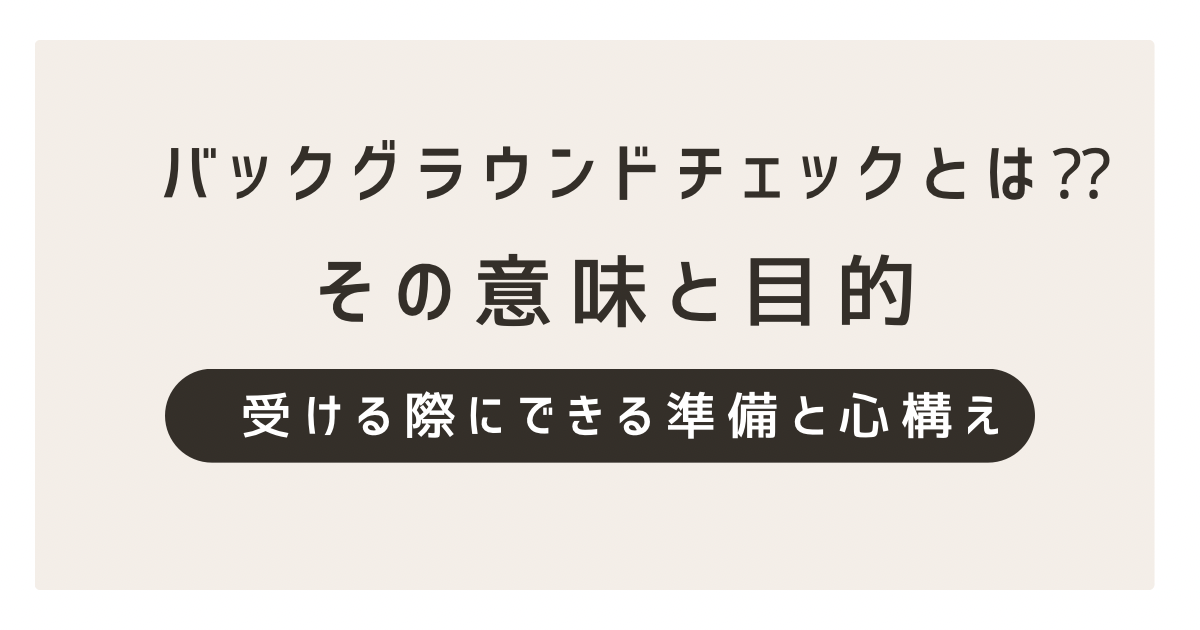
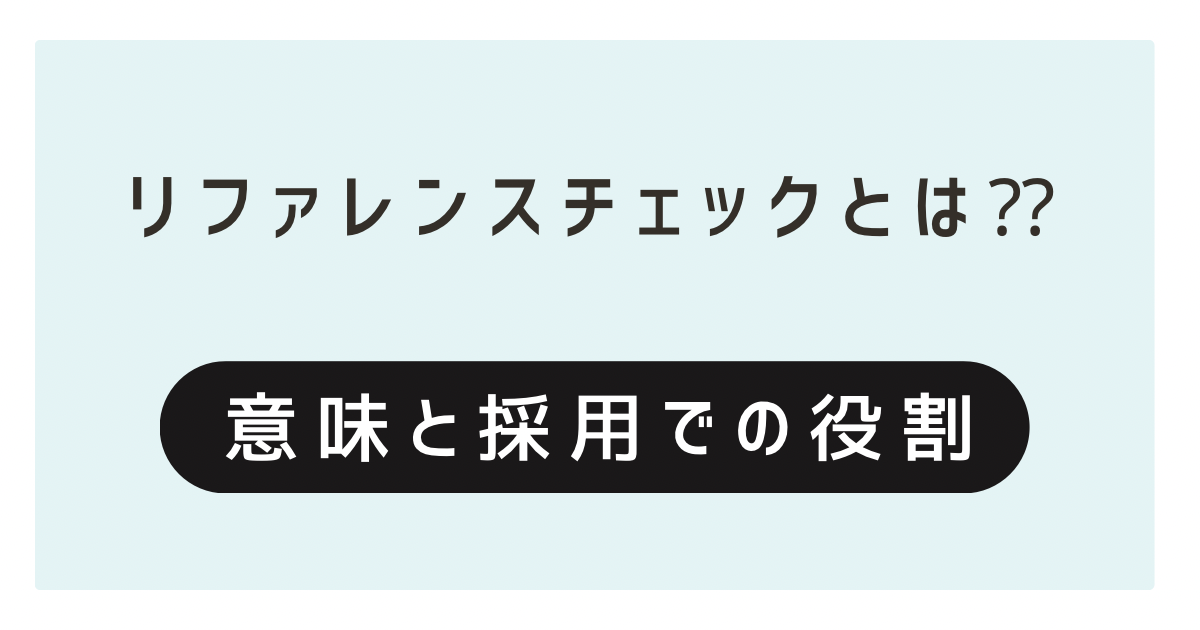
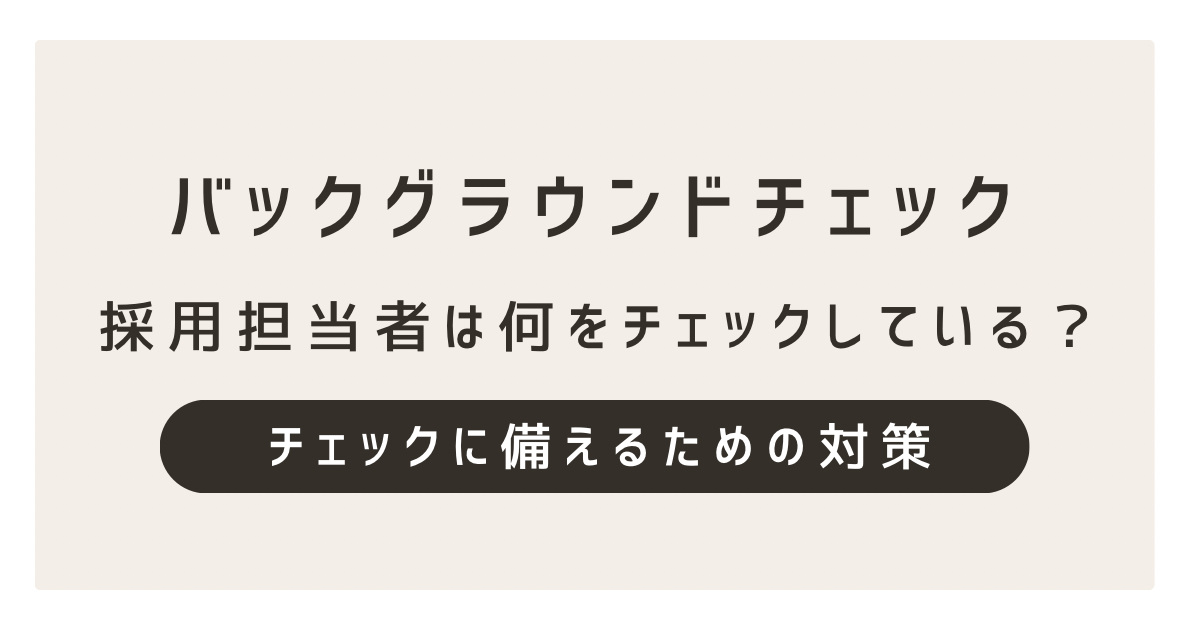
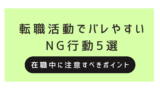
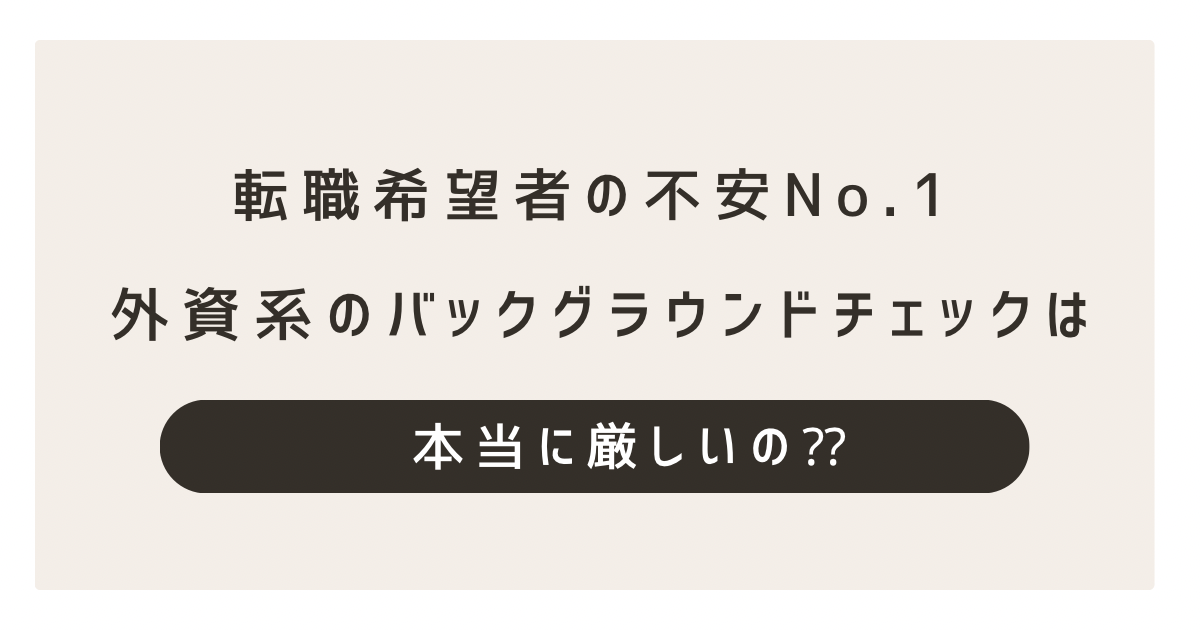
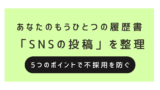
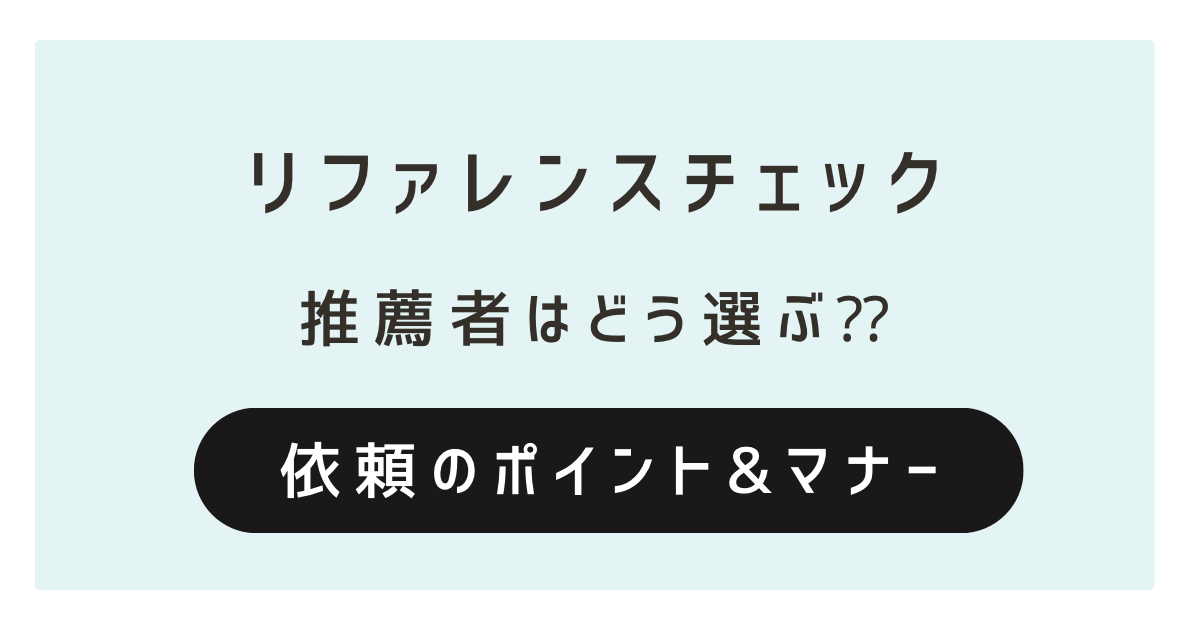
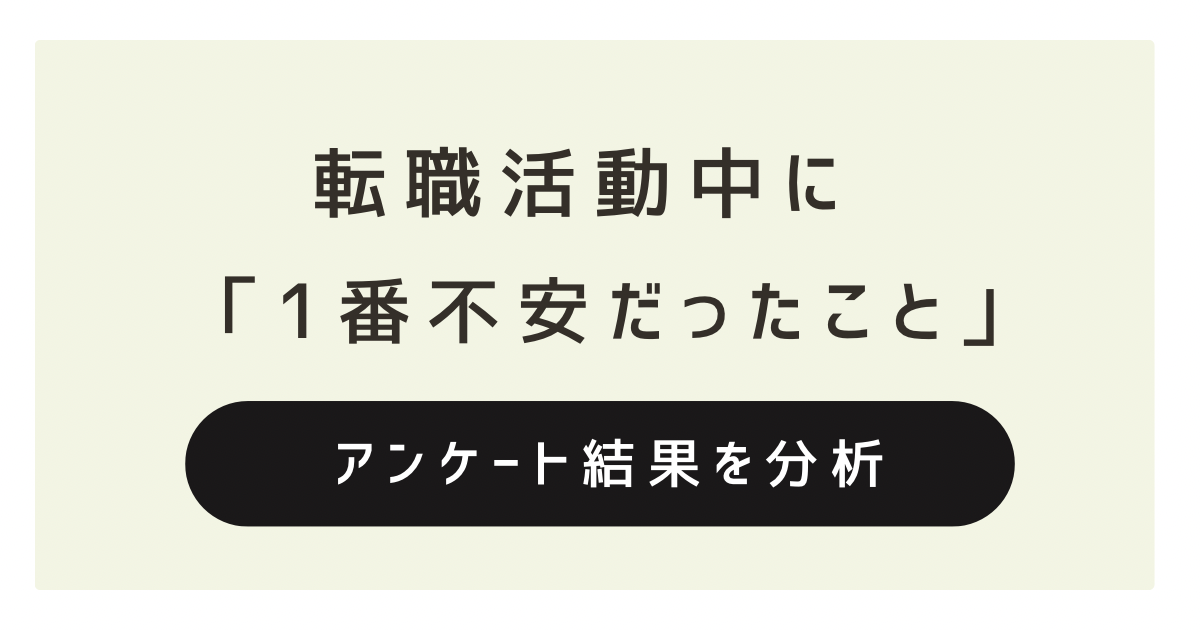
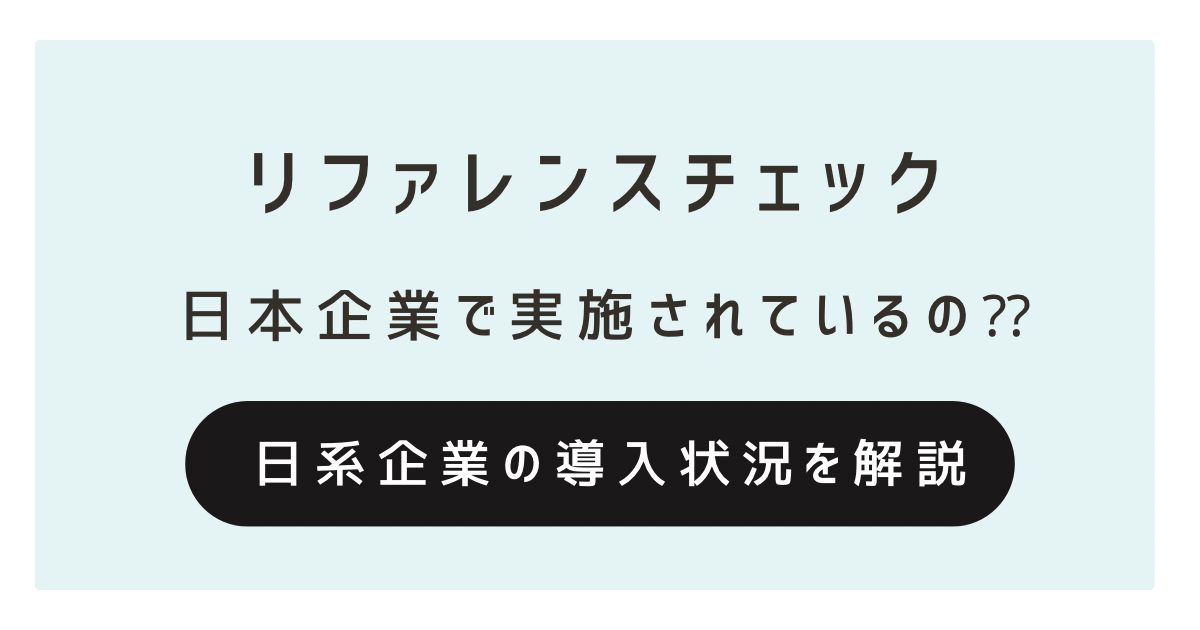
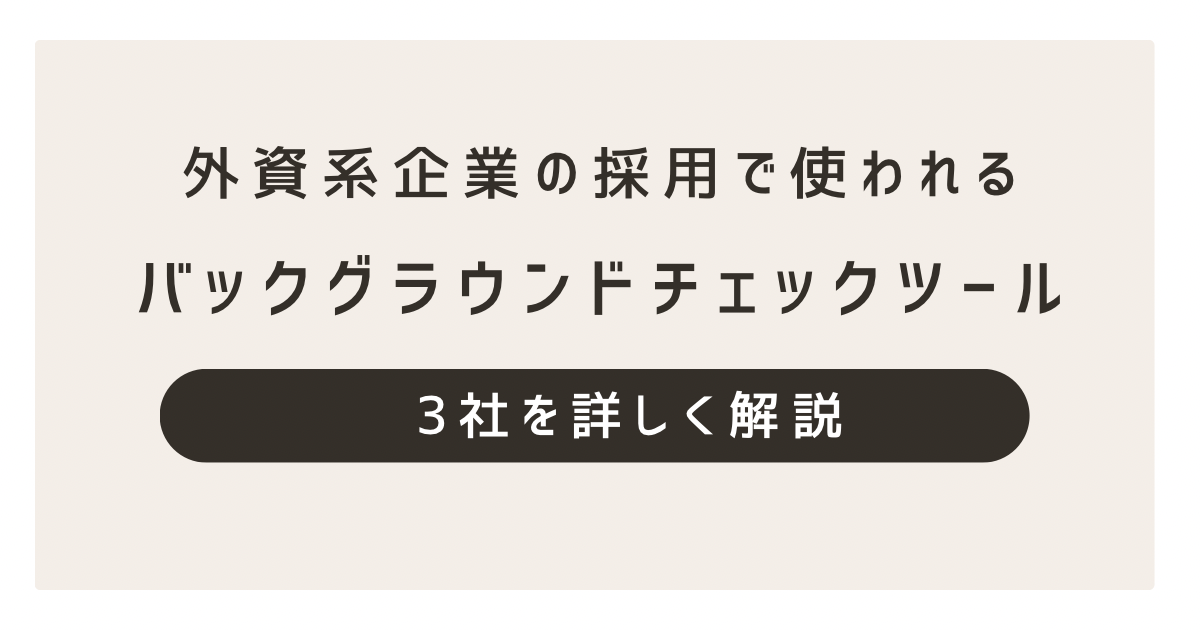
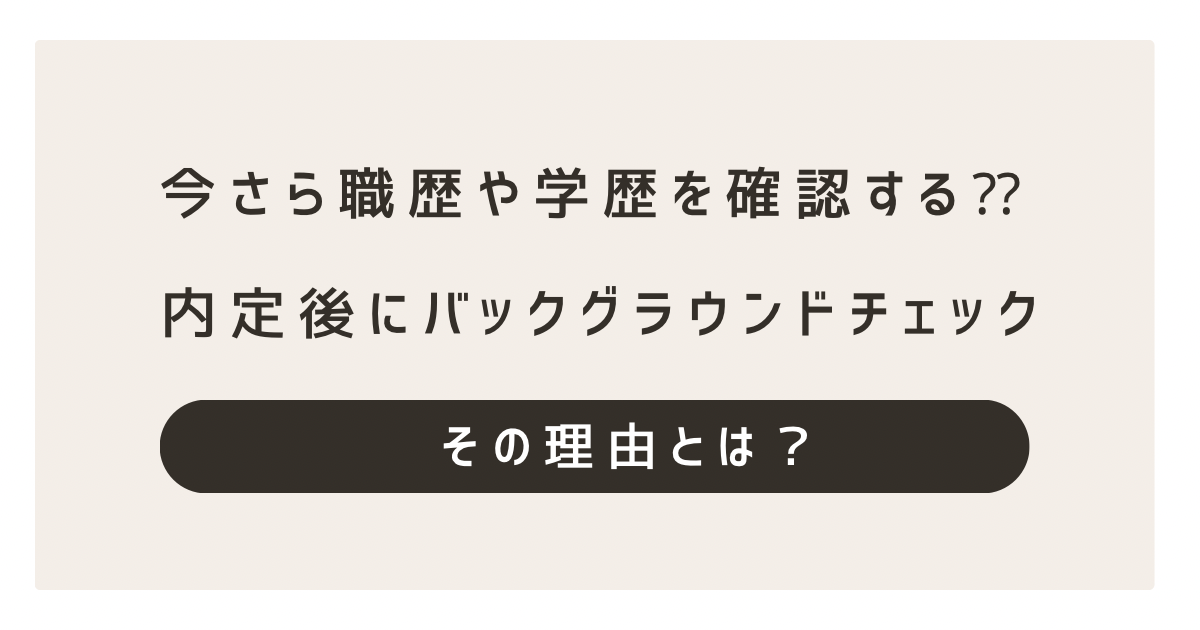
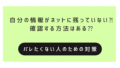
コメント